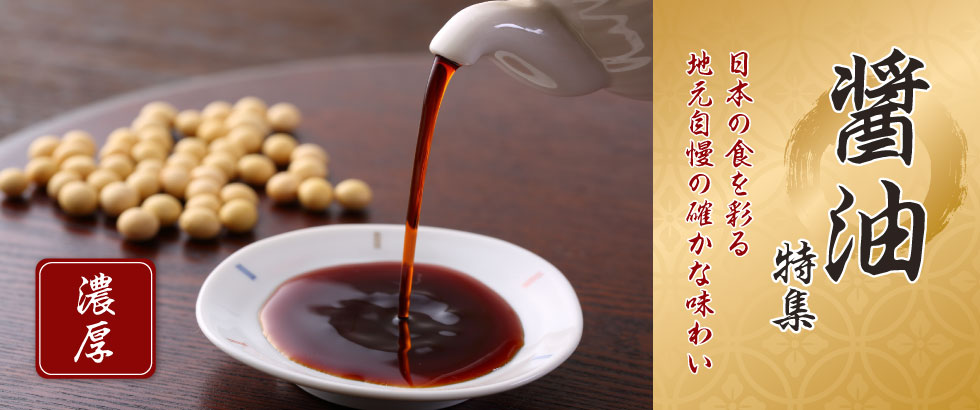
醤油は日本食には欠かせないもので、醤油を常備していない家庭は少数派なのではないでしょうか。ふるさと納税を利用すれば、自宅にいながら各地の珍しい醤油が手元に届きます。調理に使えばいつもの料理とは一味違ったものになるはずです。
北海道
-

キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L×6本 《千歳工...
[北海道千歳市]
寄付金額 12,000円
北海道 千歳市 ふるさと納税 返礼品
-

北海道羅臼町「羅臼逸鮮ギフトセット3種」しょうゆ、つゆ...
[北海道羅臼町]
寄付金額 12,000円
自然豊かな環境で育った羅臼昆布の旨味が詰まった調味料3種のセット
-
 冷蔵
冷蔵北海道産小麦使用 生ラーメン3種(醤油・味噌・塩) 計...
[北海道新ひだか町]
寄付金額 8,500円
一條製麺特製の生ラーメンの味噌・醤油・塩の3種類すべてが楽しめる欲ばりセット
-
 冷蔵
冷蔵旭川発 旭川鶏卵で人気上位のみ詰合せセット_00311
[北海道旭川市]
寄付金額 12,000円
半熟とろ~りで人気ナンバー1の半熟味玉、アスタキサンチン含有の温玉、燻製たまご、卵かけご飯専用醤油
-
 冷蔵
冷蔵大空町プレミアムセット全6回 OSA025
[北海道大空町]
寄付金額 110,000円
魅力あふれる北海道大空町の自慢の特産品を、全6回(隔月)お届けする定期便です!
-
 冷蔵
冷蔵厚岸産 殻付き牡蠣「マルえもん 2Lサイズ」30個とコ...
[北海道厚岸町]
寄付金額 45,000円
厚岸の殻付き牡蠣と、牡蠣を楽しめる加工品をセットにしました!
-

【さとふる限定】厚岸の牡蠣使用!金のかき醤油・金のオイ...
[北海道厚岸町]
寄付金額 5,000円
牡蠣の煮汁や牡蠣の身を使用したこだわりの金シリーズの調味料セットです
-

八雲みそ・醤油セット【Y-25】
[北海道八雲町]
寄付金額 12,000円
「二つの海」をもつ「八雲町」の老舗の味をお届けします。
北海道で使われている醤油は、全国的に最も普及している濃口(こいくち)醤油です。多くは、伝統的な製造法「本醸造」方式で造られています。
ふるさと納税のお礼品として用意されているのは、「鮭節しょうゆ」や「一番だし昆布しょうゆ」、厚岸(あっけし)産のかきを使った「金のかき醤油」、じゃがいも焼酎の風味が生きた「じゃがいも焼酎入り生しょうゆ」など多種多様です。「鮭節しょうゆ」は鮭節のだしが入った加工醤油のことで、旨みたっぷりで特にお刺身やお寿司などの魚料理に合います。
東北地方
-

藤勇醸造 富士醤油 1L 6本入り
[岩手県釜石市]
寄付金額 14,000円
120年愛される、三陸釜石ふるさとの味
-

【明治36年創業】老舗蔵元今野醸造自慢の吟醸醤油(1L×6)
[宮城県加美町]
寄付金額 14,000円
明治36年創業の老舗蔵元今野醸造自慢の吟醸醤油です。本格派の味わいをお届けいたします。
-

万能調味料 うまいたれ 1000ml × 3本 3L
[山形県米沢市]
寄付金額 11,000円
かつおだしがたっぷり入ったしょうゆ風万能調味料です。
-

SNSでも話題の便利な醤油「だし吟醸」500ml×2本
[宮城県加美町]
寄付金額 5,000円
これ1本で料理の味がキマルと大好評!便利な醤油だし吟醸
-
 冷蔵
冷蔵会津ブランド馬刺しセット【冷蔵】
[福島県会津若松市]
寄付金額 18,000円
厳選した大人気の会津ブランド馬刺し
-

万能調味料 うまいたれ 1000ml × 5本 5L
[山形県米沢市]
寄付金額 18,000円
かつおだしがたっぷり入ったしょうゆ風万能調味料です。
-
![完熟味噌こだわり1kg・吟醸味噌白糀1kg・万能つゆ1L・特級醤油1L4点詰合せ[4206-050] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/07111706_5b45ba92c3fd3.jpg)
完熟味噌こだわり1kg・吟醸味噌白糀1kg・万能つゆ1...
[宮城県白石市]
寄付金額 13,000円
宮城県白石市森昭のお勧め味噌・醤油・めんつゆセットをお届けします。
-

マルイ こいくち醤油 天印 1箱(1L×6本)諸井醸造...
[秋田県男鹿市]
寄付金額 11,300円
芳醇な味と香りが漂う抜群の仕立てです。県内の旅館・ホテルにて刺身用醤油としてご愛用して頂いております。かけ・つけ用・煮物を...
東北地方でも一般的には濃口醤油が使われていますが、いわゆる甘口醤油も広い地域で使われています。例えば秋田県や山形県には甘い醤油が多く、全体的に日本海側の地域では甘い醤油が好まれています。
秋田県のお礼品として用意されているのは、煮付けなどに特に合う甘口タイプの濃口醤油です。
青森県には芳醇で香り豊かな濃口醤油「寿」「小むら咲」があります。また津軽の大豆と小麦から造られた希少性の高い「津軽生醤油(きじょうゆ)」も用意されています。
福島県ではどんな料理にも合う本醸造の濃口醤油を用意しています。
関東地方
-

キッコーマン生しょうゆ3種セット G004
[千葉県野田市]
寄付金額 10,000円
密閉ボトルを使用したしょうゆの3種詰め合わせです。つけ、かけ、料理用等なくてはならない品々です。
-

ろく助塩 一生涯セット
[茨城県常総市]
寄付金額 16,000円
あら塩に、干椎茸・昆布・干帆立貝の旨みをプラスした調味塩と、ろく助塩で仕込んだ旨味醤油です。
-

キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ 62...
[千葉県野田市]
寄付金額 10,000円
通常の醤油と違い、「火入れ」(加熱処理)をしていない、しぼりたての生しょうゆです!
-

万能調味料3本セット(化粧箱入り) 「キムチ醤油」「キ...
[東京都瑞穂町]
寄付金額 7,000円
食べてみて『かけたり・つけたり』おいしさ無限大!
-

キッコーマン いつでも新鮮 超減塩しょうゆ 食塩分6...
[千葉県野田市]
寄付金額 17,000円
食塩分を66%カットした超特選規格の減塩醤油です!豊かな旨みと華やかな香り!
-

しょうゆ屋さんの調味料セット(幹J-3)
[茨城県ひたちなか市]
寄付金額 12,000円
老舗醤油蔵の万能調味料セット!食卓に「美味しい」の笑顔をお届けします。
-

【蔵元小田屋】割烹大吟醸醤油(720ml)&割烹酢(7...
[茨城県結城市]
寄付金額 17,000円
創業寛政元年 紬のふるさと結城の地で長年醸造業を営み、一流料亭や高級ホテルの料理長にも愛用されている
-

ヤマサ、鮮度生活醤油セット
[千葉県銚子市]
寄付金額 11,000円
ヤマサ醤油は明るい色と香りのよい醤油として、プロの方々からも高い評価をいただいております。
関東地方は、全ての料理に濃口醤油を使う傾向が高く、甘い醤油を使う地域もないため、関東地方出身者には甘い醤油が存在することさえ知らない人も多いようです。
千葉県は醤油の生産が盛んで、大手醤油メーカー「キッコーマン」「ヤマサ醤油」「ヒゲタ醤油」の工場があります。大手メーカー以外にも千葉県には醤油の蔵元がいくつもあり、伝統的な天然醸造で12カ月以上熟成させたまろやかな味の濃口醤油「五郎左衛門」などを製造しています。
茨城県からは、杉の木桶でじっくり熟成させた「木桶仕込みしょうゆ」やスッキリした旨みと芳醇な香りの「丸大豆しょうゆ潮来(いたこ)」などのお礼品があります。
中部地方
-
 冷蔵
冷蔵黒富士農場人気No1セット
[山梨県甲斐市]
寄付金額 12,000円
たまご屋の作ったバウムクーヘンは、満足度No1。 卵かけごはんセットとコラボで二度美味しいセットです。
-

七福醸造の特選料亭白だし4本セット H001-088
[愛知県碧南市]
寄付金額 13,000円
毎日の食卓に大活躍できる特選料亭白だしの大容量サイズ
-

七福醸造の有機白だし3本セット H001-064
[愛知県碧南市]
寄付金額 11,000円
有機塩みりんを絶妙のバランスでブレンドした贅沢なだし入り白醤油
-

【加賀醤油】冨士菊醤油 濃口(こいくち) 並印 100...
[石川県加賀市]
寄付金額 5,000円
加賀市の食文化を支える一度使うと忘れられない旨口醤油
-

【お刺身にピッタリ!】奥能登・輪島の漁師が愛用するサク...
[石川県輪島市]
寄付金額 15,000円
奥能登・輪島で昔から親しまれているお醤油・お味噌を製造しています
-

新湊名産 中六醤油セット
[富山県射水市]
寄付金額 14,000円
港町で創業以来、地元の味として親しまれる甘口醤油です。 伝統の技が醸し出すこだわりの味を是非ご賞味下さい。
-

七福醸造の有機白だし・有機白しょうゆ 4本セット ヴ...
[愛知県碧南市]
寄付金額 14,000円
有機JAS認定工場で製造された、有機白だしと有機白しょうゆのセット(有機JAS認定証取得日/平成18年11月6日)
-

七福醸造の有機白しょうゆ2本セット ヴィーガン 認証...
[愛知県碧南市]
寄付金額 7,000円
有機JASの小麦、大豆を主原料に製造した安心安全の有機白しょうゆです。 一般的な醤油に比べて素材本来の色や、風味を生かす...
愛知県は、「溜醤油」と「白醤油」の主な産地で、全く正反対の溜醤油と白醤油が同じ県で造られ使われている珍しいケースです。愛知県には、地元の名産品である魚醤(ぎょしょう)「しこの露」があります。魚醤は、魚介類を原料にした液体状の調味料で、「しこの露」は地元でとれた新鮮なカタクチイワシから造られており、大豆は使用していません。
山梨県では、少し甘めの卵かけご飯専用醤油「たまごかけご飯のためのお醤油」と放牧卵のセットが用意されています。
静岡県のお礼品として、再仕込醤油の「甘露しょうゆ」や、濃口醤油の「富士泉」「本丸亭」、かつおだし風味の「伊豆醤油」などがそろっています。
長野県には、杉樽を使った本醸造醤油やスプレー式の卓上醤油、地元の果物の汁をブレンドした「伊那谷柚子醤油」や「伊那谷りんご醤油」があります。
富山県では、地元で愛されている甘口醤油や、京風料理やうどんのつけつゆに使える淡口(うすくち)醤油もあります。
近畿地方
-

江戸時代から続く小原久吉商店の湯浅醤油 老舗の味900...
[和歌山県湯浅町]
寄付金額 16,000円
創業約170年以上。醤油発祥の地(紀州湯浅)で守り続ける伝統の味!風味とコクが特徴の再仕込醤油3本セットです。
-

国産有機醤油詰め合わせ327
[兵庫県多可町]
寄付金額 15,000円
多可の地で創業130有余年の蔵元が提供する国産有機醤油の特別セットをお届けします。
-

江戸時代から続く小原久吉商店の湯浅醤油・うすくちしょう...
[和歌山県湯浅町]
寄付金額 16,000円
人気No.1製品味くらべセット 湯浅醤油、たまりしょうゆ、うすくちしょうゆの詰め合わせ4本セット。
-

江戸時代から続く小原久吉商店の湯浅醤油1本&たまりしょ...
[和歌山県湯浅町]
寄付金額 8,000円
老舗のおすすめ味くらべセット湯浅醤油(深みのある旨み)・たまりしょうゆ(濃厚なコクとまろやかな甘み)
-

丸中醤油 蔵の恵 丸中醸造醤油720ml×2本
[滋賀県愛荘町]
寄付金額 15,000円
江戸寛政より二百余年 古来伝統の味・丸中醤油です。
-

国産有機醤油(こい口3本)詰め合わせ 734
[兵庫県多可町]
寄付金額 20,000円
創業130有余年。多可の地で醤油と味噌を造り続けている蔵元で造られた、こだわりの伝統の味をどうぞ。
-

国産有機醤油と有機純米酢詰め合わせ328
[兵庫県多可町]
寄付金額 15,000円
多可の地で創業130有余年の蔵元が提供する国産有機醤油の特別セット。国産有機純米酢とごいっしょに。
-

世界に認められた安全性!国産有機醤油 694
[兵庫県多可町]
寄付金額 7,000円
創業130有余年。多可の地で醤油と味噌を造り続けている蔵元のこだわり伝統の味をどうぞ。
近畿地方では淡口醤油が良く使われる傾向があり、大手メーカーだけでなく各地に多くの蔵元があります。
兵庫県の醤油の蔵元では、創業130年余りの蔵元が造る「国産有機醤油」や「黒大豆醤油」「かけ醤油」「お料理用うす口」、杉桶で長期熟成させた「天然醸造 まる大豆醤油」、北播磨独自の濃口醤油・淡口醤油など、非常に多くの種類の醤油が生産されています。
三重県には、「鈴鹿黒ぼく土」という鈴鹿山麓にある肥沃な土壌で栽培し、糖度40度でマイルドなにおいのにんにくがあります。その「鈴鹿黒ぼくにんにく」を地元の味噌蔵から出たたまり醤油に約1カ月漬け込んだ醤油は、卵かけご飯から肉料理まで万能に使えます。
和歌山県の湯浅町は、日本での醤油発祥の地と言われており、最高レベルの醤油を求めて現在も醤油造りが行われています。お礼品として、湯浅町の「湯浅醤油」を用意しています。創業以来170年以上も続く伝統の濃口醤油や再仕込醤油が味わえます。
中国地方
-

やすもと醤油 くんせい調味料3本セット
[島根県松江市]
寄付金額 8,000円
自宅でキャンプの気分!本格くんせい調味料詰め合わせです。
-

しいたけ醤油奥大山 360ml 1本 調味料 だし醤油...
[鳥取県江府町]
寄付金額 3,000円
道の駅駅長イチ押しの調味料
-

かき醤油・白だしかき醤油詰め合わせ A-13a
[岡山県笠岡市]
寄付金額 13,500円
モンドセレクション10年連続、最高金賞受賞
-

【E】300ml五穀調味シリーズ
[岡山県岡山市]
寄付金額 14,000円
【人気の調味シリーズ】手頃な300mlサイズ!冷蔵庫にちょこんとかわいく収まるサイズです
-

【大江ノ郷自然牧場】八頭のまごころセット
[鳥取県八頭町]
寄付金額 14,000円
豊かな自然の中、自家配合飼料で育てた平飼い鶏の新鮮卵と、卵かけご飯専用醤油です。卵のコクが口いっぱいに広がる、濃厚卵かけご...
-

【合成保存料不使用】230年間、味を守り続ける醤油屋・...
[島根県津和野町]
寄付金額 9,000円
230年の間、伝統の味を守り続ける醤油屋「大仲屋本店」の合成保存料不使用濃口醤油1L×3本セット
-

アサヒワシのあまくちしょうゆと調味料詰め合わせ
[山口県周南市]
寄付金額 19,000円
明治30年から120年超続いている地元で有名なしょうゆの詰め合わせセットです。
-

宮島かきのしょうゆ・広島県産生しょうゆセット
[広島県廿日市市]
寄付金額 14,000円
宮島周辺海域の牡蠣を使用した出汁感ある宮島かきのしょうゆ、広島産大豆・小麦使用の生しょうゆの詰合せ。
中国地方は、全国的にみて、塩辛い醤油から甘い醤油に移行していく中間の地域です。
甘い醤油は、甘口醤油に慣れている人なら刺身やお寿司、冷奴などへのかけ醤油として使うのがおすすめですが、甘口に慣れていない地域の人は、蒲焼のタレやステーキ、卵かけご飯にかけるのが馴染みやすくておすすめです。
山口県は再仕込醤油発祥の地と言われており、柳井市名産の「甘露醤油」が有名です。名前に「甘露」とつきますが、再仕込醤油の一種で、非常に濃厚な、とろりとした甘い醤油です。
岡山県には、もろみをそのまま搾った「生揚げ醤油」に「もろみ醤油」、素材の味を引き立たせる「杉桶仕込醤油」、濃口醤油と溜醤油を合わせて鰹節と昆布でだしをとった「さしみ醤油」などがそろっています。
島根県では、舞茸の風味が豊かな「舞茸だし醤油」や、国産大豆を使い手間暇かけた「さしみしょうゆ」、さらに再仕込醤油の「生揚げ醤油」「食べる醤油」などさまざまな醤油が用意されています。
四国地方
-

醤の郷 小豆島 丸大豆生しょうゆセット
[香川県小豆島町]
寄付金額 15,000円
マルキン醤油 国産の「丸大豆」と「小麦」、「塩」を使用した、原料と製法にこだわったお醤油です。
-

鎌田醤油 だし醤油500ml【8本入】
[香川県坂出市]
寄付金額 17,000円
鎌田醤油一番の人気商品「だし醤油」です。
-
![【ゆず詰め合わせセット】少しこだわりセット4[595] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/181/018100003/1469741_00_1701648192.jpg)
【ゆず詰め合わせセット】少しこだわりセット4[595]
[高知県馬路村]
寄付金額 10,000円
馬路村のゆず商品の人気詰め合わせセットです!
-

鎌田「老舗醤油メーカーのだし醤油」(200ml×10本)
[香川県]
寄付金額 10,000円
創業230年余の香川県の老舗醤油メーカー「鎌田醤油」がつくる様々な料理を引き立てるだし醤油です。
-
![【ゆず詰め合わせセット】少しこだわりセット1[507] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/181/018100003/1469712_00_1701648191.jpg)
【ゆず詰め合わせセット】少しこだわりセット1[507]
[高知県馬路村]
寄付金額 6,000円
馬路村のゆず商品の人気詰め合わせセットです!
-

小豆島特選丸大豆醤油 1L×5本
[香川県土庄町]
寄付金額 13,000円
厳選された丸大豆、丸小麦を主原料に、今も昔ながらの製法で、じっくり醗酵・熟成させたこいくち醤油です。
-
![【ごっくん馬路村・ゆずの村ぽん酢】大満足セット[535] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/181/018100003/1469762_00_1701648193.jpg)
【ごっくん馬路村・ゆずの村ぽん酢】大満足セット[535]
[高知県馬路村]
寄付金額 26,000円
【ごっくん馬路村・ゆずの村ぽん酢】
-
 冷蔵
冷蔵純生!これぞ真髄!本場さぬきうどんめん一の打ちたてうど...
[香川県多度津町]
寄付金額 7,000円
釜入れ直前の新鮮な純生うどんをそのままお届けします!
四国地方は濃口醤油が主流ですが、甘口と辛口の割合は半々から甘口がやや優勢です。
香川県の小豆島は「醤(ひしお)の郷」とも呼ばれ、醤油蔵が密集している地域です。お礼品として、烏骨鶏(うこっけい)を煮込んで作った「烏骨鶏だし醤油」が用意されています。
高知県からのお礼品としては、甘口の「濃口醤油」や「さしみ醤油」があります。地下60メートルから汲み上げた清流四万十川の伏流水を仕込水に使っているため雑味や余分なにおいがなく、素材の味が引き立つ逸品となっています。天然醸造醤油「本かつおだし醤油」や「焼きあゆだし醤油」、宗田鰹節が入った「龍馬のだし醤油」濃口・淡口などがあります。他にも、濃口醤油や淡口醤油、さしみ醤油など幅広くそろえています。
愛媛県では「卵かけ醤油」や「うに醤油」、天然醸造の「淡口醤油」「濃口醤油」「だし醤油」などがあります。
九州地方
-
 冷蔵
冷蔵【宮崎県 都城市】「きみ恋卵」「よかもよか卵」たまごか...
[宮崎県都城市]
寄付金額 10,000円
2種類の卵でTKG食べくらべ
-

サクラカネヨ 薩摩醤油 6本セット (1L×6本)
[鹿児島県いちき串木野市]
寄付金額 11,000円
料理の味を調えやすい九州産の甘い醤油をご家庭で! 料理の味を整える、甘く、濃い醤油「薩摩醤油」 サッカリン不使用
-

カトレア醤油1L3本セット
[大分県別府市]
寄付金額 11,000円
かつお・しいたけ・昆布の旨みをブレンドした、上品でまろやかな甘さが特長の 手造り出汁醤油です。
-

こいくち 甘露醤油(1.8L×6本)セットB! 常温で...
[鹿児島県いちき串木野市]
寄付金額 14,000円
吉村醸造の代表的なこいくち醤油です。焼魚やお刺身、冷奴のかけ用として、また煮魚や焼き鳥など料理用としてお使いいただけます。
-

あまくちヤマニ醤油詰合せ YS01-S11
[福岡県北九州市]
寄付金額 13,000円
一度使ったら手放せない爽やかな甘さの醤油です。
-

料理好きの人にピッタリ♪バラエティ豊かな調味料セット「...
[大分県臼杵市]
寄付金額 12,000円
1861年創業以来、味ひとすじ・純正をモットーとした醸造の老舗、フンドーキンがお届けする、醤油・味噌・ドレッシング・ポン酢...
-

蔵元直送 いつでも新鮮で、おいしさ長持ち!母ゆずり濃口...
[鹿児島県鹿児島市]
寄付金額 4,000円
いつでも新鮮で、おいしさ長持ち! 母ゆずり濃口 新鮮ボトル3本セット
-

【5営業日以内に発送】「かねよ みそ しょうゆ」南国か...
[鹿児島県鹿児島市]
寄付金額 12,000円
伝統技法を受け継ぎ作られた「母ゆずり濃口・淡口醤油」セットをご用意しました!
九州地方では甘口の醤油が広く使われています。甘口醤油の多くは甘味料で甘みがつけられており、一般的に、九州では南に行くほど甘さが増していきます。焼きおにぎりや卵かけご飯、また肉料理などと相性の良い醤油です。
福岡県では、「うまくち醤油」や、煮物用の醤油などが用意されています。「うまくち醤油」は濃厚な甘みが特徴で、万能に使えますが、特に煮物や卵かけご飯によく合います。マルサン醤油の「本造り~こだわりの醤油~」や、「にんにく醤油」「かぼす醤油」「梅醤油」など地域の素材を生かした醤油もあります。
佐賀県には、甘口醤油で仕込んだ「うに醤油」や「燻製醤油」があります。「うに醤油」は卵焼きやかまぼこ、燻製醤油は魚や肉、チーズなどによく合います。
宮崎県や鹿児島県は、九州の中でもトップレベルの甘い醤油の地域です。宮崎県では港町の青島で造られた「蔵出し地醤油(刺身)」と「蔵出し地醤油(極)」が用意されています。どちらも甘口醤油で、さしみ醤油はほどよい甘さ、極は旨みと甘みを凝縮させたより甘い醤油です。
味見してみたい醤油や、ふるさとで使い慣れていた醤油、いくつかの地域の醤油を味比べするなど、ふるさと独自の風土と歴史を持つ、地元で長く愛用されてきた醤油をぜひ味わってみてください。