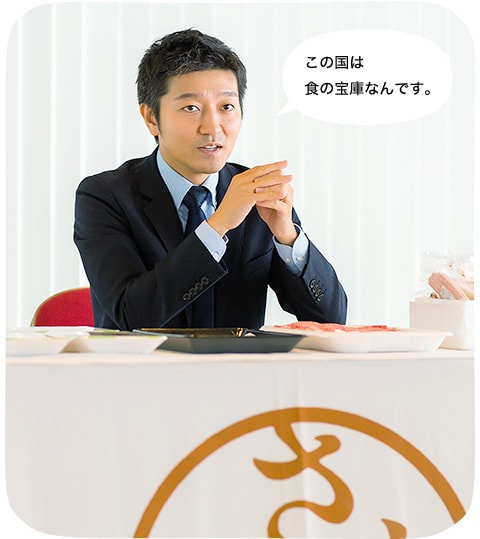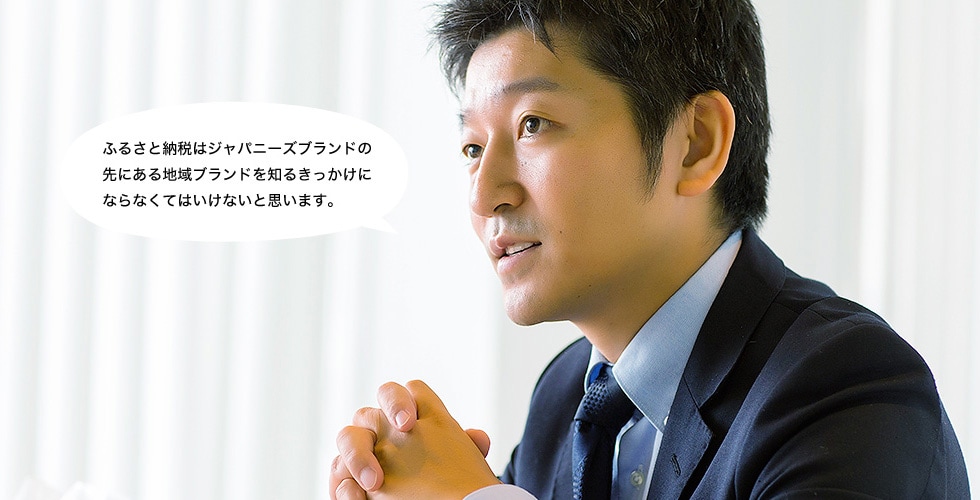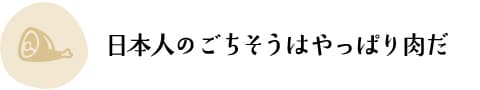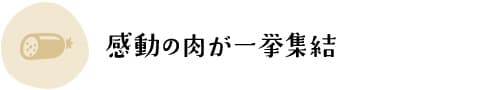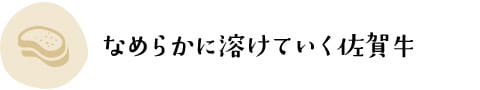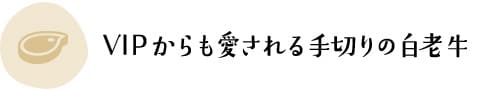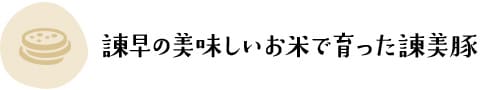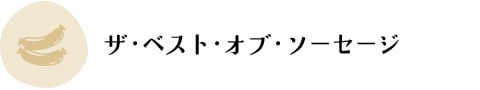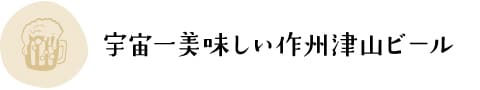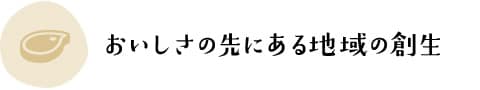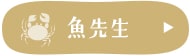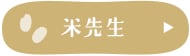※2020年2月時点
基本的に毎日が肉の日。こんにちは、さとふる編集部のYです。さとふるお礼品ランキングで常に上位を占めているのが肉。やっぱり贅沢といえば肉という考え方は、日本人の根底に根強くあるのでしょうか。どれも美味しそうですが、見ただけではなかなか違いもわからず、食べたことのないものを食べたいけれど、どれを選んだらいいかわからないという方も多いことでしょう。魚の先生としても登場した地域協働事業推進部 部長の幸田が、お肉の魅力も紹介したいということで再び登場。今日は一体どんな肉が登場するのでしょうか?

おはようございます!
いやあ、こないだ魚について話していたら肉のオススメも色々と浮かんできちゃいまして。やっぱり魚を食べたら、肉も食べてほしいと思うわけですよ。今まで各地で出会った泣くほど美味しい肉を今日は持ってきたので、ぜひみなさんにもお伝えしたいんです。これは一番人気の佐賀牛です。これは北海道の白老牛。こっちは長崎の諫美豚で、これは群馬の手作りハムセット。まあ、とにかくひとつずつご紹介しましょう。


この霜降り、ほんとフォトジェニックですよね。すき焼きに限らず佐賀牛はさとふるのお礼品の中で不動の人気を誇っています。佐賀牛という名前は聞いたことある人も多いと思いますけど、佐賀のこのエリアは米どころで、良質な稲わらを飼料として使用しているため、牛へのストレスが少なく、肉質は素晴らしいの一言。ストレスがあると、霜降りの脂のサシがうまく入っていかないんですよね。人間もそうですけど心身ともに健康なのが一番なんです。食用牛は24~48ヶ月の肥育期間で500~600kgに育てて出荷するのが一般的なんですが、佐賀牛はその中でも比較的期間を長くとって丁寧に育てています。
配合飼料の違いの他に、気温とか飼育の環境、愛情のかけ方、世話の細やかさなどは全部味に関わっています。たとえば放牧主体で育てると牛は動きまわって、しなやかな赤みが付き、ストレスもたまらないけれど、その分管理が大変。そして、当然それだけコストもかかってしまう。さらに、運動させすぎると痩せてきてしまい脂が乗らない。そのように、牛たちの調子を見ながら絶妙なさじ加減で肥育して美味しい肉をつくるには、最終的には育て方の技術が必要不可欠なんです。
そうですね。ただランクの話をすると、ABCというのは1頭の牛から取れる肉の量の格付けです。だから、味に関して言えば関係ないですね。佐賀牛というのは、JAグループ佐賀管内で育てられている黒毛和牛のうち、日本食肉格付協会による肉質の格付けが5段階評価で5等級と4等級、霜降りの度合いを示す脂肪交雑(BMS)を12段階評価で7段階以上をクリアしたものだけに与えられる称号です。なので、佐賀牛という名前が付いている時点で、味の保証はされていることになります。それだけのものだから気安く買える値段ではないし、こういったふるさと納税の機会にぜひ食べてみてほしいですね。今日はすき焼き用を持ってきてるからちょっと焼いてみます。
ちょっと大きいけど、贅沢にそのままいただきます。うん、なんてやさしい味なんだ!舌に触れたその瞬間に、もう普段食べている肉との違いが決定的にわかります。表面も中もとてもなめらかで、ザラッとした感じがまったくない。冷凍保存できるけど、水分量が抜けていってしまうので、やっぱり届いたらなるべく早く食べるのがおすすめです。保存方法は冷凍で、解凍は冷蔵庫でやるのが鉄則ですね。ああ、お米を炊いておけばよかった・・・(笑)。


こっちは北海道の白老牛です。ご存じですか?
北海道を代表するブランド牛なんですが、年間1200頭と生産頭数が少なく全国的に流通はしていなくて希少価値が高いですね。「北海道洞爺湖サミット」では、日米首脳晩餐会や総理大臣夫人主催昼食会のメニューに使用されて、世界のVIPからも絶賛された一品です。地元の方でも特別なときに食べる肉として認知されていて、滅多なことがないと食べられないみたいです。肉の値段はブランドと希少価値と生産コストで概ね決まってくるけど、白老牛は比較的高価な分類に入ると思います。これは黒毛和牛なんだけど、育てるのが大変なんです。そして飼育過程だけではなく、肉の捌き方にもこだわりがあります。ここの白老牛はナイフで捌いているんですけど、それはまさに職人技。ナイフでの手切りはおいしく切れて無駄が出ない反面、コストがかさんでしまいます。一方でチェーンソーなどの機械で切ると時間とコストを短縮できる分、厚みを緻密にコントロールできなかったり、無駄な部位が出てしまったりします。メリット・デメリットがあるんです。今日はサーロインステーキを用意したから、塩コショウで焼いてみましょう。
うん、ほんとうにとろけますね。口の中でもたつく感じがまったく無くて、もう噛まなくてもするすると飲み込んでしまえそうです。かといって、油っぽくて重いわけでもなくて、寒い地方で育っただけに、美味しさの中に締まりがあって、引き締まった憎らしいほどの肉らしさがあります。


続いては諫美豚(かんびとん)。これも知らないですよね?
たしかに国内ではまだまだ豚のブランド化は牛に比べて進んでいなくて、諫美豚のような美味しい肉をもっと広めていく必要があります。これは長崎県諫早市で育てられている豚なんですけど、とにかく餌と水の質がものすごく高いんです。全国食味ランキングで5年連続特Aを獲得した「にこまる」と、名水百選にも選ばれる多良岳水系の地下水を肥育に使用していて、ストレスはもうほとんど無い天国のような環境で育っています。お米を食べることで、豚肉がより美味しくなると注目されているオイレン酸の割合が高くなり、通常の豚肉より脂肪に甘みがあって臭みも少なく、冷めても脂肪が固まりにくい柔らかくジューシーな味わいが楽しめるお肉になっています。諫美豚を育てている土井農園では、お米を収穫した後の藁や籾殻などを家畜の餌や敷き藁として使い、減反部分で飼料用のお米をつくり、資源を無駄にしない循環型農業を実現しています。人にも地域にも地球にもやさしい素晴らしい方法なんです。
そうですね。諫美豚はしゃぶしゃぶでいただきましょうかね。見て下さい、このきれいなピンク色。新鮮さが伝わってきますね。うん、うまい!豚特有の臭みがまったくなく、ものすごくジューシー。最後にふわっと甘みがやってきます。しゃぶしゃぶの肉ぐらいの厚さでも、噛むたびに肉汁が出てきます。このセットは2.7kgも入ってるので、家族でも大満足。冬に鍋を囲むのも最高ですね。こちらの諫美豚は他のふるさと納税サービスでは取り扱っていないので、食べられるのはさとふるだけです!


きました!ここのソーセージはすごいですよ!
これは群馬県榛東村にある岸ファームという40年以上続く豚農家さんがつくっているもので、どうやって豚を食べたら美味しいか、肉の扱い方を知り尽くしていますね。有志で集まった近所のお母さんたちが、すべて手作りで作っています。わたしも何回か訪れたことがあるんですけど、このエリアは豚農家も多く、ハム作り体験のイベントなんかもやっていてとてもいい場所です。どうしても後継者がいなくて徐々に生産者が減ってしまっているので、こういった商品開発やイベントを通して、若い人たちにももっと目を向けてもらおうといろいろな努力がされています。商品開発から製造まで、これ全部やっているんだから驚きですよね。
ここは10畳程度の作業場の中で、肉を揉んで、カットして、ミンチにして、腸に詰めてというすべての工程を手作業でやっています。相当大変ですよ。ソーセージやハムは形を整えるために卵白や強力粉、片栗粉などをつなぎとして入れるんですけど、ここは非常に少ないつなぎで作っているようで、その分肉の味が強くて満足感がものすごい。大量に作って保存して卸すという規模だと、どうしても添加物をたくさん入れなければいけないんですけど、こちらでは生産量をあまり増やさず、気を配れる範囲の中できちんと保存環境を整えて生産しているので、保存料・着色料が使われていないんです。わたしも現地で何度も食べさせていただいだけれど、他のソーセージとは全く違います。特にこのボロニアソーセージがわたしの大好物。ちなみに、ソーセージとウインナーの違いって知ってますか?
(笑)ウインナー、フランクフルト、ボロニアソーセージの総称をソーセージって言います。そして、ウインナーとフランクフルトとボロニアソーセージの違いは太さと使用する腸の違い。羊の腸を使った物、もしくは直径20mm未満のものがウインナー・ソーセージ。豚の腸を使った物、もしくは直径20mm~36mm未満のものがフランクフルト・ソーセージ。牛の腸を使った物、もしくは直径36mm以上のものがボロニア・ソーセージ。ということ。まあ地域によっていろいろなソーセージの形が生まれたということになりますね。
ここの商品はさまざまなバリエーションがあって面白いんです。お母さんたちが自ら商品開発を、日々実験しながら行っているんです。このニラ入りってやつも美味しくって。餃子みたいな風味かな。変わったところだとトマトウインナーというのもあったり、時期やお母さんのインスピレーションによってセットの内容は変わることもありますね。じゃあ焼いちゃいますよ。これは本当にうまいんですよ。
これほんと最高なんです!フライパンで焼くけど、油いらないんです。調味料もいらないですね。ほんとにものすごくうまい、これは教えたくないぐらいほんとにうまいんです。わたしのベストソーセージです。見てください横の断面。うわあ・・・(泣)
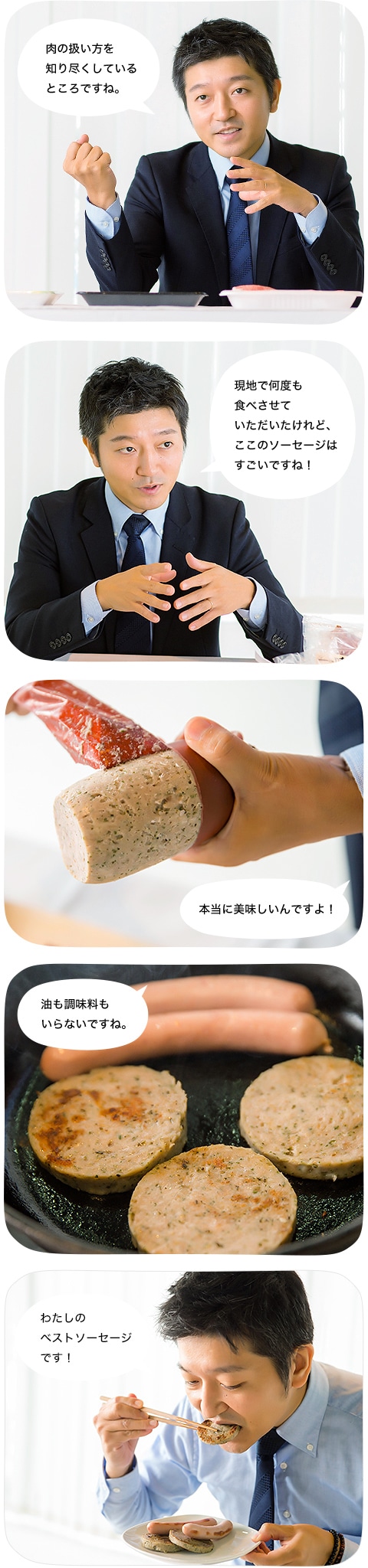

やっぱりお肉といえばビールですよね。これはさとふるお礼品でも大人気の岡山県の作州津山ビール 宇宙ラベルシリーズです!乾杯!ゴクッゴクッゴクッゴクッゴクッ、ゴクッゴクッ、ゴクッゴクッ。
ぷわぁ、うまい!このビールは国際ビール品評会「ワールド・ビア・チャンピオンシップ」で最高評価の金メダルを受賞したもので、とても飲みやすい口当たり。これはスタウトだけど、さっぱりしていてソーセージにもよく合いますね。イラストレーター西口司郎さんによって、ラベルに惑星が描かれていて、見て楽しい、飲んで美味しいビールですね。贈答用にもとても重宝されていますよ。欧米のあらゆるブルワリーを訪ね歩いて研究を重ね、岡山の清流三十七にも選ばれる加茂川の名水を使用してつくっているビールは日本人好みの味に仕上がっていますよ。

わたしも日本全国の自治体を訪れ、生産者の方と話し合いを重ねていますけれど、本当にどなたも真摯に努力をされていて、この国は食の宝庫なんです。一つの国の中にいくつもの表情をみせる食材がたくさん眠っています。ふるさと納税は自治体単位で寄付先とお礼品を選ぶ仕組みなので、ジャパニーズブランドの先にある地域ブランドを知るきっかけになれれば、というかならなくてはいけないですね。今、大きな指針として地域創生が掲げられていますけれど、一人ひとりが地域に興味を持って、その土地のものを食べたり、そこを訪れたりすることの集積でしか、地域の活性はありえないんじゃないかと思っています。