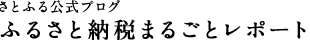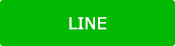源泉対象は何? 源泉徴収の基礎をレクチャー!
 源泉徴収は、前もって税金を引かれたうえで給与等を受け取ることになるので、天引きという表現もされます。確定申告による納税と源泉徴収による納税があるのはなぜなのでしょうか。この記事では、源泉徴収の仕組みやルールについて解説します。
源泉徴収は、前もって税金を引かれたうえで給与等を受け取ることになるので、天引きという表現もされます。確定申告による納税と源泉徴収による納税があるのはなぜなのでしょうか。この記事では、源泉徴収の仕組みやルールについて解説します。
そもそも源泉徴収とは?
源泉徴収は、給与や報酬などを支払う勤務先などが、それらを支払う際に税金を差し引き、まとめて国などへ納付する制度です。税額の計算は、所定の方法に基づき勤務先など給与や報酬を支払う者が行います。
源泉徴収される税金は所得税と復興特別所得税(2037年12月31日までの間に生ずる所得について併せて徴収)です。源泉徴収は、源泉徴収の対象になる所得が支払われるたびに行われます。所得が支払われた月の翌月10日が納付期限です。ただし、給与等を支払う相手が常に10人未満の源泉徴収義務者に対しては、特例として年2回にまとめての納付が認められます。その場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要です。
何が源泉対象になるの?
源泉徴収の対象になるものとして広く知られているのは、サラリーマンなどが勤務先から受け取る給与所得です。給与所得とは、給料や賃金のほか、歳費や賞与なども含みます。手当も基本的に給与所得です。
残業手当や休日手当だけでなく、扶養手当や住宅手当なども給与所得として源泉徴収の対象になります。ただし、一定金額以下の通勤手当や一定金額以下の宿直手当、転勤や出張のための旅費などは非課税です。給与所得以外にも源泉徴収される報酬はいろいろあります。弁護士や税理士のような特定の資格を持つ個人に対する報酬なども源泉徴収の対象です。
給与等の支払者が個人で、その個人が事業を行っている場合は、源泉徴収をする必要があります。
源泉徴収された後はどうなる?
給与所得の場合、その年の中途で控除対象扶養親族の数に異動があること等の理由により、給与を支払う都度源泉徴収をした税額の合計額とその年中の給与の支給総額に対して計算した納付すべき税額との間にずれが生じます。
そこで、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させるために行う処理が年末調整です。
所得税の計算の際には、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除などさまざまな所得控除が適用されます。住宅ローンを組んで住宅を取得したときに受けられる住宅借入金等特別控除も年末調整で処理を行う控除のひとつです。ただし、初年度だけは確定申告をして控除を受ける必要があります。なお、年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人だけが対象です。年末調整を行った後に扶養家族の増減があった場合には、異動の申告書を提出し、再度年末調整をし直します。2,000万円を超える給与収入がある人は、サラリーマンであっても年末調整の対象にはなりません。個人で確定申告を行う必要があります。
※この記事の内容についての詳細は、税理士等へご相談ください。
>>確定申告のやり方についてはこちらを確認<<