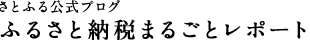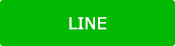年末調整済みだけど確定申告が必要!申告方法を紹介

会社勤めの人であれば自分で確定申告をしなくても年末調整として会社がそうした手続きを代行してくれます。そのため、確定申告をしたことがないという人がいるかもしれません。
しかし、年末調整を受けていても状況によっては別途確定申告が必要になる場合があります。そこで、具体的な確定申告の方法について紹介していきます。
年末調整済みか確認する方法
自分が年末調整済みかどうかを確認するには、年末に会社から支給される源泉徴収票を見ましょう。源泉徴収票にはさまざまな項目があり、数字の記載も多いためどこを見たらよいのかわからないかもしれません。
確認すべき項目は所得控除の額の合計欄です。年末調整がされている場合、その欄には合計値が記入されています。一方、年末調整がされていない場合には、その欄が空欄又は0円になっています。その場合は、確定申告が必要だということです。
ただし、年末調整を受けていても確定申告が必要になる場合があります。
まず、副業等何らかのかたちで年間20万円超の所得がある場合、確定申告が必要になります。
ただし、株式の配当益や株式の譲渡所得のうち、確定申告をしないことを選択したものについては20万円の所得の計算には含まれません。
給与所得しかないという場合でも、年末調整後に婚姻などで家族が増えた場合には確定申告が必要な場合があります。なぜなら、家族が増えると扶養控除などの控除が適用されるためです。そして、給与の年間収入金額が2000万円を超える人の場合、そもそも年末調整の対象外になります。そのため、会社から受け取る源泉徴収票をもとに確定申告をしなければなりません。
年末調整の対象とならないものは何?
年末調整の対象とならないため自分で確定申告をしなければならない所得控除等はいくつかあります。
まず、医療費控除です。年間の医療費実質負担額が10万円を超える場合、超えた部分の金額が所得控除等されます。なお、年収が200万円未満の人の場合は所得金額の5%を超えた場合に所得控除等の適用が受けられます。
次に、住宅ローン控除です。住宅ローンなどの年末残高の合計金額をもとに計算された金額が、翌年以降の所得税から控除されるのが住宅ローン控除です。住宅ローン控除に関して、2年目以降は年末調整によって特別控除の適用を受けることができます。しかし、初年度の控除については年末調整の対象とならないため、確定申告が必要になります。
また、ふるさと納税も年末調整の対象外です。ふるさと納税による控除は寄付金控除と呼ばれます。地域に寄付した金額が所得控除等の対象となります。なお、寄付金控除はふるさと納税だけではなく、学校や公益社団法人などの公的事業を行う法人または団体、政治団体などへの一定の寄付も対象です。
他には、雑損控除も年末調整されません。雑損控除とは災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合に一定金額まで所得控除が受けられる制度です。
最後に、特定支出控除も年末調整の対象外です。特定支出とは、通勤費や転居費、研修費といった項目のうち、給与支払者が証明した支出を指します。他にも単身赴任している社員が帰省するときの費用なども特定支出控除の対象です。こういった支出がその年の給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超えた金額が所得控除の対象となります。
年末調整済みの確定申告の手順は?
年末調整が終わった後に確定申告をするには、どういった手順を踏めばいいのでしょうか。まず、確定申告に必要な書類を準備しましょう。確定申告書はもちろんですが、所得控除等を受けるために必要な書類もきちんと整える必要があります。
たとえば、医療費控除を受けるためには医療費控除の明細が必要です。なお、平成29年分の確定申告から領収証は提出不要となりました。しかし、提出不要であっても5年間の保管義務はあるため、きちんと領収証は現物を確認して保管するようにしましょう。他にも所得控除等を受けるためにはさまざまな書類が求められるため、どういった書類が必要かを確認しておき、きちんと準備します。
そして、必要書類一式を用意したら必要事項を記入します。その際、控除の申請欄にもきちんと必要事項を記入しましょう。記入が終わったら、最寄りの税務署へ確定申告期限内に書類を提出して完了です。
>>確定申告について詳しくチェックするならこちら<<
所得控除等を受けたいのなら確定申告を忘れずに!
会社勤めの人であれば、会社に求められる書類を提出することで税務処理が完了するため、確定申告をわざわざ行うことはあまりないかもしれません。しかし、医療費控除やふるさと納税による寄付金控除のような所得控除等や還付を受ける場合は、きちんと確定申告をする必要があります。
また、ふるさと納税を行う場合は、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告が不要になります。ワンストップ特例制度は寄付先が5団体までなどの所定の条件を満たすことで利用可能な制度です。
>>ワンストップ特例制度とは?詳しい解説はこちら<<
この場合、所得税の所得控除はされませんが、住民税についてはその所得控除相当額を含め、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に減額という形で控除されます。