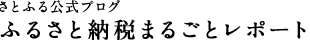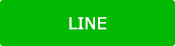個人年金保険は控除対象?計算方法まとめ

個人年金保険に加入しているという人は多いのではないでしょうか。
個人年金保険に加入していると、生命保険料控除の一種である個人年金保険料控除というものが適用されるため、所得控除が受けられるというメリットがあります。これは、自分で将来に向けた準備をしているということで国が税金の優遇をしてくれるためです。ここでは、個人年金保険料控除の計算方法について詳しく解説していきます。
個人年金保険料控除とは
個人年金保険料控除とは、生命保険料控除の一種で1年間の個人年金保険の保険料支払額に応じて所得税や住民税が控除される制度です。生命保険料控除は3つの種類に分けられています。
1つ目は、終身保険や収入保障保険といった死亡保険が控除対象になる一般の生命保険料です。2つ目は、医療保険やがん保険などが対象になる介護医療保険。3つ目は個人年金保険が対象となる個人年金保険料控除になります。
なお、個人年金保険料控除は個人年金保険料税制適格特約が付加されている契約以外は控除制度が利用できません。
個人年金保険料控除の所得税の計算方法
個人年金保険料控除の所得税の計算方法は、2012年1月1日以降の保険契約に適用される新制度と2011年12月31日までの契約に適用される旧制度の2種類で分けられます。新制度の所得控除額は次のように計算されます。年間の保険料支払額が2万円以下の場合、控除金額は支払保険料の全額です。
年間の保険料支払額が2万~4万円以下になると、控除金額は支払保険料×2分の1+1万円となります。もし、年間の保険料が3万円だったときは、2万5000円が控除されるという計算です。
年間の保険料支払額が4万~8万円以下のときは控除金額は支払保険料×4分の1+2万円です。年間保険料が6万円であれば、控除額は3万5000円になります。年間の保険料支払額が8万円以上になると、控除金額は一律で4万円です。次に、旧制度の所得税額の計算方法です。年間の保険料支払額が2万5000以下の場合、保険料の全額が控除対象になります。
年間の保険料支払額が2万5,000~5万円以下になると、支払保険料×2分の1+1万2,500円です。年間の保険料が3万円であれば、控除額は2万7,500円です。年間の保険料支払額が5万~10万円以下のときは、支払保険料×4分の1+2万5,000円になります。年間の保険料が6万円になると、控除額は4万円です。年間の保険料支払額が10万円を超えると、一律5万円の控除となります。
個人年金保険料控除の住民税の計算の仕方は?
住民税の所得控除も同様に新制度と旧制度の2つに分けて計算されます。新制度の計算方法は次の通りです。年間の保険料支払額が1万2,000円以下の場合、支払保険料の全額が控除されます。年間の保険料支払額が1万2,000~3万2,000円以下になると、控除金額は支払保険料×2分の1+6000円です。年間の保険料が2万円であれば、1万6,000円が控除額となります。
年間の保険料が3万2,000~5万6,000円以下のときは、控除金額は支払保険料×4分の1+1万4,000円です。年間の保険料が4万円になると、控除額は2万4,000円です。年間の保険料が5万6,000円以上になると、控除金額は一律で2万8,000円控除されます。
次に、旧制度の計算方法です。年間の保険料支払額が1万5,000円以下の場合、支払保険料全額が控除されます。年間の保険料支払額が1万5,000~4万円以下になると、控除金額は支払保険料×2分の1+7,500円です。年間の保険料が2万円のときは、控除額が1万7,500円となります。
年間の保険料が4万~7万円以下であれば、控除金額は(支払保険料×4分の1)+1万4,000円です。年間の保険料が5万円になると、控除額は2万6,500円です。年間の保険料が7万円以上になると、控除金額は一律で3万5,000円控除されます。
↓↓シミュレーションで詳細な控除上限額を確認する↓↓