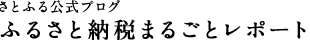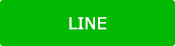源泉控除対象配偶者とは?

源泉控除対象配偶者は、平成29年度の税法改正の際に新設されました。
この記事では、税法改正で配偶者に対する控除がどう変わったのかを解説します。
配偶者控除と配偶者特別控除の改正とは?
平成29年度の税法改正では、個人所得課税についても改正が行われました。
配偶者控除と配偶者特別控除の改正において変わった点は大きく分けて二点あります。
ひとつは、納税者本人の所得金額による配偶者控除の制限です。
改正前は、配偶者自身が無収入もしくは年間所得が38万円以下(収入ベースなら103万円以下)の場合には、納税者の所得にかかわらず、38万円(老人配偶者控除は48万円)の控除を受けられました。
改正の結果大きく変わったのは、納税者本人の所得が900万円を超えたところから、段階的に控除金額が逓減(ていげん)されるという点です。納税者の合計所得が900万円から950万円までの場合は配偶者控除26万円(老人配偶者控除32万円)、950万円を超えると13万円と16万円まで逓減(ていげん)されます。そして、合計所得が1,000万円を超えると、配偶者控除の適用外となる点が最大のポイントです。
ただし、所得基準の900万円と1,000万円なので、給与収入ベースにすると1,120万円と1,120万円に当たります。もうひとつの改正点は、配偶者特別控除の枠が拡大された点です。改正前は、配偶者特別控除も納税者本人の所得による差はなく、配偶者本人の所得によって受けられる控除の金額が逓減(ていげん)されていました。しかし、改正後は、配偶者特別控除を受けられる配偶者の上限所得が123万円(給与収入ベースで201万円)まで拡大されています。ただし、大幅に変更されたのが、配偶者本人の所得が同じでも、納税者の所得により3段階で逓減される点です。
納税者の所得が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除に関しても受けられません。
>>シミュレーションや早見表で手っ取り早く控除上限額を確認<<
ふるさと納税の控除上限額(限度額)がわかるシミュレーション&早見表
源泉控除対象配偶者とは一体?
配偶者控除対象配偶者に当たるかどうかは、給与所得者本人の合計所得金額と配偶者の年間所得によって決まります。給与所得者本人の条件は合計所得金額が900万円以下であることです。
これは給与年収に換算すると1120万円以下に当たります。なおかつ、生計を一にしている配偶者の合計所得が85万円以下であることが条件です。これは給与収入ベースに換算すると150万円以下になります。配偶者特別控除の満額38万円を受け取れる枠は、配偶者本人の収入を基準にすると広がりました。しかし、納税者本人の所得を基準にした場合、配偶者が無収入であっても、源泉控除対象配偶者から外れることになります。
源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者の違い
平成29年の税法改正では、源泉控除対象配偶者という名称以外に、同一生計配偶者という名称も登場します。どちらも配偶者と付いていますが、異なるものを指す言葉です。源泉控除対象配偶者の方は、配偶者控除か配偶者特別控除によって38万円の控除を満額受けられる配偶者ということができます。それに対して、同一生計配偶者とは、納税者本人の所得に関係なく生計を一にしている配偶者の年間所得が38万円以下の場合です。平成29年の税法改正以前の控除対象配偶者がちょうど当てはまります。改正後の控除対象配偶者は、同一生計配偶者のうち、納税者本人の所得が900万円以下の場合に限られるため、必ずしも一致するわけではありません。