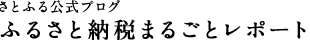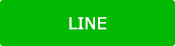聖徳太子が腰掛け、安堵した石がある町/奈良県安堵町【ふるさと納税・自治体事典】

「安堵町(あんどちょう)」には、聖徳太子が飛鳥に出勤するために使った「太子道」という道があり、道沿いには太子ゆかりのエピソードがたくさん残っているそうです。「飽波(あくなみ)神社」にある「腰掛石」もそのひとつ。ここではそんな安堵町をご紹介します。
安堵町の概要
安堵町は、奈良盆地の北西部に位置し、町内にはかつて聖徳太子が斑鳩宮と飛鳥を行き来したとされる古道「太子道(たいしみち)」が通っており、今もその名残を残しています。
また、町の南に大和川、西に富雄川(とみおがわ)、中央に岡崎川が流れ、難波の津と飛鳥を結ぶ水運の要衝として、豊かな歴史・文化が古より集積している町です。
近代陶芸の巨匠で、人間国宝の第1号である富本憲吉(とみもとけんきち)をはじめ、「晩翠堂(ばんすいどう)」という塾を開いて多くの人材を輩出した今村文吾、奈良県再設置の立役者である今村勤三、大阪大学第5代総長で、BCG接種を確立し、予防医学の基盤を打ちたてた今村荒男(いまむらあらお)など、多くの偉人を輩出しています。
安堵町は、面積も奈良県で2番目に小さく、人口も多くありませんが、住民一人ひとりが輝き、まちづくりの主役となり、「小さくてもキラリ光る交流のまち あんど」をテーマとして掲げ、生涯にわたって自己実現を図っていけるまちを目指しています。
●人口:7470人(2018年8月1日現在)
●市の花:テイカカズラ、ナデシコ
●市の木:モチノキ
さとふるから申込めるお礼品はコレ!:安堵町の名産品・特産品
◆富本憲吉「四弁花」模様オリジナル風呂敷「色絵赤更紗模様飾皿」模様&「色絵四弁花更紗模様六角飾筥」模様
安堵町は、日本近代陶芸の巨匠と呼ばれ、1955年に重要無形文化財保持者(人間国宝)となった富本憲吉(とみもとけんきち/1886年~1963年)の「ふるさと」です。
このお礼品は、そんな富本の「四弁花」模様オリジナル風呂敷2枚組。
繊細で美しく気品あふれる色絵磁器の数々で、独自の清純な世界をつくりあげてきた彼の足跡は「陶芸のさと 安堵」として後世に受け継がれています。この風呂敷は、富本憲吉の代表的な四弁花模様の作品を用いて製作しました。
※四弁花模様は、富本の生家(奈良県:安堵町)に自生していた「テイカカズラ」をモチーフにしています。
■生産者の声
安堵町出身で近代陶芸の巨匠、1955年に人間国宝に認定され、1961年に文化勲章を受章された富本憲吉先生が、本来五弁花である町の花「テイカカズラ」を四弁花に抽象図案化した模様の風呂敷です。
お礼品の詳細はこちらをクリック!
富本憲吉「四弁花」模様オリジナル風呂敷「色絵赤更紗模様飾皿」模様&「色絵四弁花更紗模様六角飾筥」模様
◆うぶすなの郷 TOMIMOTO ペアランチ券
2012年5月、富本憲吉の自宅跡であった「富本憲吉記念館」が惜しまれながら閉館。その後、2017年1月に体験型宿泊施設「うぶすなの郷 TOMIMOTO」として生まれ変わりました。
このお礼品は、その「うぶすなの郷 TOMIMOTO」で自然の恵みを味わうペアランチ券となります。
近郊で獲れた奈良県産の新鮮な野菜をふんだんに使用した、身体にやさしい松花堂です。
見た目も鮮やかで料理長のこだわりが詰まった料理をぜひご賞味ください。
ソフトドリンク付です(お1人様1ドリンク)。
■生産者の声
大和の歴史と人間国宝・富本憲吉を感じる宿。
地元の食材をたっぷり使ったレストラン。
新しい息吹を生み出す陶芸工房&ギャラリー...
安堵や斑鳩の歴史や文化を楽しみながら、緑豊かな空間で自分と向き合う。
そんなぜいたくな時を過ごしていただけます。
■提供サービス内容/提供地
・うぶすなの季節の松花堂ランチ2名様
・ワンドリンク(アルコール類除く) 2名様分
・お食事会場『五風十雨(ごふうじゅうう)』
〔サービス提供地:うぶすなの郷 TOMIMOTO/奈良県生駒郡安堵町〕
お礼品の詳細はこちらをクリック!
◆うぶすなの郷 TOMIMOTO ペア宿泊券
こちらも、「うぶすなの郷 TOMIMOTO」からのお礼品。
近代陶芸の巨匠にして人間国宝である富本憲吉の生家はリノベーションしてホテル&レストランとなりましたが、そちらですごすことができる「ペア宿泊券」となります。
客室は文化、歴史、そして豊かな自然にあふれる空間で、1日2組限定のゆったりとした時間を過ごしていただけます。
客室は、富本が過ごした部屋「日新」と2階建ての大きな蔵を改築した「竹林月夜」の2つのタイプから選べます。
夕食は、本格和食の会席料理。たくさん食べた次の日は、体にやさしい出来立ての朝ごはんが用意されます♪ 1泊2食付(夕食・朝食)。
■提供サービス内容/提供地
・ご宿泊 2名様(「日新」、もしくは「竹林月夜」)
・うぶすなの季節の会席ディナー 2名様
・うぶすなのご朝食 2名様
〔サービス提供地:うぶすなの郷 TOMIMOTO/奈良県生駒郡安堵町〕
お礼品の詳細はこちらをクリック!
◆お座りサンタと鹿セット
手作りのサンタと安堵のい草で作成した鹿のセット。「工房ばごい」で人気のお座りサンタです。
どんなところにでもちょこんと座ります(落下防止接着剤付)。
それに加えて、安堵町の特産でもあるい草を使用し、つくり上げた鹿を2体セットにしました。
手作りなので1つひとつ表情が違うのが魅力!
すっきりとしたシンプルなデザインかつ木彫りなので、どんなシーンにでも自然に溶け込みます。
■内容
・イソベサンタ お座りポーズ(高さ:約30cm)
・安堵のい草で作成した鹿 2体
お礼品の詳細はこちらをクリック!
安堵町の特産品
◆灯芯
安堵町の特産品のひとつに「灯芯」があります。今では聞きなれない言葉になってしまいましたが、かつて使われていた照明具、「行燈(あんどん)」には欠かせないものでした。
「行燈」は、時代劇などで室内に置いてある照明具としてよく登場するため、ご覧になったことがあるでしょう。行燈の中の灯明皿(とうみょうざら)に油を入れ、そこに挿したヒモの先に火を灯しますが、そのヒモが「灯芯」で、和ロウソクの芯にも使われています。
この「灯芯」の原料となっているのは、畳の材料として知られているい草です。灯芯用には少し太い品種が使われるそうです。
秋に植えて刈り取りは5月~6月。そのい草を梅雨の晴れ間に干して乾燥させます。束ねた草の上部を縛って三角錐の形にしたものを立てていきます。
田んぼに三角錐のい草が並ぶ様は安堵町の風物詩ともなっていましたが、1960年代にはすでに行燈の時代は終わっており、最後の商業栽培は1968年だったそうです。
安堵町の一大産業だった「灯芯づくり」。い草をうまくひいて表皮を取り除き、灯芯を取り出す技術は「灯芯ひき」と言い、昔は子どもたちも自然とその技術を覚えていたそうです。
今ではできる人が少なくなってしまいましたが、町でもこの「灯芯ひき」の技術(町指定の「無形民俗文化財」にもなっています)を引き継いでいく努力をしています。
たとえば1996年には、灯芯ひき技術を後世へ継承していくことを目的に、「灯芯保存会」を発足させました。
保存会では、定期的に「安堵町歴史民俗資料館」で練習会を行い、スキルの向上に努めています。また、この技術を多くの人に知ってもらうべく、奈良県立美術館などで体験会や実演会を実施する他、若い人も積極的に勧誘しているとのこと。
さらに、自分たちの手で、灯芯の原料であるい草の栽培も行っています。
今もお寺の年中行事などで灯す灯明に灯芯は欠かせません。実際、東大寺や元興寺(がんごうじ)、春日大社、法隆寺などの行事に、安堵町の灯芯が奉納されました。
たとえば、東大寺では二月堂の修二会(しゅにえ)に、元興寺では地蔵盆の明かりとして使われています。
◎灯芯保存会
町の特産である「灯芯」そして、それをつくるための「灯芯ひき」という伝統的な技術を後世へ伝承し、さらなる普及を目指すことを目的に活動するボランティア団体で、1996年に有志で結成されました。
メンバーは当初、20名程度でしたが、現在では約40名が在籍しています。
活動内容は、前述のようにい草の育成、体験普及活動の指導協力ですが、灯芯やい草にちなんだグッズの企画立案や製作販売なども活発に行っています。
また、こうしたグッズの収益金の一部は善意銀行などへ寄付しているそうです。
安堵町の観光資源
◆安堵町歴史民俗資料館
「安堵町歴史民俗資料館」は、奈良県再設置運動に尽力した運動家、今村勤三の邸宅跡を活用した展示施設。
今村氏より町への家屋・資料提供を機に展示施設として改修し、さまざまな角度から安堵町の昔の姿や伝統を今に伝えるべく1993年に開館しました。
敷地面積は1581平方メートル。表門・同茶室(1847年造)・主屋・蔵・庭園からなっています。
常設展示として今村氏に関する資料や、町の伝統産業である「灯芯ひき」に関する民俗資料を展示している他、江戸時代から伝わる古文書や人々が使用した民具の展示、さらにテーマと期間を決めて特別展示も行っています。
また、安堵町に古来より伝わる伝統を引き継ぐため、年間を通してさまざまな体験会(灯芯ひき、わらぞうりづくり、い草栽培、田植えから収穫・調整まで行う古代米栽培など)を開催しています。
◆聖徳太子の腰掛石
聖徳太子が牛頭天王を祀る祠を建てたのが始まりとされる「飽波(あくなみ)神社」。
聖徳太子が公務に通われた斑鳩宮(いかるがのみや)と飛鳥宮をつなぐ太子道沿いにあり、その境内には聖徳太子が腰を掛けたという伝承のある、通称「腰掛石」があります。
ここに腰かけて愛馬・黒駒とともに休憩をとり、「ホッと安堵された」と言い伝えられます。
◆あんど芋煮会
安堵の秋の収穫祭といえば「あんど芋煮会」です。
地産の里芋、ニンジン、ゴボウなどの野菜や奈良県のブランド牛である大和牛をふんだんに使用した「あんど芋煮鍋」は毎年大好評! 1杯200円で販売されますが、あっという間に700杯以上が売り切れてしまうそうです。
また、この「あんど芋煮鍋」は、「奈良大立山まつり」の中で開催される「あったかもんグランプリ」の第1回で「審査員奨励賞」を受賞、第3回では「優秀賞」を受賞するなど、すでに高評価を獲得済み。大鍋で一気につくる芋煮汁の味わいは格別です♪
会場の安堵中央公園にはお土産店も並び、安堵町産の野菜も販売されます。同時に「あんど芋煮会PRステージ」や物産展などで大変盛り上がります。
あとがき
保存会や町の人たちの努力によって、この地に生き続ける「灯芯」と「灯芯ひき」の技術。この「灯芯」が使われているものといえば「行燈(あんどん)」ですが、その間接照明のようなやさしい灯りや、インテリアとして部屋の中で映えるその芸術的なデザインを見たことはありますか? ぜひ安堵町で体感してみてください。
※2018年8月28日時点の情報のため、お礼品の受付停止や寄付金額が変更されていることがありますが、ご了承ください。
※参考・参照元
・安堵町公式 ホームページ(http://www.town.ando.nara.jp/)
・『第三版都道府県別 日本の地理データマップ』小峰書店