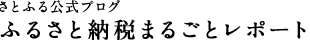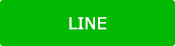医療費控除を受けたい!年間10万以下でも受けられるもの?

所得税などの負担を減らす制度の1つに医療費控除があります。医療費控除の適用を受けることを検討している人のなかには、支出した医療費の金額が少ないため控除条件を満たさないのではないかと不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
医療費控除を賢く活用するためには、制度の概要や控除条件などについて理解しておくことが大切です。そこで、医療費控除制度の基礎知識とふるさと納税との併用に関する注意点についてお伝えします。
年間10万円以上にならないと医療費控除は受けられない?
医療費控除とは、所得税や住民税の税額計算における所得控除の1つです。給与所得などの所得から医療費控除額を差し引くことによって課税対象となる所得金額を減らし、税負担を軽減できるメリットがあります。
医療費控除の適用を受けるためには適用条件を満たすことが必要です。医療費控除は、医療費の自己負担額として支出した金額が一定金額を超えなければならないという限度額が設定されています。その限度額については10万円という数字が有名で、10万円を超えなければ医療費控除は使えないと認識している人が多いといわれています。
しかし、実際には支出額が10万円以下でも適用を受けられるケースがあります。税法上、支出金額の下限は、10万円、もしくは総所得金額等の5%のうちいずれか低い金額とされ、その金額を超えた分が医療費控除の対象となることが正式に定められています。総所得金額等とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
年間医療費が10万円以下でも控除を受けられるケース
医療費控除の適用を受けるためには、金額が一定の金額を超えることが必要です。そのため、適用を検討する場合は、まず年間の医療費支出額を把握することになります。
支出額が計算できたら、税法が定める金額を超えているかチェックします。適用条件として定められている金額は10万円、もしくは総所得金額等の5%。仮に総所得金額等が200万円未満であれば、5%を掛けた金額は10万円未満となります。その場合は、医療費支出額が10万円未満であったとしても医療費控除の適用を受けることが可能です。
たとえば、総所得が300万円だった場合、5%を掛けると15万円となりますが、10万円のほうが低い金額ですので、10万円を超える支出が医療費控除の対象額となります。
実際にいくらなら医療費控除を受けられる?
総所得が200万円未満の場合、具体的にいくらの金額が医療費控除対象額になるのかイメージがわかないという人もいるでしょう。そこで、4つのケースについて具体的に医療費控除額を計算してみます。
1つ目のケースは、総所得金額等が199万円の場合です。200万円未満ですので、総所得金額等に5%を掛けて限度額を求めることになります。199万円の5%は9万9500円です。この金額を超える医療費支出が医療費控除額となります。2つ目は、総所得金額等が150万円の場合です。同様に計算すると、限度額は7万5000円となります。3つ目のケースは総所得が100万円だった場合です。この場合は、5万円が限度額となります。さらに4つ目は総所得が85万円の場合で、5%を掛けると4万2500円です。このケースでは、医療費支出が5万円だったとしても7500円の医療費控除が受けられます。これらの計算例を見れば、10万円未満の支出でも医療費控除の適用を受けられることが実感できるでしょう。
総所得200万円以上の場合にできる対策
医療費支出が10万円に満たない場合でも、総所得金額等を200万円未満に抑えることができれば、医療費控除の適用を受けられる可能性があります。ただし、総所得金額等が200万円を超えていても、10万円未満の医療費支出について適用を受けられる可能性があります。
自らの総所得金額等が200万円を超えていたとしても、一定の条件を満たす共働きの配偶者など自分以外の家族の総所得金額等が200万円未満であれば、その家族が医療費控除の適用を受けることが可能です。
注意点は、医療費支出を誰が行ったことにするかです。医療費控除は、自分もしくは一定の家族について医療費を支出した人が適用を受けられる制度です。支出の対象は、自分以外の家族の分でも問題ありません。たとえば、夫の総所得金額等が200万円を超え、妻の総所得金額等が200万円未満の場合、夫婦の医療費を妻の名義で支払うことによって、支出額が10万円未満でも医療費控除の適用を受けられる可能性があります。所得が少ない人が医療費を支出することがポイントです。
医療費控除を申請する方法は?
医療費控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。自営業者の場合は、基本的には確定申告を行うことになります。しかし、会社員の場合、会社が税額計算を行ってくれる年末調整では医療費控除の対応をしてもらえません。そのため、会社員であっても医療費控除の適用を受ける場合は確定申告が必要です。
確定申告においてやるべきことは主に4つあります。1つ目は、医療費の明細書と確定申告書の用意です。2つ目は、医療費の領収書を整理することです。枚数が多い場合は、日付や病院名、支出額などの一覧表を作るとよいでしょう。3つ目は、確定申告書への記入です。医療費控除の内訳などを記載する欄がありますので、整理した情報を確認しながら記載します。4つ目は、確定申告書の第一表の所得控除欄にある医療費控除欄に控除金額を記入することです。限度額を超える金額を記載します。すべての記載が終了したら、税務署に確定申告書を提出します。申告書は持参するだけでなく郵送でも提出可能です。
ふるさと納税と医療費控除を併用するときの注意点
ふるさと納税を利用しようと考えている場合は、医療費控除との併用ができるのか、ふるさと納税によって所得控除等できる金額や医療費控除額に影響があるのかなどについて心配だというケースもあるでしょう。
まず、ふるさと納税と医療費控除の併用ですが、問題なく併用可能です。ただし、医療費控除の適用を受けることによって、ふるさと納税制度を利用することで所得控除等できる金額に影響がありますので注意しましょう。
>>ふるさと納税の控除限度額をこちらでしっかりチェック<<
ふるさと納税の控除上限額(限度額)がわかるシミュレーション&早見表
医療費控除の適用を受けることによって、課税対象となる所得金額を減らすことができます。その結果、負担する税額は減少します。一方、ふるさと納税による税負担の軽減効果は、税額があれば控除するというものです。そのため、医療費控除を受けることによって課税所得が減少すると、所得控除等の対象額が減る可能性があります。税額がゼロになると所得控除等はできません。また、ふるさと納税で得られる所得控除等可能額よりも税額が少なければ、発生している税額までしか所得控除等を受けられなくなります。