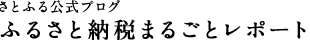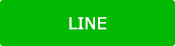元々は"強飯(こわめし)"と言った「おこわ」【ふるさと納税お礼品事典:おこわ】

(※2019年1月24日更新)
もち米を蒸した料理のことを「おこわ」と言い、五目おこわやきのこおこわ、山菜おこわ、鰻おこわなど、さまざまなバリエーションがあります。また、お祝いごとなどで食べる「赤飯」も、実は「おこわ」の一種。ここでは、そんな「おこわ」のお礼品を3品、ピックアップしました。
島根県雲南市 笹巻きおこわ はしま10個セット(うなぎ5個+しまね和牛肉5個)
雲南市(うんなんし)は、島根県の東部に位置する人口およそ4万人のまちです。2004年(平成16年)に6つのまち(大東町・加茂町・木次町・三刀屋町・吉田村・掛合町)がひとつになって誕生しました。
「雲南」という名前は、旧出雲国の南に位置することに由来し、古くからこの地方の呼び名として親しまれてきたことから名づけられました。
日本の25年先の高齢化社会をいく雲南市。今、雲南市ではさまざまな地域課題に対し、前向きにチャレンジする人が生まれ、少しずつ成果を生み出しています。
雲南市は、子ども×若者×大人による3つのチャレンジを連鎖させ、10年後も20年後も市民みんなで支え合い、いきいきと暮らせる魅力あるまちづくりに挑戦しています。
このお礼品は、おいしい雲南市産のもち米を自家製のだしで炊き込み、うなぎ、しまね和牛肉をそれぞれ熊笹の葉に包んだ手作りのおにぎりです。
島根の豊かな自然が育んだ味と香りを、ぜひお楽しみください。
■お礼品情報
●内容:
・うなぎ 5個
・しまね和牛肉 5個
●賞味期限:各90日
●配送:クール便(冷凍)
●寄付金額:1万円
お礼品の詳細はこちらをクリック!
笹巻きおこわ はしま10個セット(うなぎ5個+しまね和牛肉5個)
新潟県弥彦村 お饅頭6種類と笹おこわ6種類の詰合せ
新潟県中央部の日本海側に位置する弥彦村(やひこむら)は、霊峰弥彦山とその麓に鎮まる越後一の宮「彌彦神社」の門前町・北国街道の宿場町として栄えてきた地域です。
神社のご祭神、天香山命(あめのかごやまのみこと)が越後の民にさまざまな産業の基礎を授けたと伝えられていることから、越後文化発祥の地と言われています。
こうした独自の歴史・文化に加え、四季折々の美しい自然や、「弥彦 湯神社温泉」「やひこ桜井郷温泉」といった湯量豊富な2つの温泉など観光資源に恵まれ、新潟県内屈指の観光地となっています。
このお礼品は、提供事業者「三笠屋製菓」自慢の6種類の笹おこわとお饅頭のセット。
◎笹おこわ(6種類)
新潟県産の餅米を、昔ながらの製法で蒸し上げた五目おこわ・山菜おこわ・醤油おこわや、しょうゆラーメンのスープで味を整え、うずらのたまご・焼豚・メンマ・なるとをトッピングしたラーメン風おこわなど6種類を県内産の笹で包み、冷凍おこわに仕上げました。
◎饅頭(6種類)
昔ながらの製法で、一つひとつ手づくりしています。饅頭の生地や餡子が違うので、バリエーション豊富です。
■お礼品情報
●内容:
・笹おこわ(しょうゆラーメン風/鮭わかめ/五目/山菜/醤油/梅ちりめん)
全6種類×各1個
・味噌饅頭×2個
・しそ饅頭×2個
・田舎饅頭×2個
・玉子饅頭×2個
・うぐいす饅頭×2個
・温泉饅頭×5個
●賞味期限:冷凍3ヵ月
●配送:クール便(冷凍)
●寄付金額:1万1千円
お礼品の詳細はこちらをクリック!
お饅頭6種類と笹おこわ6種類の詰合せ
三重県鈴鹿市 海の幸 魚長「穴子おこわ」
鈴鹿市(すずかし)は、日本のほぼ中央、三重県の北中部に位置し、山や海などの豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、四季の変化に富み、歴史と文化が育まれた町です。
また、自動車レースの「F1日本グランプリ」や夏の風物詩でもある「鈴鹿8時間耐久レース」が鈴鹿サーキットで毎年開催され、国際色豊かなモータースポーツの聖地として、その名は国内外に広く知られています。
このお礼品は、独自の製法によるタレをからめたおこわに、香ばしく焼いた蒲焼の穴子をのせた「穴子おこわ」。
真空、冷凍状態でお届けしますので、そのままご家庭の冷蔵庫で保存し、解凍して召し上がれます。
すぐにお茶漬けにもできるよう、お吸い物、山椒、わさび、特製タレをつけました。
■お礼品情報
●内容:
・穴子おこわ(60g×10個)
・お吸い物×3、わさび×3、山椒×2、特製タレ×1
●賞味期限:180日
●配送:クール便(冷凍)
●寄付金額:2万円
お礼品の詳細はこちらをクリック!
海の幸 魚長「穴子おこわ」
「おこわ」の由来は?
もち米を蒸した日本の伝統料理の総称が「おこわ」です。
昔はもち米が高価だったことから、主にお祝いなど特別な日に食べられるものであり、「強飯(こわめし)」と呼ばれていました。「強(こわ)い」は、「堅い」の意味です。
この「強飯」を表す女房詞(にょうぼうことば/※)が「御強(おこわ)」であり、これが「おこわ」という名前の由来でもあります。
また、なぜ「おこわ」が「強(こわ)い=堅い」かと言うと、江戸時代にご飯を"炊く"習慣が生まれる前は、主に主食のご飯はお粥にして食していたそうです。
つまり、ふだん食している"柔らかいお粥"に対して、この"この特別なごちそう"が堅かったことから、「おこわ(御強)」になったということです。
※女房詞(にょうぼうことば)とは?
昔、宮中に仕える女官が使っていた隠語的な言葉。単語の頭に「お」を付けるのも、女房詞の表現のひとつ。
あとがき
「赤飯」は、もち米に小豆などを混ぜて蒸したもので「おこわ」の一種ですが、通常「おこわ」とだけ言ったときには、この「赤飯」を指すことがあります。
またちなみに、「おせきはん」という言い方も女房詞とのことです。
今回紹介した3品を、ぜひふるさと納税をするときの参考にしてください。
※2018年4月25日時点の情報です。
※ご紹介しているお礼品が在庫切れの場合でも、「入荷案内メール」へのご登録で(要「さとふる」会員登録)、入荷時にメールにてお知らせいたします。