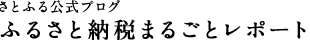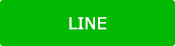納付の意味とは? 税金で考えなければならないことを紹介

この記事では、納付という言葉の意味と納付の方法、さらに納付と深い関わりがある税金について解説します。
納付とは
納付という言葉は、一般的には金銭や品物を納めることをいいます。ただし、相手は国、都道府県、市区町村などの行政機関で、納めるものは主に税金です。義務として金品を支払うケースで使われます。
納付する税金の種類って?
納付する税金には多くの種類があります。納付の対象になる税金の主なものには、申告所得税、消費税、法人税、相続税、贈与税、住民税などがあります。
申告所得税とは、所得税と源泉所得税とに区分していうときの呼び方です。申告所得税は、確定申告で1年間の所得に一定の税率を掛けて税額を算出して納付します。消費税は、消費という行為に対してかかる間接税です。消費税を負担するのは物を買ったりサービスを利用したりする消費者ですが、生産や販売、流通を行う企業や店舗が納付します。法人税は、課税対象の法人が納付する税金です。相続税は相続が発生した際に、相続や遺贈によって取得した財産の価額に応じて課税されます。贈与税は、個人から財産を無償で譲り受けたときに課税される税金です。住民税は、都道府県民税と市町村民税の総称で、地方自治体が行政サービスを行うための資金を確保するために徴収する税金です。
納付する前の段階の控除とは?
申告所得税を納付する際には、確定申告で正確な所得を計算し、それに基づいた税額を算出することが必要です。確定申告で所得税の控除を受ける場合は、それぞれ必要な事項を申告書に記載し、必要書類を添付した上で申告します。
給与所得者等で確定申告が不要となる要件を満たしている方については、給与から直接所得税等を源泉徴収され、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了します。この場合、年末調整時の際に必要な書類を勤務先へ提出します。
ただし、所得税の控除には年末調整で受けられるものと、確定申告が必要なものがあります。寄付金控除や医療費控除、住宅ローン控除を初めて受ける場合等は年末調整で控除を受けることはできません。
年末調整で受けられる控除は、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除などです。なお、配偶者の所得が38万円を超える場合には配偶者控除の対象となりませんが、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でかつ配偶者の所得が38万円超123万円以下の場合、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
控除を受けたうえで納付をしよう
税金の納付は国民の義務です。納付期限内に納めないと、延滞税や加算税などの対象になるので注意してください。
※2018年12月5日時点の情報です。
※この記事の内容についての詳細は、税理士等へご相談ください。