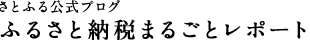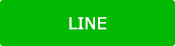源泉所得税って何?年末調整の仕組みを徹底解説!

サラリーマンは年末になると、年末調整で還付金が返還されることがあります。しかし、年末調整について名前は知っていても、還付が発生する仕組みについてよく知っているという方は少ないのではないでしょうか。年末調整によって還付されているお金は本来、毎月の給与からたくさん引きすぎた部分が返ってきているだけです。
また、年末調整を行った結果、1年分の所得税額が毎月の源泉徴収額の合計より多い場合には不足額を徴収されます。そこで、この記事では年末調整の仕組みや源泉徴収について説明していきます。
年末調整の仕組みとは?
年末調整とは、簡単にいうと「会社が毎月計算して納付してくれている源泉所得税を、年末に1年分を再計算して正しいものに修正する」手続きです。
1月から11月までの給与については支払額に応じた源泉所得税等を給与から天引きしておき、1年の最後の月である12月にまとめて、控除額の異動や変更がないかを確認するようにしました。つまり、従業員の1年間における控除額の変更がないかどうかを確かめる作業が年末調整です。
確認した結果、還付や追徴課税が発生することがあります。また、年末調整によって、正しい所得税額が納付されたことになりますので、一定の要件を満たす場合、サラリーマンは確定申告を行う必要がありません。
源泉所得税とは?
毎月の給与から差し引かれる所得税のことを源泉所得税と呼びます。源泉所得税は、概算で徴収されている所得税なのです。源泉所得税は、基本的には毎月の給与収入やボーナスを加味した金額で計算されています。また、源泉徴収で計算されている金額には、社会保険料控除や扶養親族の有無などは含まれていますが、生命保険料控除などの支出は含まれていないのです。
その結果、1年間に家族の異動や保険料の変更がない場合は、年末調整において給与所得から生命保険料控除などを引き算する再計算が行われるため、還付されるケースが多いのです。一方で、源泉所得税を徴収していても追徴課税となるケースもあります。たとえば、年の途中で急な昇格や、過去になかったような残業時間の急増などが発生した場合です。つまり、年末調整で再計算が行われる生命保険料控除などよりも給与収入の増加が上回ってしまうと、毎月源泉徴収されている所得税では足りなくなるというわけです。
年末調整の対象になるのは?
会社は従業員を雇って給料を支払う以上、企業の規模にかかわらず、基本的にはすべての人を対象にして年末調整を行わなければいけないと決まっています。また、対象となる人の役職や立場も関係ありません。給料を支払っている人が正社員だろうと、パートやアルバイトであろうと同様に年末調整を行う義務があります。
ただし、年末調整を行わなくても良いと認められているケースもいくつかあるのです。年末調整を行わなくても良いのは、「サラリーマンであっても確定申告を行わなければいけない人」や「比較的短期間しか働かなかった人」などが該当します。
サラリーマンであっても確定申告が必要なケースとしては、「1年間の給与収入が2000万円以上ある人」です。また、「2カ所以上から給与収入を得ていて、従たる会社からの給与が20万円を超えている場合」は従たる会社では年末調整を行ってくれないため、確定申告が必要となります。比較的短期間しか働かなかった人に該当するのは「1年の途中で退職して再就職しなかった場合」や「2カ月以上連続して雇用がない(日雇いなど)場合」です。
また、特別な事情があった場合にも年末調整が免除されるケースがあります。それは災害の被害を受けた場合に災害減免法が適用されて、その年の給与に対する所得税の徴収について猶予や還付を受けている場合です。
年末調整で出た過不足金はどうなる?
年末調整を行うとほとんどの場合で過不足金が発生し、還付あるいは追徴課税が起こります。年末調整という名のとおり、ほとんどの企業では事務上の手続きの問題から12月の給与の段階で、還付や追徴課税分の金額を給与から差し引きます。
しかし、従業員を多く抱えている企業にとって、年末調整の事務量は非常に膨大です。また、1年間の所得を計算する都合上、12月に入ってから年末調整の再計算をしなければいけないため、時間的な制約も事務員のプレッシャーとなり、ときにはミスも起こってしまいます。さらに、年末調整を行ったあとに、急な結婚が決まって扶養親族の数が変更する可能性もあるでしょう。
間違った所得税を納付されると税務署側も困りますので、会社が提出する年末調整の書類の期限は翌年の1月31日までとなっています。実際に従業員への還付または追徴課税をする時期は、翌年の2月まで認められています。
年末調整の対象外の人は確定申告が必要
年末調整を行うことによって、会社が従業員の代わりに所得税を申告しています。つまり、年末調整の対象外となる人は確定申告を自らが行わなければいけません。確定申告を行うポイントはいくつかあり、まず忘れてはいけないのは「基礎控除」や「配偶者控除」「生命保険料控除」などの基本的な控除です。
基礎控除については、納税者本人に対して無条件で認められますが、配偶者控除については年間で一定以上の収入を得ていると認められないため注意しましょう(本人の合計所得金額にも上限があります)。
また、生命保険料控除や地震保険料控除については、支払っている保険料全額が認められるわけではありません。支払っている金額のうち一定額が認められます。
正確な所得税の金額がわかるのは年末調整後!
年末調整を行うことによって、源泉徴収を計算しているよりも控除額が多ければ還付されますし、反対に給与収入が著しく増大している場合には、追加徴収される可能性もあります。一年の途中で大きな昇給があった人などは、年末に追加徴収される可能性もあります。