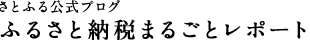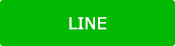年間の所得税はいくら? 税率や計算方法を紹介

年間の所得税がどのように計算されているのかを知っていますか。
この記事では年間の所得税の基本的な仕組みと具体的な税率や計算方法を交えて説明していきます。
年収と所得税の関係とは?
働き方や収入を得る方法は人それぞれであるものの、毎年1月1日から12月31日までの間に所得が生じた場合は、所得税を納付する義務があります。所得税の計算方法は、総合課税制度と分離課税制度がありますが、ここでは、総合課税制度の対象となる所得に限定し計算方法を紹介します。総合課税制度とは、年間の所得金額を合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、その残額である課税所得金額に税率を乗じて所得税を計算する方法です。
総合課税制度において適用される税制は、「超過累進税率」であるため、課税所得金額に応じて所得税率が定められており、課税所得が増えれば、税率もあがるという仕組みになっています。
年間の所得税の基本的な計算方法
所得税法では、所得を10種類に区分しており、所得税の計算方法は、所得の区分によって異なります。
勤務先から受ける給与、賞与などは「給与所得」、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等を個人で営んでいることから生じる所得は「事業所得」、住宅や土地などの貸しつけにより生ずる所得は「不動産所得」、5年を超えて所有している山林を伐採して譲渡し生じた所得や立木のままで譲渡し生じた所得は「山林所得」、公社債や預貯金の利子などは「利子所得」、株式の配当などから得られる所得は「配当所得」、また、退職により勤務先から受ける退職手当や退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得は「退職所得」、クイズの賞金や満期保険金などは「一時所得」に区分されます。
さらに、家庭用のたな卸資産以外の資産、生活用動産以外の資産を売却したときに生ずる所得は「譲渡所得」上記いずれにも、分類できないものは「雑所得」に区分されます。
年収は収入した金額をいい、所得は収入からその収入に係る原価、必要経費ならびに税法で定められた一定の金額を差し引いた後の金額をいいます。
給与所得者の例であれば、給与所得の計算方法は
「年収-給与所得控除=給与所得」
となります。
給与所得控除には収入金額に応じて計算されるものと、実際に支出し、雇用者から承認を受けた額を元に計算される特定給与所得控除の2つからなります。
上記の10種類の所得の種類に応じた計算方法により計算したそれぞれの所得金額を合計したものを総所得金額といいます。所得税とはこの総所得金額から「所得控除」を差し引いた残額である課税所得金額に税率を乗じて計算します。
所得控除とは、医療費控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除・寄附金控除等があります。
所得税の税率
総合課税制度の対象となる所得の所得税の計算に使われる税率は、課税所得の金額に応じて、5%から45%の7段階に区分されています。
具体的な計算方法は、「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
平成25年(2013年)1月1日から2037年12月31日までの所得に関しては、通常の所得税に加えて「復興特別所得税」が課せられます。復興特別所得税とは、平成23年(2011年)に発生した東日本大震災に関する復興事業を行うための財源として徴収されるものであり、所得税を納める義務がある人のすべてが対象となる点を押さえておいてください。税額としては、所得税額の2.1%相当になるものと定められています。たとえば、所得税率が20%の区分に入る人の場合、復興特別所得税を加えた後の税率は「20%×102.1%=20.42%」となるのです。
源泉徴収制度と確定申告
所得税は、所得者自身が、上記に方法に従ってその年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。源泉徴収制度は、給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、2その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。
納税者の事務を軽減するため、給与所得にかかる源泉所得税については、雇用者が年末調整を行った所得税額をもって、納税者個人の納税義務は充足されますので、年末調整を受けた給与所得者は確定申告義務対象外となっています。
しかし、年末調整を受けなかった給与所得者や、給与所得以外の収入が一定額以上ある者、年末調整の計算に含まれていない所得控除の適用を受けたいとする者は、確定申告をする必要があります。
所得控除等を受けるためには、それぞれの控除の種類によって必要となる書類が異なります。寄付金や保険料などの領収書は、確定申告をするときに必要になるので、大切に保管しておくことを心がけてください。