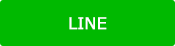2023/06/30
豊富な特産品を活かし地域事業の底上げとさらなる地域活性化へ
佐賀県佐賀市 1,400品目以上のお礼品を自身の目で確かめた自治体職員の取り組み
九州の北西部に位置し、北部には温泉やダム湖、南部には有明海の豊穣な干潟など豊かな自然を有し、多くの特産品にも恵まれている佐賀県佐賀市。
そんな佐賀市で、2022年、1,400品目を超える全てのお礼品を試食・確認する大規模なお礼品審査会が実施されました。審査会実施の背景や想いについて、佐賀市ふるさと納税推進係 杠 精士郎さん、増野 秀則さんに伺いました。

豊富な特産品に恵まれた土地 佐賀
「素材そのもので勝負できる自信があります」(増野さん)
山と海に面した自然豊かな土地には、「佐賀牛」や「お米」のほか、2022年まで19年間連続で生産量・販売額日本一を誇った「佐賀海苔」などの豊富な特産品があり、その品質は高く評価されています。またそれらを使用した「加工品」や「バスクチーズケーキ」などのスイーツも人気です。
 佐賀牛
佐賀牛
 バスクチーズケーキ
バスクチーズケーキ
食以外の分野では、筑後川をはさみ隣接する大川家具とともに発展し、今なお伝統的な技術・技法で製作される「諸富家具」、江戸元禄時代より佐賀藩鍋島家の献上品として用いられてきた「鍋島緞通(なべしまだんつう)」と呼ばれる敷物、などといった工芸品を通し伝統を今に受け継いでいます。

諸富家具
 鍋島緞通(なべしまだんつう)
鍋島緞通(なべしまだんつう)
ふるさと納税の取り組み
豊富な資源に恵まれている佐賀市は、2008年からお礼品提供を始めました。しかし当初は、世間一般に制度自体が認知されておらず、賛同していただける事業者は少なかったそうです。
そうした中、複数のポータルサイトへの掲載を始め、市として独自にお礼品のカタログを作成。特産品が多いがゆえの見せ方の工夫もされています。
「それまで一覧化はされていたものの、文字も写真も非常に小さなリストと言うべきものだったのですが、新たなカタログでは代表的なお礼品を選定し写真を大きくしたことで実際にイメージしやすくなり、寄付者様にとっても選びやすくなったのでは」と杠さんは語ります。
「さとふるから見せ方・出し方など提案をいくつもいただけることがありがたいですね。HPでの掲載方法や、同じお礼品でも(個数や味違い、価格帯などの)バリエーションを作るなど、佐賀市のふるさと納税増加の後押しになったと感じています。」(杠さん)
間口が広がった結果、2020年にはそれまで800品目ほどだったお礼品数を2倍近くの1,500品目まで増やすことができ、寄付額も徐々に増えていきました。
2023年4月にはふるさと納税推進係ができ、本格的に力を入れていくことになったそうです。
きっかけは複数自治体への総務省指導
順調にお礼品数と寄付額を増やしていた佐賀市ですが、大規模な審査会を実施するにはどのような経緯があったのでしょうか。
2019年6月に総務省から「お礼品は寄付額の3割以下に」との明確なお礼品基準が提示され、2022年に基準違反した自治体が指定取り消し処分となる事案が複数報道されるようになりました。
ふるさと納税制度を継続するにあたって「指定取り消しは最も避けなければいけない事態。今回の指定取り消しにおいて指摘されている課題は無視できない、自治体として責任を持つことが大切だ」と改めて感じられたそうです。併せて、それまでデジタルデータベースで行っていたお礼品の審査について、「エントリーシートの説明と写真だけで判断しては、きちんと市のふるさと納税のお礼品として審査したとは言えないのではないか」と考え、これまで審査したものも含め、お礼品を改めて見直す、という決断に至ったのだと教えてくれました。
お礼品審査会の見直し ~1,400品目以上の全お礼品を審査~
佐賀市はそれまでの市内部で完結するお礼品審査会を見直し、新たに佐賀市観光協会を主体とする、観光協会メンバー、自治体職員、有識者を中心とした審査会を設置。ふるさと納税の寄付が増える11月頃までに登録している全お礼品を再度審査するべく、8~10月にかけて週の半分以上を費やし、3~6名の2班体制で審査会メンバーが実際にお礼品を試食、確認し審査を行いました。
「当時は掲載しているだけでも1,400を超えるお礼品があり、限られた日数で全てを審査するのは本当に大変でした」(増野さん)
事業者との連携や審査会実施を通し、どのような変化があったのでしょうか。
 審査会の様子
審査会の様子
 訪問審査の様子
訪問審査の様子
自治体×事業者双方にとっての相乗効果に
審査会を実施するにあたり、お礼品の提供や、アクティビティなど体験型の場合は現地での受け入れ対応など、当然事業者の協力は必要不可欠となります。
「審査会実施の意義についても事業者様へ丁寧に説明することで佐賀市のふるさと納税への取り組み姿勢が伝わったと思います」(増野さん)
また全てのお礼品を見直したことをきっかけに、品目数が多く類似品も多いお礼品が寄付者様に逆に選びにくいのではないか、他にも開拓するべきジャンルがあるのではないか、といった課題に気付き、市としても掲示方法やお礼品選定を再考するようになったそうです。
また審査会で見つかった気付きや課題点は事業者へフィードバックし、商品の見直し・改良といったブラッシュアップにつなげているそうです。こうしたやり取りの中で自治体・事業者双方のコミュニケーションも活発になったそう。
このようなサイクルが回ることで、地元の事業もより活性化され、新たなお礼品が生み出される仕組みのきっかけにつながったのだと思います。
「元来事業者様には、ふるさと納税という制度がいつまでも続くものと考えず、むしろこの制度をチャレンジの場として活用してほしいという想いが根底にありました。これまでEC事業に無縁だった事業者様も少なくなく、例えば目を引く写真の撮り方や加工方法、最後まで読んでもらえるサイトの見せ方などを習得し、もし制度が終わったとしても、ふるさと納税を通じて培った知識や経験が事業者様の財産として残ってほしいと考えています」(増野さん)
「市や観光協会にとっても、佐賀市のお礼品の良さや事業者様の想いを改めて認識することができました。審査会の実施は非常に大変でしたが、佐賀市のお礼品は自信を持って寄付者様へ提供できると実感し、実施してよかったと感じています」(増野さん)

光吉農産のみなさん

れんこん生産者の楠田さん
事業者間の交流を通しさらなる地域活性化へ
寄付者様の「佐賀市を応援したい」というお気持ちを何より大事にしたい、という佐賀市。「今年も楽しみにしています」といったお声をいただく機会もあるそうで、リピーターも多くいます。
そんな佐賀市に寄せる期待や寄付者様の気持ちを大事にする佐賀市だからこそ、今回の大審査会の実施につながったのだと思います。
「今回の取り組みを通して、お礼品同士の掛け合わせや新しい食べ方などの嬉しい気付きがありました。今後は事業者間のコラボレーションなどに繋げられたらいいなと思います。今後もふるさと納税制度を積極的に活用し、地域活性化につなげたいと思っています」(杠さん)
今回は、自治体×事業者×寄付者の相乗効果がさらに地域活性につながる、ふるさと納税のよい活用事例をご紹介しました。
お礼品同士のコラボレーションにも注目したい佐賀市に、今後もますます期待が高まります。
▼佐賀県佐賀市のふるさと納税はこちら
https://www.satofull.jp/city-saga-saga/