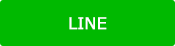2019/10/28
柑橘農家の枠を超え"じゃばら"を広める
紀伊路屋 "じゃばら"の栽培・加工から認知拡大まで
和歌山県広川町に、古代から続く祈りの道、熊野古道の紀伊路で"じゃばら"や"みかん"などの柑橘類を栽培する長谷農園があります。長谷農園の加工品ブランド「紀伊路屋」で特に力を入れている"じゃばら"の商品は、テレビで取り上げられると、瞬く間に品薄となりました。自身のじゃばら栽培や加工業に力を入れるだけでなく、じゃばらの栽培農家を増やしたいと話す代表の長谷光浩さんに、まだあまり知られていない"じゃばら"について、またふるさと納税の活用について伺いました。

長谷農園で栽培しているじゃばら
紀伊国屋文左衛門のように効能を理解して"じゃばら"を届ける
「じゃばらってご存知ですか?」と話し始めたのは、紀伊路屋(長谷農園)の長谷光浩さんです。
"みかん"などの柑橘類に比べ、まだ認知度が低いといえる"じゃばら"は、和歌山県北山村に自生し、いまから約40年前に品種登録された柑橘。登録から20年経つと、育成者権が切れるため、他の地域でも栽培が可能になりました。
じゃばらは非常に酸っぱく、少し苦みがあり癖になる風味が特徴。酸味・苦みがあるためか、みかんなどに比べ獣害被害にあいにくく、育てやすいことが特徴だそうです。
 紀伊路屋 代表 長谷光浩さん
紀伊路屋 代表 長谷光浩さん
あの熊野古道の紀伊路で江戸時代よりも前から、代々農家を営んできた長谷家での柑橘類の販売は現在3代目になるそう。そんな歴史ある農園を管理しながら、じゃばらの栽培を始めるに至ったのは、どんなきっかけがあったのでしょうか。
「重度の花粉症持ちの妹夫婦が、『花粉症にじゃばらが良いらしい』とテレビで見て、じゃばらを買って果汁を飲んだら、症状が落ち着いたそうなんです。そしたら、『作れないの?』と聞かれて、15年前に栽培を始めました。
じゃばらにはナリルチンという機能性成分が多く含まれており、このナリルチンに花粉症の症状を和らげる効果があるそう。果汁にはクエン酸も多く含まれているため、血圧の上昇を抑制してくれるなど、花粉症だけではなく、色々なものに作用があるんだそうです。また、ナリルチンはアトピー性皮膚炎やアレルギー性気管支喘息など、『Ⅰ型アレルギー』に分類される症状にも有効と考えられていて、問い合わせやリピートも多いです」

江戸以前の紀伊路が描かれた古絵図
長谷家の敷地で古くから柑橘自生していたことがわかる
「江戸時代の商人・紀伊国屋文左衛門は、この和歌山から嵐の中船で江戸やエゾにみかんを届け、巨万の富を築いた人物です。
船にみかんを積むときに船の床に"フナドコ"という柑橘を敷き詰めて、その上にみかんを盛り、エゾまで腐らせずに多くのみかんを届けたといわれています。そのころから"フナドコ"の抗酸化作用や、腐敗を防ぐ効果があることを知っていたのかもしれません。紀伊国屋文左衛門のように効能を理解して、うまく商品化へ結び付け、機能性の高い品を世に届けていきたいですね」
一年中"じゃばら"を楽しんでもらうために
栽培の傍ら、収穫した柑橘を使った6次産業化に取り組み、2010年に加工品ブランド「紀伊路屋」を立ち上げます。
「通常は、果実を市場へ持って行くのが農家の流れです。はじめは自分の思っていた以上の価格が付いたのですが、他県からじゃばらの出荷が増えてくると、思っている価格にならない。また、じゃばらは12月に収穫時期を迎えるので、2月~3月の花粉症の時期まで生のまま保存できないんですよね。年間を通して柑橘類を楽しんでもらいたい、一番良い時期の農産物の加工品を届けたいと思って加工業に挑戦しました。
ちょうどその時広川町の商工会がアグリ塾という勉強会を開いてくれて、3年間実践と座学で学びながらドレッシングなどを作ったりしていました」
じゃばらを作り始め、タイミングよく6次産業化の勉強をすることができたため、じゃばらの加工品を花粉症の時期に、みかんジュースを夏の暑い時期になど、一番ニーズの高い時期に商品を出せるようになったそう。
 「農家が一番忙しいのは収穫時期。多くの農家はその時期に全部出荷して換金する。2か月の収入で1年間暮らしていくわけです。いろんな職業の方から、『その短い期間だけでよう1年食うなあ』といわれることもあります。ただ、冷凍や乾燥技術を使い加工品にすることで、ニーズの高い時期に作業・出荷できるようになるので、作業量と収益の平準化ができるようになります。青果として販売できないものも有効活用できるというメリットも大きいです」
「農家が一番忙しいのは収穫時期。多くの農家はその時期に全部出荷して換金する。2か月の収入で1年間暮らしていくわけです。いろんな職業の方から、『その短い期間だけでよう1年食うなあ』といわれることもあります。ただ、冷凍や乾燥技術を使い加工品にすることで、ニーズの高い時期に作業・出荷できるようになるので、作業量と収益の平準化ができるようになります。青果として販売できないものも有効活用できるというメリットも大きいです」

乾燥されたじゃばらの皮
じゃばらの効能と共に紀伊路屋の商品がテレビで紹介されると、東京にある和歌山のアンテナショップに記録的な行列ができたそう。
「県の方に聞いたのですが、『並んだけど買えなかった』『どうしたらじゃばらが買えるのか』と問い合わせが多く入ったそうです。まだ高い認知とはいえない今でも需要と供給が合っていない状況ですね。おかげで県の方もじゃばらに注目してくださり、職員の方が農園を訪れて話し合ったりしています」

紀伊路屋の商品ラインアップ
左から2番目の"じゃばらグミ"は2018年に
クラウドファンディングで開発資金を募り誕生した
"じゃばら"を全国へ広める
栽培・加工だけにとどまらず、"じゃばら"の普及・認知拡大を目的にしているという長谷さん。もはや一農家の枠を越えた活動をしています。
「通常、柑橘類にはJAさんの栽培マニュアルや指針があるのですが、じゃばらの場合は何もなかったんです。試行錯誤で栽培方法を学び、6年ほどかけて安定した収穫量を採れるようになりました。これから栽培を始める人には資料を作って渡したりして、じゃばらの普及活動を行っています。これ以上うちの農園の生産量を増やすという考えはなく、他の農家さんに仲間に加わってもらって、地域全体でじゃばらの作り手を増やし、生産量を上げていきたいと考えています
計1.5haの地元の耕作放棄地を活用して栽培を進めていて、それらがあと2,3年で実がついてくる。その時に販売に困らないようにと、町の補助金を活用して『広川町じゃばら加工組合』を立ち上げました。だからといって収穫したじゃばらすべてを加工品にしようというわけではありません。その農園ごとに販売に関する考えはあると思うので、栽培の手助けや、収穫したじゃばらを加工品にしたい!といってくれる時に一緒に加工品を作っていきたいですね。こうして作り手を増やし、じゃばらの生産量を増やし、加工品を作って、日本中の人たちが悩むアレルギー対策に活用してもらったり、年中じゃばらを身近に楽しんでもらえるようにしていきたいです」
広川町のある有田郡は、毎年耕作放棄地・廃園が増えているそう。地域の景観を損なうという問題にも関わってきます。耕作放棄地の解消は、どの地域でも重要課題です。うまくいけば、モデルとして全国の農家に参考にしてもらえるようにしたいと話していました。

成分の含有量や効能を教えてくれた
じゃばらの伝道師になりつつある長谷さんは、じゃばらの「おいしさ」と機能性の高さによる健康効果を広く知ってもらうための活動もおこなっています。農林水産省が進める「機能性農産物活用促進協議会」の協力を得て、じゃばらの機能性の高さを研究したり、じゃばらの成分による作用を提示するほか、じゃばらを身近に感じてもらうために、保存方法やアレンジレシピなどを公開しています。
品種のブランディングや機能・効能の認知拡大、品位の向上、消費者のためのアプローチなど、じゃばらの発展を見据えた農業を推進していると感じました。
"じゃばら"の普及にふるさと納税を活用
じゃばらの普及活動に邁進する中で、ふるさと納税のお礼品提供を始めた理由を伺いました。
「じゃばらの生産量拡大の取り組みとほぼ同じ思いです。『じゃばらを広めていきたい』という気持ちで始めました。
ふるさと納税も活用してもっとじゃばらが有名になって、生産量の増加とともに全国へ広がっていたらベストかなと。
ふるさと納税は町のためで、自分たちだけが儲かってもダメだと思うんです。もちろん、売り上げを伸ばし税金を納めるということも、町への貢献では大事だと思いますが、いくら自分のところだけ売り上げがあっても...。地域があって、町があって、そこに自分たちがいる。ふるさと納税という、自治体・事業者・全国の寄付者の方みんなを巻き込む仕組みだからこそ自分たちだけが儲かるというのは違うと思います。
今後、紀伊路屋のお礼品が全国の寄付者に選ばれて、喜んでもらい、それが寄付金・税収となる。結果『町が良くなった』と体感できれば、本当に町に貢献したなと思えると思います」

ふるさと納税ではセットのお礼品が人気
ふるさと納税は、じゃばらを知ってもらえる有効なツールだと、長谷さんはいいます。
「どんなに良い品を作っても、いかに表へ出ていけるか、見てもらえるかが重要ですよね。そういった意味では、ふるさと納税の役割は大きいです。
例えば他のショッピングサイトに掲載する場合は掲載費や手数料、広告費がかかったりします。『さとふる』さんは掲載費用がかからないので、生産者や各自治体のPRに大きなプラスになっていると思います。生産者にとって全国の方の目に触れるというだけでもハードルが高いので...。
それに、『一般のショッピングサイトで人気です』とうたうよりも、『ふるさと納税で人気です』という方が、自治体のお墨付きがあるうえで売り切れているとなると、本当に人気であることに信憑性が増すような気もします」
また、『さとふる』のレビューが参考になったこともあるそう。
「通常の小売りは単品で出していたのですが、ふるさと納税はジャム・果汁・粉末のセットがあって、こういうのが喜ばれるんだなあということを知りました。
高評価なレビューが入るとそれを見て寄付してくださる人もいて、レビューも大切だと思っています。実際に、レビューを見ている事業者は多いです。皆厳しいレビューも含めてチェックしています」
ふるさと納税で未来へ投資
「ふるさと納税は直接寄付者の方へ商品を届けるので、大手の商社や卸先を通すよりも収益が大きいんです。そういう意味でも生産者にはありがたい。ふるさと納税をやっている農家同士では、この話で盛り上がります。
また、『さとふる』さんの場合は、品を用意していれば手配をすべてやってくれる。ほかのサイトでは伝票作成や請求処理などの作業が発生する場合もありますが、『さとふる』さんは生産者が一番不得意なところをやってくれるのでありがたいです」
代行できる業務をさとふるが担い、事業者の方々には自社のために、未来のために時間をかけてほしいと考えるさとふるにとって、とてもうれしいコメントでした。
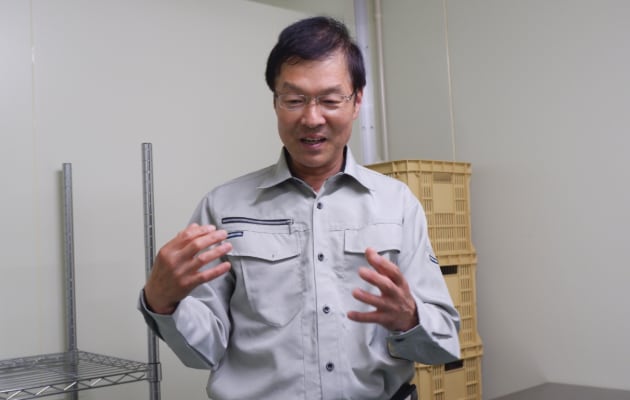
加工品開発や新しい取り組みを進める中で、ふるさと納税が役に立ったと感じることがあるそうです。
「ふるさと納税の収益は、苗木や機械の購入など、今後の加工事業のために活用しています。投資ができる状態じゃないと新しいことを始めたくてもなかなか難しいし、何か始めると何か問題が出てくる。その時に投資できると、機械で解決するという選択肢が生まれました。作業の効率化につながり、お金をつくる循環につながっていますね」
"じゃばら"が広川町に訪れる理由に
地域・町と一体となりふるさと納税を活用し、じゃばらの普及に力を入れる長谷さんに次なる展望を聞きました。
「新しいじゃばらの加工品開発も進めていますが、今は "タチバナ"という柑橘を栽培しています。これには、アレルギーに良いといわれるヘスペリジンという成分が入っています。
また、農研機構でマンダリンに無核紀州を交雑して育成された"かんきつ中間母本農6号"は認知症やアルツハイマーに良いといわれ、シークヮーサーなどにもあるノビルチンという成分を含んでいるうえ、シークヮーサーにはない成分が高濃度で含まれていて機能性の高さに注目しています。今はアレルギーの子が増えていたり、高齢化などの社会問題もある。世の中の問題にフィットする農作物がまだまだあるということなんです。とくにチャンスだと思っています。
これからもまだあまり出回っていない品種の栽培に力を入れ、じゃばらのように栽培技術の公開などを通して新品種の生産量拡大や、その柑橘の普及に力を入れていきたいです」
現在は、じゃばらを求めて県外から訪れる人が増えているそう。じゃばらが広川町に訪れる理由になりつつあることを実感しているそうです
豊富な知識と経験を自分だけのものにせず、品種のため、地域の発展のために活動する長谷さん。
「"じゃばら"といえば長谷さん」といわれる未来も遠くないかもしれません。これからの活躍が楽しみです。