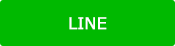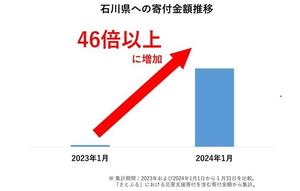2019/02/14
孔子に学ぶ"温故創新"の力を源に、イノベーションを起こす
佐賀県多久市 職員の提案で使途を決定する『多久市職員提案制度』を導入

佐賀県多久市 横尾俊彦市長 釈菜の祭官の衣装をまとって
佐賀県多久市を応援した寄付者には、御礼品と一緒に横尾俊彦市長からの御礼状が届きます。寄付者との1対1の距離感を大切にしている多久市では、ふるさと納税を"温故創新"の力の源として活用しています。
まちづくり、未来づくりの発想の源
佐賀県多久市の多久聖廟(孔子廟)では、毎年、春と秋に『多久聖廟釈菜(たくせいびょうせきさい)』が開催されます。儒教の祖である孔子とその高弟に感謝し、お供えをする式典で、多久聖廟創建以来310年間、毎年欠かさず行われてきました。多久市に寄付されるふるさと納税の寄付金は、この伝統の式典を守るためにも、活用されています。
「孔子の『論語』の中に"温故知新"という言葉がありますが、多久市は"温故創新"でいきたいと考えています。古きをたずねて新しきを創っていくことが大事です」(横尾市長)
燦々と日の降り注ぐ自然豊かな大地、そこに生息する稀少動物、桃やミカン、枇杷などの果物や佐賀牛、古くから続く産業。多久市には、古くから受け継いできた様々な地域資源があります。
「そうしたモノを大切にしながら、日々、イノベーションを起こし、未来想像へのチャレンジをしていく、それが"温故創新"です」(横尾市長)
多久市では、シェアリングエコノミーや、子育て中の母親を中心としたクラウドワーク、着地型・滞在型観光など、新たな取り組みに次々とチャレンジしています。中でも子育て支援には積極的で、地域内の空き教室、空き学校などを活用し、児童センターを新しく整備しました。センター内に設置した木製の子ども用遊具の数々は、ふるさと納税を活用し、整備したといいますが、温かい雰囲気に包まれた児童センターは地域内外の子育て世代に好評だそうです。
多久市を応援するふるさと納税への寄付は、①子どものための事業、②豊かな自然を守るための事業、③文化・スポーツ振興のための事業、④まちづくりのための事業、⑤その他市長が必要と認める事業に活用されます。2016年度から、職員提案制度を設け、日頃、市民と身近な市職員が、いま、本当に市に必要なものを提案する仕組みが開始しました。
取材当日に見学した『多久聖廟釈菜(たくせいびょうせきさい)』の雅楽の楽器購入費用にも寄付金の一部が充当されているそうですが、この活用方法も正に制度で職員が提案したものだそう。

『多久聖廟釈菜(たくせいびょうせきさい)』の出し物
幼児太鼓では、幼稚園生たちが論語をいくつも斉唱しながら力強い演奏を奏でた

地元学生による華やかな釈菜の舞
「本当に市のことを考えている職員にとって、ふるさと納税は新しいアイデアや発想の勇気を与える制度ではないかと思っています。より良いまちづくり、未来づくりの財源、発想の源、力の源となっていると感じています」(横尾市長)
寄付金を誇れるカタチで残す
"新しいふるさと"や"期待を込めるふるさと"を応援するというのがふるさと納税の主旨と考え、多久市では、その想いに正直に応えられるよう、真面目に努力しています。
ふるさと納税を担当する、多久市役所総合政策課係長の瀬戸口泰輔さんは「ふるさと納税では、とかく、寄付を集めることばかりにとらわれがちですが、志を持って寄付いただいたものをいかに活用していくかが、重要だと考えています」と話します。
 多久市役所総合政策課係長 瀬戸口 泰輔さん(左)木下 千賀子さん(右)
多久市役所総合政策課係長 瀬戸口 泰輔さん(左)木下 千賀子さん(右)
ふるさと納税の本来の意図をきちんと捉え、派手なプロモーション等は行わないという方針もあり、寄付金の伸び率が決して大きいとはいえません。しかし、実直な活動の成果は確実に現れており、多久市の柚子胡椒の大ファンになり、毎年寄付して近所にまで配っている東京の寄付者の事例など、嬉しい実績も出てきています。
多久市では、寄付者に横尾市長からの御礼状を送るなど、規模が小さいからこそできる1対1の距離感を大事にし、寄付者との繋がりを大切にしています。
「お礼品の品数や豪華さでは他の地域に負けてしまいます。我々は品数の勝負ではなく、皆さまからいただいた寄付を、寄付してくださった方が誇れるカタチで残していくことを大切にしています」と、瀬戸口さんと同じく総合政策課の木下千賀子さん。
ふるさと納税担当者としては、多久市に寄付した人が、何かのきっかけで多久市を訪れてもらうことが最終目的だと教えてくれました。
「その時に『寄付金はこれに使いました』と、胸をはって見せられるもの、説明できる事業を考えていかなければなりません。カタチに残るモノだけではなく、今後はコトや施策そのものへの活用を高めていくことが課題です」(木下さん)
"縁"を"円"に、小さな繋がりを大切に
ふるさと納税を通じて送られてくる応援メッセージの中には、「祖母が多久市出身なので応援します」といったメッセージもあります。直接的ではなくとも、自分のルーツのどこかに多久市との関わりを見つけ、数ある地域から多久市を選んで寄付をする人がいる。これこそ、ふるさと納税の本来目指していた姿かもしれません。
「モノがもらえるから得ということではなく、いつか自分の人生の中で関わっていたかもしれない地域と繋がれる場所。それが、ふるさと納税なのだと思います」(木下さん)
 瀬戸口さん、木下さんの力強い言葉とまなざしが印象的
瀬戸口さん、木下さんの力強い言葉とまなざしが印象的
現在、20代、30代で多久市に住んでおり、その後、市を離れたとしても、その子どもや孫が「肉親が出身だから寄付します」と繋がっていける。それがふるさと納税の良さであるといえます。
瀬戸口さんも木下さんも、担当者として、寄付者に対し大きな感謝の気持ちを持っていました。
「これだけ色んなサイトの中で、多久市を見つけてもらえたことが奇跡。その縁に感謝して、その小さな縁を大きく広げていければいいなと感じています」(木下さん)
"縁"を繋げて"円"にする。多久市では今後も、小さな繋がりを大切に、実直な取り組みを続けていきます。