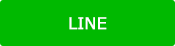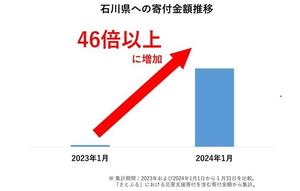2019/01/31
劇的に変化した、事業者・行政間の信頼関係
和歌山県橋本市 「パイル織物」で100億円産業を目指す
地場産業や農業で地域の活性化を図る和歌山県橋本市。
ふるさと納税が制度以前からあった地域資源に光を当て、磨きをかけるきっかけとなり、さらに新たな商品やサービスへと進化させるエンジンとなっています。新たな挑戦を支援する橋本市の取り組みと今後の展望を平木市長に伺いました。
 和歌山県橋本市 平木哲朗市長
和歌山県橋本市 平木哲朗市長
地場産業を元気に
橋本市は2015年4月、官・民が一体となって市の地場産品や特産品をブランド化し、国内外に売り出すことを目的に『はしもとブランド推進室』を設立しました。販路開拓やふるさと納税による地場産品の魅力発信・新商品開発支援など、地域経済の活性化や市内事業者・農家の所得向上を目指し、取り組みを進めています。
「橋本市はもともと、地場産業の技術が非常に高い地域です」と話す平木市長。
日本一の生産高を誇る高野口町の『パイル織物』は、国会議事堂やNHKホールの椅子から新幹線のシート、欧米のアパレルトップブランドの生地まで、幅広く活用されています。また、橋本市の伝統地場産品である『紀州へら竿』は、国の伝統的工芸品にも指定されています。
「『パイル織物』は、もともと約600億円あった売上が約45億円にまで落ちました。『紀州へら竿』も、伝統技術を継承する職人が減少しており、生産能力がどんどん小さくなってきている。地元にある高い技術を持った地場産業をもう一度元気にすることで、地元経済を活性化させていきたい。」(平木市長)

 『紀州へら竿』(上)や『パイル織物』(下)など橋本市には高い技術を誇る地場産業がある
『紀州へら竿』(上)や『パイル織物』(下)など橋本市には高い技術を誇る地場産業がある
地場産業を活性化していくためには、今までと同じものだけでなく、新しい商品を開発していくことも必要です。橋本市では2017年4月、『パイル織物』に対し、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づく『ふるさと名物応援宣言』を行いました。宣言を行うことで、国の『ふるさと名物応援事業』(事業者への補助金)に優先採択されるほか、地域産品のブランド化に対する人材育成研究への優先参加や、中小企業庁のポータルサイトにおける情報発信などのメリットが得られます。
「パイル織物を素材産業から最終製品化まで行うように変えていく取り組みにも力を入れています。商品開発や販路開拓の補助金を使いながら、活性化を図っていきたい」(平木市長)
現在、橋本市のふるさと納税では、『パイル織物』を使ったスリッパ・毛布・バッグなどをお礼品として紹介しています。
付加価値を加えることで地場産業や農家が豊かになる仕組みを
『パイル織物』のブランド戦略にあたり、平木市長は「同じモノを作っていても売れる時代ではありません。付加価値の高い、いいモノを作っていく必要があります。薄利多売ではなく、高い技術でいいモノを作って、それに見合ったの価格で売っていく。ターゲットを明確にした商品販売を行っていきたい」と話します。
国の伝統的工芸品である『紀州へら竿』は、竿1本を完成させるまでに約130の工程があり、その全てを手作りで製作している。この特長を活かし、竿づくり体験など、観光と合わせた打ち出しにも挑戦中です。

『紀州へら竿』の制作の様子
"橋本ブランド"の認知度を高めるため、農作物のアピールにも力を入れています。全国有数の柿の産地である橋本市で栽培されるたねなし柿や紀の川柿、富有柿などの生鮮品のほか、あんぽ柿や柿酢などの加工品も自慢の特産品です。また、和歌山の温暖な気候を活かして栽培される糖度の高い葡萄も自信を持ってお薦めしています。

 橋本市のたねなし柿(上)、ぶどう(下)
橋本市のたねなし柿(上)、ぶどう(下)
寄付を集めるだけであれば、他地域からいいモノを寄せ集めるだけでできますが、橋本市では地元の農作物や地場産品にこだわっています。地元の産品をふるさと納税のお礼品として取り扱うことで、地場産品そのものの価値を再認識することができ、地元事業者により安定した売り上げを確保することができるというメリットもあります。
「じっくりと探していけば、農作物でも地場産品でも、橋本市特有の隠れた原石がもっとあると思います。それらを磨き上げ、新たな商品として販売していくことで、事業者や農家に収益を上げてもらう。ふるさと納税はその手段として非常に有効です。重要なのは、橋本市の名をいかに売っていくか。地域の資源を発見し、発信し、販促する。この三段階が必要です。地場産業と農産物で地域を活性化させ、新しいコトに挑戦できる環境づくりをしていきたいと考えています」(平木市長)
ふるさと納税をきっかけに高まる、民間事業者からの信頼
また、ふるさと納税を進める中で起きた最も大きな変化の一つは、事業者と行政の「つながり」が生まれた、つまり信頼関係を築けたことだといいます。
はしもとブランド推進室が設立された当初は、ふるさと納税にしても販売促進のイベントにしても、募集しても参加する事業者が少なかったようですが、継続的にコミュニケーションを図ることで、相互理解が進み、信頼関係が生まれ、さらにその輪が広がり、ふるさと納税事業に参加する事業者が増えてきています。今では、はしもとブランド推進室が呼びかける事業に積極的に取り組んでもらえるようになったそうです。「ふるさと納税事業を推進することで、橋本市の名が少しずつ広まっているというメリットもあります。"ここにいいモノを出せば売れる"ということで、新たな挑戦に繋がっていく。成果は非常に大きいと思います」。(平木市長)
今後の課題は、農業従事者の高齢化で耕作放棄地が増える中、農業で収益のあがる仕組みを作っていくこと。例えば、シーズンものの柿だけでなく、他の時期に売れる作物も栽培することも重要です。また、生鮮品だけでなく、加工品を作ったり、形が不ぞろいなどの理由で市場からはじかれた野菜や果物を再利用したりといった工夫も必要と平木市長は語ります。
「収益が上がることで、若い担い手がやる気を出して新しいモノを作ってくれれば、耕作放棄地も少なくなります。地場産業の『パイル織物』も、まずは100億円の売上を目指して、新しい挑戦が始まっています。商品開発・販路開拓を支援し、事業者や農家の所得が向上し、地域経済の活性化につながる仕組みを全方位的に取り組んでいきたい。」(平木市長)
橋本市では、市の名をより広めていくため、今後もより一層、ブランド推進への取り組みに力を入れていきます。