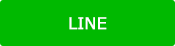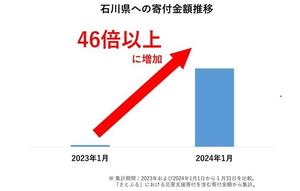2018/12/31
地域間競争に勝つ 自治体×まちづくり会社で取り組む6次産業化
大分県竹田市 400年の歴史を持つ城下町をプロデュース

大分県竹田市は、2018年4月から、まちづくり会社の『まちづくりたけた株式会社(通称:アグル)』と連携し、ふるさと納税への取り組みを強化しています。自治体とまちづくり会社が連携することの強み、現在の課題や将来展望について、竹田市ふるさと納税担当の髙橋さん、まちづくりたけた株式会社の児玉社長、子安マネージャーにお話いただきました。
ふるさと納税の仕組みを再構築
竹田市役所企画情報課TOP戦略推進室副主幹 髙橋英明さん(以下高橋さん):ふるさと納税の制度が始まって約10年。竹田市では、参加いただける事業者がなかなか増えず、お礼品の商品不足もあり、これまで、これといった成果が出ていませんでした。そこで、今年の4月から、まちづくり会社の『まちづくりたけた』と連携し、仕組みを再構築しました。
基本的には、書類の手続きや契約管理は市が担当し、事業者とじっくり向き合う商品開発やPR、参加事業者の募集、及び事業の説明などは、『まちづくりたけた』が担うこととしました。
まちづくりたけた株式会社 代表取締役 社長児玉誠三さん(以下児玉さん):『まちづくりたけた』は2015年に、中心市街地活性化基本計画の推進母体として設立しました。これまで、人材育成や創業・起業支援、空き店舗・空き家対策、観光、雇用・就業促進など、まちのプラットフォームとして事業に取り組んでいましたが、この4月から、「ふるさと納税支援事業」、「不動産活用事業」、「チャレンジショップ事業」、「作家支援拠点施設事業」、「電力小売事業」などを、竹田市との連携により、推進しています。
高橋さん:ふるさと納税で集まった寄付金を何のために使うかというのは重要で、できる限り、地域の課題解決のためのツールとして活用していきたいと考えています。
特に竹田市は、全国の中でも高齢化率の高い地域です。地域課題は広範多岐に亘っていますが、ふるさと納税の趣旨を尊重し、市民に見える有効活用を考えています。また、竹田市は、瀧廉太郎作曲の『荒城の月』で知られる岡城の麓や400年以上の歴史を持つ城下町を中心に、独自の歴史や文化を持つ地域でもあります。そうした歴史・文化振興にもあてていきたい。
連携している『まちづくりたけた』は地域活性のために作られた会社です。お互いの強みを活かし、官民協働の連携により納税者はもちろん、地場産業育成の一助となればと考えています。
地域商社の必要性
まちづくりたけた株式会社 総括マネージャー 子安史朗さん(以下子安さん):ふるさと納税の寄付金額をどう上げていくかについては、様々トライしていますが、中でも現在力を入れているのは、返礼品開拓、表現クオリティ向上、プロモーションの3つです。
大きな企業の少ない竹田市では、農業が基幹産業です。第一次産業に従事しながら加工品を作る人もいるし、加工専門の事業者もいる。どの事業者も商品開発には熱心です。ただ、最後の販路開拓、マーケティングは自分たちでできていないのが現状です。
児玉さん:我々は、ふるさと納税事業を担当しながら、人材育成や起業・創業支援などもしていきますが、ブランド構築、販路開拓、マーケティングといった6次産業化の最後の部分を手助けする仕組みづくりもしていきたいと考えています。
竹田市には小さな個人事業者が多い。地元の素材を生かしたコンセプトの明確な商品ができても、少量しか生産できません。例えば、いい商品ができたら、組織化してロットを確保し積極的に出していく。ブランド化していける仕組みを、ふるさと納税に関わる商品作りを通じて、自治体と連携してできないかと考えています。
私は地域には地域商社が必要だと考えています。地域商社がプロデュースして、市や県、JAなどと連携をとり、いい商品を継続して販売していく仕組みを作る。小さな生産者一人では無理でも、いくつかの商材を地域商社が一緒にプロデュースしていけばいいのです。仕組みとして、地域商社、地域エージェントが必要だと思います。
子安さん:生産者の方の多くは、今は作り手目線で買い手目線がない。ふるさと納税を通して買ってくれる人が多くいると分かれば、買い手目線もできてくるかなと思います。
また、「体験型」のような、外から竹田市に来てもらえるようなお礼品も拡充させていきたいと考えています。竹田市に住んでいる人こそが、その地域性そのものを表しているので、サービスの提供などのお礼品を通して、竹田の魅力を知ってほしいです。
 まちづくりたけた株式会社の皆さん
まちづくりたけた株式会社の皆さん
1+1を4や5に
児玉さん:自治体との連携にあたっては、自治体には自治体の役割があり、民間には民間の役割があると思っています。せっかく地域に素晴らしいものがあっても、それぞれが別々に活動していては十分な力を発揮できない。自治体と民間ができること、得意なことを協力して魅力を最大限に発揮できるようにしないと地域間競争には勝てません。
子安さん:竹田市との役割分担はうまくできていると考えています。事業者とのやりとりは完全にこちらに任せてくれていますし、契約や手続きなど、自治体しかできない部分はやっていただいています。
児玉さん:自治体とまちづくり会社が一緒にやっているという持ち味を生かして、1+1が2ではなく、4にも5にもなっていけばいいと思います。そのことが地域の事業者にも見えるようになれば、商品づくりやふるさと納税への参加も増えてくるでしょう。
寄付されたお金を何に使うか、ふるさと納税の使い道の明確さは重要かと思います。現在は、お礼品目当ての寄付が多いかと思いますが、本来は、竹田市に縁のある人、出身者、竹田市を好きな人が商品に魅力を感じ、竹田市のためにと寄付をするのが正しい姿と言えるでしょう。自分が商品を買ったそのお金が、竹田市のために役立っていることを見えるようにしなければ、ふるさと納税は続いていきません。これは、時間のかかることですが、この制度はそういうことが基本ですので、忘れないようにしなければなりません。
子安さん:どう使うかを明確にしたら、どう使ってどんな効果が出たのか、その後の情報まで丁寧に出すのが、寄付をしてくださった方に対する誠意かと思います。
髙橋さん:連携は始まったばかりです。試行錯誤しながら、地域事業者にも寄付してくださった方にも喜んでいただく、いいカタチに作り上げていきたいと思います。