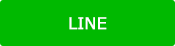2018/06/29
世羅町の気候風土をワインに
せらワイナリー 町産ブドウ100%で醸造
山々が連なる台地に位置し、日照時間が長く、昼夜の寒暖差が大きい広島県世羅町の気候風土は、糖度が高く色や香りが良いブドウの栽培に適しています。
町産ブドウ100%で造られるワインは、町の気候風土や農家の想いを消費者の元に届けています。
「6次産業」で町を活性化
広島県世羅町は人口約1万7,000人の小さな町で、標高350~450mの山々が連なる通称「世羅台地」に位置します。2004年に甲山町、世羅町、世羅西町の3町が合併し、現在の世羅町が誕生しました。
町に2006年にオープンした「せらワイナリー」は、2012年の「日本ワインコンクール」で金賞を受賞するなど、質の高いワインの製造者として注目を集めています。レストランや直売店も備えたワイナリーは、町の中心的な観光施設にもなっており、年間約23万人が訪れます。
日照時間が長く、昼夜の寒暖差が大きい町の気候風土は果樹栽培に適しています。世羅町は従来、ナシの産地として知られていましたが、現在はワイン造りに必要なブドウも栽培しています。町産ブドウは糖度が高く、色や香りが良いのが特長です。
せらワイナリーのワイン造りでは、輸入の濃縮果汁などは一切使わず、町産ブドウを100%使用しています。国内には多くのワイナリーがありますが、地元産ブドウだけでワインを造っているワイナリーはごく一部です。「地元産ブドウ100%のワイン造りを維持できるのは私たちの誇りで、ありがたいことです」と、せらワイナリーショップ店長の小川公美子さんが取材に答えてくれました。
せらワイナリーのワイン造りは、地元農家との共同作業で進められてきたものです。町の基幹産業は農業ですが、1990年代末には「経営が安定しない」、「高齢化で担い手が減少している」など、様々な課題に直面していました。
これらの課題に対処するため、町は農業と加工や流通、販売を一体化して推進し、新たな付加価値を生み出す「6次産業化」の取り組みを開始しました。1999年には、生産者、農園、畜産家、産直市場等による「世羅高原6次産業ネットワーク」が設立されました。6次産業化を進める中、町の新たな特産品づくりを目指して始まったのが、せらワイナリーでのワイン醸造です。
せらワイナリー 小川公美子さん
農家と共に生み出す町の味
町の特産となるワイン造りの計画が始まった当時、町内ではブドウの栽培が行われていませんでした。このため、せらワイナリーの設立と町内の農家でのブドウ栽培は、ほぼ同時に始められました。当初はワイン造りに賛同してくれた数戸の農家で栽培を開始しましたが、その数は現在、約30戸に増えています。
「醸造を始めたころはブドウの栽培量が少なく、一部の商品に他の産地のブドウも使っていました。しかし、その後は町の取り組みもあって生産農家の数や栽培面積が増え、すべての銘柄のワインを町産ブドウ100%で造れるようになりました」
ワインの原料となるブドウを町産に限定すれば、地域の気候の変化がワインの品質にも大きく影響することになります。しかし、他産地のブドウを使って造るワインでは、世羅町の特産品とは自信をもっていえません。また、ワインの味の決め手はブドウであることから、どのようにすれば良いブドウを安定的に生産できるのか、生産農家と共に考えながら試行錯誤を続けてきました。
せらワイナリーのワインに使われている町産ブドウの品種には、ハニービーナスやマスカット・ベーリーA、サンセミヨン、ヤマソービニオンのように日本固有の品種のほか、欧州系品種のシャルドネやメルローがあります。収穫の際はブドウの状態がよくわかるよう、機械は使わず、農家の人たちが時間をかけて丁寧に手摘みします。
また、多くのワインメーカーではワインの品質を安定させるため、醸造段階で補糖、補酸を行っていますが、せらワイナリーでは敢えて補糖、補酸は行いません。これは町産ブドウの良さを活かし、町の気候風土を消費者にそのまま伝えるための取り組みです。

町と共に愛される商品目指す
せらワイナリーでは、世羅ぶどうのPRの手段のひとつとしてワインを生産していることもあり、うまくふるさと納税を活用するようにしていると言います。
「ワインを通して町や私たちを知ってもらい、少しでも名前を覚えてもらえればと思います」
今、ぶどうの生産をされている方々は2006年にワイナリーが立ち上がったときに協力してくださった方々が多いため、現在も応援していただけているという実感があるそうです。ふるさと納税は地域の特産品PRとしても有効なため、寄付者に対しては、寄付をしてワインが1個届くというよりは、町の名前で、世羅町のお礼品が1個届いたんだ、という風に実感してもらえるようになればよいと思うとのことです。
原料となる町産ブドウや醸造段階でのこだわりに加え、商品シリーズの名前やラベルでも工夫を凝らしています。例えば、収穫年や品種、製法にこだわり、世羅ブドウの可能性を丁寧に引き出したシリーズ「セラモンターニュ」では、「山」を意味するフランス語「モンターニュ」を用いて「山」によって生み出された世羅町の土地の個性を表現しました。
また、欧州系ブドウ品種を使用したシリーズ「山のめざめ」は、数々の試行錯誤を重ねた結果、名付けられました。欧州系ブドウ品種を使った醸造では、品質向上に向けて多くの困難に直面してきました。ワインの品質が目標に到達せず、製品化を断念した年もあります。そのような困難を乗り越え、新たな出発をした際の「めざめ」を消費者に感じてほしいという願いから、この名を付けました。
「お客様には世羅町を想像し、『このワインができた町に行ってみたい』と思っていただけたら嬉しいです。また、『世羅町のワイナリーに行って、飲んでみたい』と感じていただきたいという、私たちの想いが伝わるような商品づくりをしていきたいです」
町の特産となる「町産ブドウ100%のワインを造る」という目標は、既に達成しました。しかし、今後もそれを維持し、ワインの品質をさらに向上させていくためには努力も必要です。良質のブドウを栽培してくれている農家では高齢化が進んでおり、後継者の育成も課題となっています。せらワイナリーでは、今後も町の基幹産業を担う農家と共に成長を続け、町と共に愛されるワインを造り続けるための努力を続けていきます。