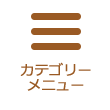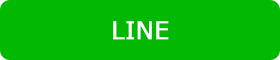北海道恵庭市 市民主導のまちづくりと特産品開発
北海道恵庭市は新千歳空港から電車で約15分、札幌駅から電車で約25分と非常にアクセスの良い場所にあるまちです。市の西側には豊かな自然と四季折々の彩りを感じることができる恵庭渓谷があるほか、個人の庭を開放するオープンガーデンにも全国から見学者が集まるなど、花づくりが盛んなまちでもあります。
「恵庭市の一番の魅力は"市民が主役であること"」と話す、恵庭市 企画課でふるさと納税の担当をされている山本さん、大林さんと、経済部の木下さん、中村さんに、市民が主導となって開始された魅力あふれる活動や、官民一体となって進める特産品開発についてお話を聞きました。

"未来のまちも美しく"個人宅の庭で始まったオープンガーデン
恵庭市は1989年ごろ、全国に先駆けて個人の庭を開放するオープンガーデンを開始し、2019年にはオープンガーデンとして、およそ50軒の個人宅の庭が6月下旬から2か月間にわたって開放されました。また、まちの観光拠点の一つである道の駅の名称が「道と川の駅 花ロードえにわ」となるなど、「花のまち」としての認知が広がっています。
このオープンガーデンの取り組みは、市民の方々が主導して開始されたそう。
「40年ほど前に恵庭市の"恵み野地区"に住宅街が造成され、新しい住宅が作られていったのですが、そこの住民の方々が『今は新しい住宅が立ち並んで美しい街並みだが、建物が古くなったときにこのきれいな街並みをどう維持していけば良いのだろう?』と考える中で、ニュージーランドのクライストチャーチに視察旅行に行った際に、100年近い歴史を持つ家屋がガーデニングに飾られ、美しい街並みを作り出していることに感動して、『これをぜひ恵庭でも広めていこう』と考えたそうです」(大林さん)
偶然にも恵庭市は「恵まれた庭」と書きます。このことから話を聞いた周辺住民も賛同し、個人宅でそれぞれガーデニングを行い、コンテストなども実施することで徐々にそのガーデニングの美しさの認知が広がっていったそう。そうすると、市外からバスツアーで個人宅のオープンガーデンを周るバスツアーが行われるほどの人気となりました。
 美しいオープンガーデンの様子
美しいオープンガーデンの様子
市民発信の取り組みにより観光客が集まるようになったことで、まち全体として「花のまち」としての取り組みが広がっていき、2020年11月には恵庭市に新たな観光スポットとして花の拠点「はなふる」がオープン。「道と川の駅 花ロードえにわ」などに隣接して7つのテーマガーデンから成る「ガーデンエリア」や、子どもの遊び場であるえにわファミリーガーデン「りりあ」などの新規施設が誕生しました。「ガーデンエリア」ではプロのガーデナーたちが設計したガーデニングを楽しむことができます。
また、2022年6月から7月にかけて花と緑に関する国内最大級のイベントである「全国都市緑化フェア」が開催予定です。ふるさと納税の使い道にも「全国都市緑化北海道フェア事業」が設定されるなど、恵庭市では「花のまち恵庭」を全国に発信していこうとしています。
ブックスタート事業で、子どもたちの"読書愛"が育つ
市民主導で広がった取り組みは、花に関するものだけではありません。恵庭市には「読書のまち」でもあり、 "ブックスタート事業"はそれを象徴する取り組みの一つです。恵庭市のブックスタート事業は2000年に市立図書館とそこで活躍するボランティアの方々や保健センター職員の「大切な"初めての絵本との出会い"を支援したい」という思いから始まりました。
そもそもブックスタートとは、1992年にイギリスのバーミンガム市で開始されたもので、地域に生まれたすべての赤ちゃんと保護者を対象に絵本を渡し、絵本を介して赤ちゃんと保護者がゆっくり心を通わせる時間を持つことを呼び掛けた活動です。当時、急速に移民が増加していたイギリスでは、識字率の低下が社会問題となっていました。
英語を母国語としない移民の親子に乳児期から絵本に触れる機会を設けることで、すべての赤ちゃんに平等に文字や言葉に出会う機会を提供することを目指して始まったのがブックスタートです。
日本におけるブックスタートは2000年の「こども読書年」で紹介されたことを機に全国各地で広まっていったといわれており、同年、恵庭市では全国に先駆けて本格的なブックスタート事業を開始しました。
「日本では移民の語学力という課題は大きくなかったものの、当時のブックスタート関係者の方々は『子育て中のお母さんの孤独に寄り添う手段として、日本でも活用できるのでは』と考え、取り入れ始めたそうです」(大林さん)
図書館といえば、「静かに本を読む場所」というイメージも強い中で、恵庭市立図書館ではブックスタート事業を導入する以前から、「ベビーフレンドリーライブラリー」を目指し、赤ちゃん連れの家族が訪れやすいよう、ベビーカーの設置などを通して、「赤ちゃんを図書館につれてきていいですよ」というメッセージを発信していました。ブックスタート事業で、赤ちゃんの健診時に市からの絵本のプレゼントと共に、図書館での読み聞かせプログラムなどを入れることで、より多くの親子にメッセージを発信することができるようになりました。
 図書館での絵本の読み聞かせの様子
図書館での絵本の読み聞かせの様子
ブックスタート事業の効果は、子ども連れの図書館利用を呼び掛ける効果だけではありませんでした。
「絵本を通して、お父さんの育児参加を促す効果があったほか、ブックスタート事業で小さい頃から読み聞かせに触れてきた親子や地域ボランティアの方々からの『学校にももっと本を』という声に、恵庭市では道内で初めて市内すべての小中学校の図書館に専任の学校司書を配置しました。子どもたちの成長に合わせて高校でも様々な読書の試みが進められています」(大林さん)
自治体のサポートで200以上の特産品が誕生
恵庭市内では、アスパラガスやえびすかぼちゃといった野菜から、ハスカップなどの果物や植物まで、数多くの農畜産物がつくられています。
2020年4月にリニューアルオープンした農畜産物直売所「かのな」には、季節ごとに約300種類の野菜のほか、果物や加工食品、花の苗や肥料など、バラエティ豊かな産品が並び、連日それらを求めて、市内外から多くのお客様が訪れるそうです。
 たくさんの種類の花や野菜が並ぶ、農畜産物直売所「かのな」店内
たくさんの種類の花や野菜が並ぶ、農畜産物直売所「かのな」店内
そんな豊かな恵庭市の農畜産物などの地域資源を活かした産業間連携による商品・サービスの開発を目指して2013年に「恵庭市農商工等連携推進ネットワーク」が設立されました。「恵庭市農商工等連携推進ネットワーク」の活動は恵庭市の商工労働課が事務局となっていて、加入者による商品開発の支援や勉強会の運営のほか、ホームページ運用などの情報発信を行っています。
今回、お話を聞いた木下さん、中村さんは市の経済部商工労働課に所属し、この「恵庭市農商工等連携推進ネットワーク」の活動を進めています。市が地域の事業者活動の支援に取り組む背景について、木下さんは以下のように話します。
「もともと、恵庭市の事業者の方々は各社で積極的に商品開発に取り組む素地があり、我々も素晴らしいことだと考えています。我々行政がマッチング支援や各種支援制度をご紹介することで、各社の活動をより効果的かつ加速させていくお手伝いができていると考えています」
市が行っている支援はマッチング支援や各種支援制度の紹介だけにとどまりません。
「参加事業者数の増加と共に商品数が増えていることは喜ばしいことですが、各事業者さんが努力の末に商品開発を行っても、その先の課題になりがちなのが『販路』の部分です。我々も商談会や、市内のアンテナショップ、道の駅での商品販売の案内のほか、恵庭市と静岡県藤枝市の共同オンラインショップやふるさと納税への出品を促すことで課題解決のお手伝いをしています」(中村さん)

恵庭市と静岡県藤枝市の共同オンラインショップ「藤の恵」
設立当時、33団体だった参加事業者は現在101団体(2021年5月時点)に増加。これまでにえびすかぼちゃを使ったプリンや洋菓子を始め、恵庭市産の小麦「ゆめちから」を使用したパスタなど、「恵庭市農商工等連携推進ネットワーク」を通して生まれた商品は、なんと200を超えるそう。参加事業者からは「勉強会や交流会を通して新たな発見が生まれた」といった声や「新しいつながりを持つことができた」などの声が寄せられています。
2020年は新型コロナウイルスの影響で対面を伴うイベントや事業が中止になってしまった面もあったそう。2021年はオンラインなども活用して、事業者のサポートを行っていきたいと木下さんと中村さんは話します。
ふるさと納税で様々な効果が生まれる
市民主導の取り組みを自治体がサポートし、まち全体の魅力となるよう取り組んでいる恵庭市がふるさと納税に参加したきっかけは、恵み豊かな自然あふれる、市の魅力の情報発信手段を求めたことでした。
「恵庭市は空港にも札幌市にも近く、中継地のまちですが、知名度がなく通過されてしまうという課題がありました。しかし、恵庭岳を源流とした恵庭市の水の美味しさから食品関係の企業の工場が多数あるだけでなく、季節ごとに彩り豊かな食物を楽しむことができ、美しい花々を見ることもできます。そういった恵庭市の魅力を、ふるさと納税を通じてもっと情報発信していきたいと考えました」(大林さん)
「さとふる」に掲載している恵庭市のお礼品には今回の記事で紹介した「恵庭市農商工等連携推進ネットワーク」を通じて開発された商品を始め、米や野菜、ジェラートといった食べ物だけでなく、市内のフラワースタジオで制作されているプリザーブドフラワーなど、多種多様なお礼品があります。

恵庭市産のえびすかぼちゃを使用した「かぼちゃぷりん」
また、寄付の使い道も子育て支援事業や農業振興事業のほか、2022年に恵庭市で開催予定の「全国都市緑化フェア」の準備や運営に使用される、全国都市緑化北海道フェア事業など9種類の使い道から選択することができます。
最近では、市内の公共機能の一部が集約した複合施設「えにあす」内にある市立図書館恵庭分館のリニューアルに寄付金が活用されました。
リニューアルによって、出入り口が増えたり、分館のエリア以外にも「えにあす」施設内で本を楽しめるようになったりと、開放的で訪れやすい雰囲気になったほか、道内初の"手のひら静脈認証システム"も導入されました。"手のひら静脈認証システム"導入により、利用者は専用装置に手のひらをかざすことで本を借りられるようになるなど、住民の公共サービスの利便性の向上や、コミュニティづくりに活用されています。
 リニューアルによって訪れやすい雰囲気となった、市立図書館恵庭分館
リニューアルによって訪れやすい雰囲気となった、市立図書館恵庭分館
また、寄付金の活用といった面だけでなく、ふるさと納税は交流人口の増加や市内事業者との新たなつながりを生み出すといった面でもメリットを感じているそうです。
「『自分の好きなビールの北海道工場が恵庭にあることを、お礼品をきっかけに知りました』という声や、『恵庭には行ったことが無いけど、近くに行ったときには寄ってみたいと思います』というコメントをいただくと、職員としてはやる気が出ますし、恵庭市に関わってくださる人たちが増えたのではと感じています。また、以前は主に経済部のみが地域の事業者さんと関係していましたが、ふるさと納税のお礼品への出品をきっかけに、ふるさと納税を担当している部署とも関係ができ、新たな取り組みにつながる可能性もあります。そして、お礼品事業者さんに低リスクで販路を拡大していただくことができるなど、ふるさと納税がきっかけとなり、様々な点で地域活性につながっていると思います」(山本さん)
恵庭市は2020年に市制50周年を迎えました。住民が約7万人のまちは、人々のつながりが強く、程良い距離感のネットワークがあると山本さん、大林さんは話します。
住民一人ひとりが主役となって、まちの多彩な魅力を作り上げている恵庭市。全国的な感染症の拡大もあり、旅行は難しいかもしれませんが、まずはお礼品などで地域の魅力に触れ、自体が収束したあかつきには、北海道で訪れるスポットの候補に加えてほしいと思います。