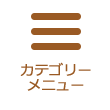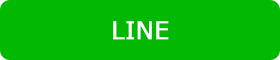島根県雲南市 若い世代の力を地域に活かす
雲南市は、子ども、若者、大人による3つのチャレンジを連鎖させ、市民が支え合い、いきいきと暮らせるまちづくりで全国から注目を集めています。
ふるさと納税の寄付金は、多くの市民や事業者のチャレンジ支援に活用されています。
今回、UIターンで市内に居住するようになった若者や、市民を支援するNPOやコミュニティナースの活動について話を聞きました。(全2話)
「日本一チャレンジにやさしいまち」の秘密(前編)はコチラ>>

雲南市 山王寺棚田雲海
次世代育成事業「幸雲南塾」を運営するNPO「おっちラボ」
NPO法人「おっちラボ」は、若者のチャレンジを応援する次世代育成事業「幸雲南塾」を運営しています。幸雲南塾は2011年に雲南市が開設、2013年4月には、その卒業生が中心となって事業を引き継ぎ、おっちラボを設立しました。
塾には、「地域を元気にしたい」、「楽しいまちにしたい」、「地域の課題解決を仕事にしたい」といった想いを持つ、若い世代が集まります。一人ひとりの目標や思いの実現に向けて、行政、民間企業、NPOが一体となって塾生をサポートし、「学び」、「仲間づくり・市民との連携促進」、「実践・試行の場」を提供します。
現在、おっちラボの代表理事を務める小俣健三郎さんは東京出身で、主に企業法務を扱う弁護士として約4年半働いた後、2015年6月にIターンで雲南市に移住、おっちラボに入りました。
「弁護士の仕事をする中、ゼロから社会づくりを学べる場所で働きたいと考えるようになり、ここへ来ました」と小俣さんは言います。おっちラボでは幸雲南塾の運営や、ビジネスセクター、都市部との連携強化を担当しています。
塾の卒業生の活動は、地域の課題解決につながる様々な動きや起業につながっています。これまで約70のプロジェクトが立ち上げられ、うち約9割もの事業者が現在も持続(※)しています。その事業の中で代表格といわれるのが、地域の中に入り活動する看護師"コミュニティナース"の活動です。
※実施主体が交代したものも含む
地域の人たちの健康を守るコミュニティナース
コミュニティナースは看護の専門性を活かしつつ、病院という場所にとらわれずに、まちへ出て多様なケアを実践する医療人材です。雲南市では今年4月から、市内の3地区に各1人のコミュニティナースを配置。現在配置されている人材は市の「生活支援コーディネーター」としても活動しており、地域自主組織の地域福祉推進員とも協力することで、一方的なケアでなく、住民とパートナーシップを組みながら「毎日楽しい」という状況を作り、住民を健康にするための取り組みを進めています
 波多地区でコミュニティナースとして活躍する柿木守さん
波多地区でコミュニティナースとして活躍する柿木守さん
現在、コミュニティナースとして、市内で活動する柿木守さんも、幸雲南塾の卒業生の1人です。地元出身の柿木さんは島根大学を卒業し、横浜市の総合病院に看護師として勤務した後、Uターンで故郷へ戻りました。今年4月からは雲南市のコミュニティナースとして、市内の波多地区を担当しています。
柿木さんがコミュニティナースとして担当する波多地区は市の端に位置し、かつては約1400人だった人口が300人程度に減少しています。高齢化も進んでいますが、地域自主組織の活動は活発です。地区内にある「はたマーケット」は、地区にスーパーマーケットがなくなったため、住民たちが立ち上げました。また、無料で送迎を行う地域内タクシーや温泉、喫茶やサロンも自治組織が運営しています。
このような中、柿木さんはコミュニティナースとして地域住民に密接な活動をしています。活動では市の保健師をはじめ、消防団や体育協会など様々な分野の人たちとの連携も重要になります。
「コミュニティナースは、日ごろから住民との交流を深める中で、健康教室への参加や検診を促したりします。重症の患者さんを見つけた場合は、保健師さんや病院につなぎ、普段の様子は私たちが見るといった連携も始めています」(柿木さん)
柿木さんと同様に、今年4月から雲南市のコミュニティナースになった宮本裕司さんは、市内の新市地区を担当しています。以前は病院に5年間勤めましたが、「目の前の患者さんで精一杯になり、自分がなぜ看護師になったのかを少しずつ忘れてしまう」と感じていたそうです。
その後は訪問看護で2年間働いてから、雲南市のコミュニティナースプロジェクトの募集に出会い、「自分がやりたかったことはこれではないか」と気づきました。コミュニティナースになってからは、住民の日常的な健康行動をサポートし、見守りを兼ねた配食サービスも行っています。
「地域に出て気づいたことは、住民の方々にとっては、必ずしも健康が第一ではないということです。どうすればその人たちが健康的な生活に近づけるかと考えた時、必ずしも医療の切り口ではなく、その人の得意なことや好きなことにアプローチしていくのが良いと思うようになりました」(宮本さん)
自宅にこもりがちな高齢者もサロンでの集まりに参加し、健康的な生活ができるよう、その人が好きなことを聞いてサロンに取り入れるなど、様々な工夫をしています。また、配食サービスなどを地域住民と一緒に行い、対象者の様子を報告しあう会議も定期的に実施を開始しました。これにより、地域住民がみずから見守りあう環境をつくることを目的としています。
コミュニティナースの活動には、ふるさと納税の寄付金が活用されています。「私の1つの想いは、コミュニティナースのような看護師の新しい在り方、働き方が広がっていくことです」と柿木さんは言います。
看護師の資格を持つ人たちには、病院に就職しても様々な理由で退職し、その後は資格を活かす場がないという人も少なくありません。しかし、看護師はコミュニケーション能力が高い人も多く、地域社会で活躍できる様々な可能性を秘めています。
宮本さんはコミュニティナースとして、「楽しいことをしていたら、いつの間にか健康になっている」という状況を目指しています。地域の人たちと手を取り合い、活動を通じて住民の笑顔を作っていこうとしています。


柿木さん、宮本さん共に地域住民との密接なコミュニケーションの中で活動している