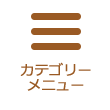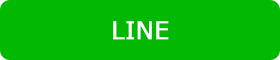まる弥カフェ 地域産品を磨き都市生活者にも喜ばれる商品へ

まる弥カフェのお礼品の一つ、「朝どれ野菜のサラダ便」
高知県と聞いて、多くの人がイメージするもの―それは"幕末の志士"坂本龍馬と"最後の清流"四万十川ではないでしょうか? そのため、龍馬関連史跡の多い高知市など県中部と、四万十川の流れる県西部に人々の関心は向かいがちで、県東部を知る県外の人は決して多くありません。
しかし、実を言えば、安芸市や芸西村をはじめとした県東部は、「ゆず」や「冬春なす」の生産量が全国1位であるのみならず、「白玉糖」や「どろめ」をはじめ特色豊かな農水産物を産出する1次産品の宝庫なのです。
そして、この地域の1次産品を使って、東京などの都市生活者のライフスタイルにフィットする洗練された6次産品を続々創出し、彼らの心をしっかりとつかんでいる女性がいます。安芸市で「まる弥カフェ」を経営する小松恵子さんです。
事業化のキッカケは「龍馬伝」
「私の家は代々、安芸市で暮らしてきました。東京の短大を卒業したあと、県内の銀行に21年間勤務し、その後、林業の経営計画に携わる夫の仕事を手伝っていました」
転機は突如訪れました。2009年、NHKが2010年放映の大河ドラマ「龍馬伝」の制作を発表したのです。この作品は安芸市出身で三菱グループの創始者・岩崎弥太郎の視点から龍馬の生涯を描くものであり、放映が始まれば市内の弥太郎生家には多くの観光客が訪れると県では考えていました。ところが生家周辺には里山の風景が広がるばかりで一軒の飲食店すらありません。
そこで、生家付近で店を開くよう地元の関係者に声がかかりました。
「でも、本当にそんな多くの観光客が来るとは誰も信じられず、やり手がいなかったようで、なぜか私に依頼が来たのです。しかも、放映開始は2カ月後に迫っていました」
小松さんは、それこそ"清水の舞台から飛び降りる"覚悟で、生家前にカフェをオープンします。それが現在の「まる弥カフェ」です。

まる弥カフェ 小松恵子さん
「市役所の駐車場だったところに、自費で急ごしらえの店をつくりました」
放映の効果は著しく、それまで年間1000人だった観光客がいきなり21万人となり、カフェの運営は多忙を極めました。
「でも、龍馬伝の放映が終了すると、生家を訪れる観光客は急激に減少していきました。21万人が翌年には10万人となり、さらに5万人...と減っていきました。カフェが黒字だったのは初年度だけです。それでもあきらめなかったのは、減ったとはいえ、お客様が来てくださっていたからです」
都市生活者にターゲットを絞り"地産外商"
苦しい日々でしたが、2012年、力強い仲間が加わります。県東部の室戸市出身、大阪でパティシエとして修業を重ねていた野村利花さんです。
「まる弥カフェ」をめぐる状況は徐々に変わっていきます。オリジナルの焼き菓子やギフトセットなどが来店したお客さんに好評を博すようになり、同年、東京駅構内の店舗にてビスコッティ(イタリアの焼き菓子)を販売、都内イベントにて出店する機会にも恵まれました。そうした中で小松さんたちの目指す方向性もより明確化していきます。
「一次産品をそのまま出したり、他と同じように地域性を前面に出した素朴な6次産品を作ったりするのではなく、東京圏の私より若い30~40代男女のライフスタイルに適合した垢抜けた商品作りを指向するようになっていきました」
商品コンセプトの洗練はもとより、パッケージのデザイン性、都市の世帯形態に即した商品サイズ、ワンストップで食材が揃うサービス(カツオのたたきなら、その薬味一式も封入)など、顧客のニーズまで察知したサービスを実現していったのです。
2014年には広島出身の浜口あずささんがデザイン・広報担当として加わり、「まる弥カフェ」の発信体制はいっそう強化されました。
そんな、「まる弥カフェ」の商品は、ふるさと納税のお礼品に選ばれたことで、さらに新たな局面を迎えます。
ふるさと納税返礼品に選ばれ実力を蓄える
「『2014高知豪雨』で水害が発生し観光客が激減するという出来事もあって、自然災害リスクのある地域ではお客さんを待っているだけの商売は難しいと痛感していたときのことでした。本当にありがたかったですね」と小松さんは述懐します。
以降、加工食品の製造・販売が「まる弥カフェ」の売上の大半を占めるようになり、売上規模も倍増していきます。
「たくさんのご注文をいただくようになりましたが、一部のふるさと納税サイトでは出荷時期の調整も可能なため、生産体制が追い付けるようになりましたし、食材ロスのない効率的な経営ができるようになりました。地元の生産農家のみなさんも、農産物が今までとは違ったカタチの商品になって県外や東京に出ていくようになったことをよろこんでくれています」
この環境変化は小松さんの心にも大きな変化をもたらしたようです。それまで、光が見えず苦悩も多い日々でしたが、新しい商品を考えチャレンジしていこうという心の余裕が生まれたといいます。
2017年、地元の安芸桜ヶ丘高校から地元名産を使った商品作りの相談を受けます。安芸市と言えば「冬春なす」の生産量全国1位です。野菜嫌いの子供や女性でも美味しく食べることのできる商品として「なすのプリン」を共同で企画・制作したところ、「商業高校フードグランプリ2017」でグランプリと来場者賞をダブル受賞しました。もちろん、ふるさと納税返礼品としても大人気となっています。
 なすをまるごと1本使った「なすのプリン」
なすをまるごと1本使った「なすのプリン」
小松さんは今、県全体を巻き込む壮大な構想を推進中です。
「県内では、せっかく良いものを産出していても自力での効果的情報発信が難しい小さな生産者・事業者が多いのが現実です。そこで "オール高知"でチームをつくり、都市生活者にターゲットを絞り、彼らの生活にマッチするような商品を開発・販売するネットスーパーを来年オープンさせる予定です」
未知の新分野に次々挑戦し続ける小松さん。彼女の快進撃から、いよいよ目が離せません。