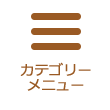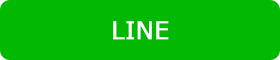株式会社土井農場 安全な自社栽培飼料で育った「諫美豚(かんびとん)」を全国へ
長崎県のほぼ中央に位置し、古くから交通の要衝として大きな役割を果たしているまち、長崎県諫早市(いさはやし)。有明海などの海に囲まれ、北には多良山系に面しており、四季折々の豊かな自然に恵まれています。そんな諫早市で「安心安全な食品を消費者へ届けたい」と資源循環型農業に取り組み、自社で栽培・収穫した米で育てた「諫美豚(かんびとん)」を販売しているのが株式会社土井農場です。今回は、株式会社土井農場の代表取締役である土井賢一郎さんに、資源循環型農業へ取り組む想いや、ふるさと納税から始まった変化についてお話を聞きました。

「もったいない」の精神から生まれた「おいしい」の驚き
県下最大の穀倉地帯でもある長崎県諫早市で、土井さんのご家族は代々米作りを行っていましたが、土井さんの父親の代から養豚を開始し、米作りと養豚を行う複合農家となったそうです。そんな家庭に育った土井さんが自ら農業にかかわり始めたきっかけは、戦時中の日本を描いたアニメ映画の存在でした。幼い子どもが十分に食べることが出来ず、亡くなってしまうという描写に、「同じような思いをする子どもがいないように、自分が農業に携わり、多くの人の健康と命を守りたい」と強く感じたそうです。

株式会社土井農場 代表取締役 土井賢一郎さん
農業に関わるようになってから「どうすれば消費者の方々に喜んでいただけるだろう」と考えた土井さんが挑戦したのが資源循環型農業でした。
資源循環型農業とは、「もったいない」という言葉にも代表されるように、全てのものを資源としてとらえ、それらを無駄なく、循環し活用する日本の伝統的な農法です。土井農場ではもともと米作りと養豚を行っている環境を生かし、豚舎から出た堆肥を水田の土づくりに、水田から出た藁やもみ殻は豚舎の敷物にするなど、副産物を循環させることで捨てればごみになるような資源を有効活用し、農業を行っています。
「時代が進むにつれて飼料や化学肥料、人間の食べる食料まで輸入のものがあふれるようになりましたが、日本の伝統的な農業ではもともと、資源循環型農業が自然に行われていました。自然環境にやさしく、消費者の方々にも安心安全な食べ物を届けたいと思ったときに、資源循環型農業を行うべきだと思ったんです」

土井農場では約800頭の豚が育てられている
土井さんは、この資源循環型農業の徹底を進める中で、堆肥ともみ殻の活用に加え、自社で育てる豚に同じく自社で栽培・収穫した米を飼料として与え始めます。
「当初は余ったお米を『もったいない』の精神で食べさせてみました。もともと、父の代から残飯を豚に与えることがあり、米を食べた豚は成長もよく、味もよいということは感覚としてわかっていたのですが、自社で育てている米で育てた豚を食べてみたら本当においしくて、『こんなに豚肉っておいしかったのか』と味の変化に驚きました」
そう語る土井さん、諫早の恵み豊かな地下水を飲み、水田の副産物であるもみ殻の上でストレスなく育った豚の味に自信を持っていたそうですが、飼料にお米を加えたことで甘味やうまみが増し、上質な脂の味とすっきりした後味になるなど、"別次元のおいしさ"に変わったことに非常に驚いたようです。
その後、県の農業改良普及センターの勧めもあり、自社で栽培する米である「ヒノヒカリ」や「にこまる」のほか、飼料用の専用品種も含め4種類の米をそれぞれ食べさせた豚の味の違いなどの試験を行った土井さんは米の品種でも、豚肉の味に影響が出ることに気付きます。
「試験してみて、『ヒノヒカリ』や『にこまる』を食べた豚などが美味しかった一方で、飼料用の専用品種を食べた豚は全然おいしく感じなくて、『米の品種でここまで味に影響が出るのか』とさらに驚きました。『肉の味を決めるのは飼料なんだ』と確信しましたね」

土井農場で栽培された「ヒノヒカリ」「にこまる」
様々な検討を重ねた結果、土井さんは米の食味ランキング(穀物検定協会選定)で特Aを何度も獲得しており、長崎の奨励品種である「にこまる」を33%飼料に配合した豚を育て、「諫美豚」として世の中に出すことを決めます。
自信の品を全国に広めたふるさと納税
「『諫美豚』の美味しさを世の中に広めたい」そう考え、商談会に参加するなど、積極的な営業活動を開始した土井さんですが、「諫美豚」の味や品質への大きな自信と裏腹に、名前を広めていくことに苦戦します。商談相手から「美味しいけど、それだけでは埋もれてしまう。商品を広めていくためのブランディングは時間も労力もかかるから、まずは安く卸してくれれば、自分たちが宣伝してあげる」といわれたこともあったそう。販路を広げる際、商品の良さやこだわりよりも流通業者との繋がりや価格の安さが求められる場合があり、苦労したそうです。
全国への販路拡大の活路を求めつつ、諫早市内にある自社の直営店舗のほか、近くのレストランや地域のスーパーや直売所で「諫美豚」の販売を行っていた土井さん。販路拡大のきっかけとなったのがふるさと納税だったそうです。

食べると良質な油の甘味やうまみが広がる「諫美豚」
「『諫美豚』の名前を全国の方に知っていただく機会になれば」そう思い提供を始めた土井農場のお礼品は、「臭みもなく、やわらかくて美味しかった」「甘くて本当に美味しい豚肉だった」などの声があがり、全国から申し込みが集まりました。
「私たち農家がものすごくいいものを作ったとしても、流通販路を広げていくのはとても大変ですが、ふるさと納税はいいものがあったらすぐに広まっていく。宣伝のうまさや、安さに頼らずに各地域の良いものを広めてくれる存在だと思っています」
また、売上が向上するだけでなく、ふるさと納税がブランド名を知ってもらうきっかけになっていると土井さんは話します。
「全国の秘書の方が接待の際に選ぶ手土産のおすすめを選ぶ品評会のような機会があり、そこに『諫美豚』のハムを出させていただいたのですが、いらっしゃっていた秘書の方から『諫美豚美味しいですよね』と声をかけていただきました。嬉しくて『なんでご存じなんですか?』と伺ったところ、ふるさと納税で知っていただいたということで、ふるさと納税の知名度の高さに驚いたと同時に、お礼品提供することが自社商品へのブランディングに寄与してくれていることに気付きました」
安心安全の想いを諫早から世界へ
土井農場では「にこまる」を通常の飼料に33%の割合で与えて育てた「諫美豚」、さらには「にこまる」と大豆のみを与えて育てた「諫美豚プレミアム」の主に2種類の肉を販売しています。1頭が一生のうちに食べるお米の量は「諫美豚」で約70kg、「諫美豚プレミアム」で約200kgと膨大であり、土井農場ではその飼料となる米作り・大豆作りも自社で担っている為たくさんの作業が発生しますが、そうまでしてこだわり続ける背景には"世界最高品質の豚肉を作りたい"という想いと共に、"食の安心安全へのこだわり"があるそうです。
「一般的に使用されている飼料の中には、遺伝子組み換え飼料が使用されているものなどもありますが、豚が食べた飼料も含め、最終的には消費者の方々の体に入るので、今後何年も時が経つ中で影響がでる可能性もあるのではと考えています。自ら作ったお米を飼料とすることで、安全な食品を届け日本の皆さんの健康や命を支えたいと思っています」

展示会などで自社商品をPRする地道な努力も欠かさない
(写真は2019年8月に行われた「アグリフードEXPO」出展の様子)
土井さんは、資源循環型農業で育つ「諫早豚」の飼育方法が、食の安心安全につながるだけでなく、日本の食料自給率や、地域農業を守ると話します。
「今、日本の食料自給率は約40%です。この数字はもし輸入が止まった時には6割の国民が死ぬかもしれないという恐ろしい数字です。『絶対にそんなことがあってはいけない。自分が防波堤になって国民の食料を守るんだ』と、今でも思いながら農業に取り組んでいます。『諫美豚』の飼育方法は、食糧不足が来た時、餌として貯蔵したお米を人間に回すことが出来ますし、食料自給率を高めるものです。他にも、近年米農家は米の値段が下がって困っていますが、『諫美豚』と同じように、米を家畜の餌にすることにより、安全安心で美味しい世界最高レベルの肉のブランドを生み出すことが期待できると考えています。その利益が米農家に還元されることで、収入の安定につながります。『地域がブランドを育て、やがてそのブランドが地域を支える』のです」
「諫美豚(かんびとん)」という名前は豚を食べたときに感じる「甘味(かんみ)」と諫早市の「諫(かん)」をかけ「諫早平野の米で育った美味しい豚」という意味でつけられたそう。「諫」という漢字の中には、「諫美豚」の味を作る「米」という文字も含まれています。土井さんによると「九州以外の人にはなかなか読めない」という商品名ですが、これからも「諫美豚」の美味しさや安全さと共に、「諫早市(いさはやし)」の名前が日本全国、さらに世界中に広がっていくことを願っています。