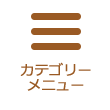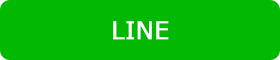漆陶舗あらき 想いがこもったオリジナル商品で全国にPR
石川県の北部、能登半島の中央部に位置する石川県七尾市の七尾一本杉通り商店街にある漆陶舗あらきは、200年以上前の嘉永年間にはその地で商いを行っていたと伝わる歴史ある会社です。伝統工芸品である輪島塗や、漆器・陶器の他にも、地域に受け継がれる風習である「花嫁のれん」をモチーフにしたオリジナル商品を扱っています。「地域に受け継がれる伝統を未来につなげていきたい」そんな想いが詰まった商品開発の裏側や、ふるさと納税をきっかけに起こった変化を、漆陶舗あらきの女将である新城礼子さんに聞きました。

漆陶舗あらき 女将 新城礼子さん
幕末から伝わる"女の一生を踏み出すのれん"
「花嫁のれん」とは幕末から伝わる、加賀藩の能登・加賀・越中で始まった婚礼の風習のひとつで、嫁入り道具として準備され、結婚式の当日に嫁ぎ先の仏間の入り口に掛けられます。花嫁は結婚式の前に花婿の家の玄関先で、「合わせ水」の儀式を行い、両家が挨拶を交わした後、白無垢に着替えた花嫁が「花嫁のれん」をくぐり、嫁入り先の先祖のご仏前でお参りをした後、結婚式が始まります。

華やかな「花嫁のれん」

のれんをくぐり、その家の一員となることを仏前で報告する
仏間に掛けられた「花嫁のれん」は結界を表すと考えられており、花嫁は"決意"や"覚悟"をもってくぐることから「女の一生を踏み出す」といわれているそうです。
この風習は今でも続いており、花嫁の両親が旅立つ娘を想い準備するのれんは、結婚式の後も大切に受け継がれ、家によっては代々各世代の「花嫁のれん」が大切にしまわれていることもあるそうです。
そんな「花嫁のれん」を、商店街の各店舗や住宅に展示する「花嫁のれん展」を2004年から、七尾一本杉通り商店街で毎年開催しています。
「当初は、嫁入りの時に使われたあと、各家のタンスにしまい込まれていて、なかなか世に出る機会のなかった『花嫁のれん』をお披露目する機会や場所があればと、商店街の中で声を掛け合って始めたのがきっかけです。最初の年は56枚ほど展示することから始まったのですが、展示してみると、意外にも地元の方々が見にいらっしゃっいました」
新城さんは当時の様子をそう振り返ります。そのうちに「うちにもあるから飾って」と地域の方々から花嫁のれんが集まり、回を増すごとに増え続け、今では170枚を超える「花嫁のれん」が展示されます。やがて県外からも美しい「花嫁のれん」を見に人が訪れるようになり、最近では「花嫁のれん」をモチーフにした観光列車や観光バスが走るほど、「花嫁のれん展」は県内外から多くの見学者が集まるようになりました。

開催中、新郎新婦が通りを練り歩く「花嫁道中」も行われる(令和2年は4月29日開催予定※荒天時中止)
試行錯誤の結果出来上がったオリジナル商品
「花嫁のれん展」は毎年ゴールデンウィーク中のみの開催である為、期間外も「花嫁のれん」を見ることが出来るよう、2016年には七尾一本杉通り商店街のすぐ近くに「花嫁のれん館」が開館しました。開館をきっかけに商店街の各店舗でも、「オリジナル商品を出したらどうか」という案が持ち上がり、漆陶舗あらきでもオリジナル商品を開発、「花嫁お椀・花婿お椀」が出来上がりました。
オリジナル商品の開発はこの時が初めてだったという新城さんは、当時の開発のこだわりや苦労について、こう語ります。
「普段から気軽に使っていただけるものをと考えて、最初に花嫁のれんをイメージしたデザインの山中塗のお椀を作りました。まずは花嫁・花婿をイメージしたデザインをデザイナーの方に作っていただき、そのデザインを製品化するために漆器メーカーに相談したのですが、『いや、このデザインは実現できませんよ』と言われてしまって・・・。あとから聞けば、メーカー側にもデザイナーの方がいらっしゃるので、デザインの部分からメーカーにお願いすれば、製品にする際のことも調整しながらデザインを組み立てられたのだと思うのですが、最初はそれも知らなかったので、デザインのイメージを製品上でも実現するために試行錯誤しました」
度々課題にぶつかりながら完成させた「花嫁お椀・花婿お椀」の開発期間は6か月にも及んだそうですが、何とか完成。販売開始後にはお客様の声に答えてお椀の模様が見えるパッケージに改良するなど、細部にもこだわりが詰まっています。
 「花嫁のれん」をイメージして作られた「花嫁お椀」
「花嫁のれん」をイメージして作られた「花嫁お椀」
「『花嫁のれん館』や店舗でお買い求めいただくお客様から、『結婚のお祝いに使いたい』というお声をいただき、贈答品に使えるようなパッケージにしたいと思っていたのと同じタイミングでふるさと納税のお礼品として提供することが決まった為、お祝いに使えて、全国配送ができるようなパッケージをスタッフ一同で考えました。私自身も知り合いの方の結婚のお祝いでプレゼントしたのですが、すごく喜んでくださって、嬉しかったです」(新城さん)
ふるさと納税でお礼品と共に"想い"が伝わる
当初「花嫁のれん館」と店舗のみで販売していた「花嫁お椀・花婿お椀」ですが、ふるさと納税のお礼品として提供を開始したことで大きな反響があったそうです。
「『花嫁お椀・花婿お椀』の他にも、石川の伝統工芸品である輪島塗や、九谷焼など、様々なバリエーションのお礼品を提供しているのですが、初年度思った以上の申し込みがあり、『商品が足りなくなるんじゃないか』と嬉しい悲鳴を上げるほどでした。最初は全国の皆さんにこんなに受け入れてもらえると思っていなかったので、すごく嬉しかったですね」
 店内には色とりどりの九谷焼など、新城さんがこだわりぬいて選んだ商品が並ぶ
店内には色とりどりの九谷焼など、新城さんがこだわりぬいて選んだ商品が並ぶ
たくさんの申し込みが入ることで増加した売上は、続いて開発された「花嫁お箸と花婿お箸」、「花嫁のれんスプーン」などの"花嫁のれんシリーズ商品"のパッケージやギフトボックスの初期投資にも活用されており、商品の付加価値向上の助けにもなっているそうです。
 「花嫁お椀・花婿お椀」と「花嫁のれん ペアスプーン」は石川県の優良観光土産品に推奨されている
「花嫁お椀・花婿お椀」と「花嫁のれん ペアスプーン」は石川県の優良観光土産品に推奨されている
また、ふるさと納税は売上面だけでなく、「花嫁のれん」のPRにもつながっています。お礼品と共に、「花嫁のれん」に関するチラシなども同封することで、受け取った寄付者からは「花嫁のれんという風習を初めて知った」という声や「実際に花嫁のれんを見に、七尾一本杉通り商店街を訪れてみたい」などの声が届くそう。
お礼品の提供を通して、地域が大切に守ってきた風習が全国に知られていっていることについて、新城さんは「七尾一本杉通り商店街は『花嫁のれん』を大事に心に抱き、守っている土地なので、お礼品を通して皆さんにその気持ちが通じたのかなと思うと嬉しいですね。一人でも多くの方に『花嫁のれん』を知っていただいて、そして『花嫁のれん館』や一本杉通り商店街に行ってみたい、訪れてみたい、花嫁のれんを見てみたいという風に思っていただけることが何よりかなと思っているので、今後もふるさと納税を通じ、PRし続けていけたらと思います」と話します。
令和2年の第17回「花嫁のれん展」は4月29日(水)から5月10日(日)まで開催予定。4月29日には晴れの日を迎える新郎新婦が一本杉通り商店街を練り歩く花嫁道中が行われる(荒天時中止)のほか、一本杉通り商店街では「語り部処」と呼ばれる各店舗にて、一枚一枚の「花嫁のれん」が作られた時代や経緯、エピソードなどを持ち主にヒアリングし、見学者に丁寧に伝えているという。ぜひ、地域で大切にされてきた「花嫁のれん」の美しさや、そこに込められた"想い"を体感しに、足を運んではいかがでしょうか。