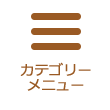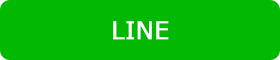のとしし団 農地を荒らすイノシシとの共生
 お礼品として提供している「のとしし(イノシシ)肉」と加工品
お礼品として提供している「のとしし(イノシシ)肉」と加工品
農地を荒らすイノシシが近年、増加している石川県羽咋市。やむをえず捕獲されるイノシシを新鮮な状態で処理し、安全な食肉として製品化する取り組みが進められており、新たな産業や特産品の創出で、地域の課題も解決しようとしています。
地域おこし協力隊が活躍
石川県羽咋(はくい)市では近年、イノシシによって農地が荒らされる被害が相次いできました。この地域ではかつてイノシシが生息していたものの、畑を荒らす害獣として駆除され、明治から大正にかけて絶滅したとされてきました。
しかし、2012年に1頭が捕獲され、2017年には年300頭以上が捕獲されるほど、その数が増加しています。地元の農家の人たちは、農地や農作物を守るため、やむをえずイノシシを捕獲するようになりました。
このような中で、市は捕獲したイノシシを廃棄せず、貴重な資源として活用するための検討に入りました。そして獣肉処理施設を設置し、食肉として活用することが決まり、2015年には「のとしし大作戦」として事業が開始されました。
「のとしし」は、能登のイノシシを意味しています。地元で人気がある獅子舞の演目「獅子殺し」は、田畑を荒らした害獣のイノシシを天狗が退治したという伝承に基づくものです。イノシシ退治は昔から、「五穀豊穣」のために避けて通れないこととなってきました。
獣肉処理施設は当初、市が運営していましたが、2017年12月には合同会社「のとしし団」の設立に至りました。施設の開設時から、事業を支えてきたのが「地域おこし協力隊」です。現在、「のとしし団」代表を務めている加藤晋司さんも、昨年度末まで3年間、地域おこし協力隊の隊員として施設で活動してきました。
 のとしし団 代表 加藤晋司さん
のとしし団 代表 加藤晋司さん
「知人から誘われて、この仕事に関心を持ち、地域おこし協力隊として羽咋市に移住しました。以前は京都の会社に勤めていましたが、新しいことに挑戦したいと思っていました」(加藤さん)
加藤さんにとって特に魅力だったのは、羽咋市では協力隊員が3年の任期終了後も地元で活躍できるよう、事業の立ち上げに参加できるという点でした。「のとしし大作戦」も、その一環として開始されました。
「産業や雇用の創出、特産品づくりという3つが、これによって同時に実現できていると思います。また、地域おこし協力隊の人たちが移住してくれることで、事業の担い手となる若い世代の居住者も増加します」(髙田さん)
のとしし団の事務担当の髙田さんによれば、この事業は地域に様々な効果をもたらすものになっています。とりわけ、畑を荒らす害獣と見なされ、処分されてきたイノシシが、地域活性化への貴重な資源となりました。
2017年に会社が設立されてからは、運営の主な部分は、のとしし団が市から引き継いでいます。他方で市も引き続き、地域おこし協力隊を募集・派遣するなど、部分的な支援を行っています。
地元の猟師と連携し、鮮度の高い肉を届ける
イノシシ肉は当初、飲食店など事業者向けにブロックで出荷していましたが、2016年4月には一般の消費者向けにスライスの販売も始めました。一般向けの販売は現在、農協の直売所や道の駅で行っています。さらに2016年10月以降は、ふるさと納税の寄付者へのお礼品にも採用されています。
イノシシは通常、捕獲されると連絡が入り、電気のやりを使って内臓を傷つけないよう仕留めます。鮮度を保つため、現地で血抜きした上で施設へ搬送します。施設に到着すると、再びきれいに洗い、余計な部位を取り除きます。品質を保つため、前処理は仕留めてから1時間以内で行います。
 肉の解体作業のようす
肉の解体作業のようす
その後は冷蔵庫で冷やし、翌日、皮をはぐ作業を進め、電解水(酸性の水)で洗浄、殺菌します。モモ肉、ロース肉などの部位ごとに切り分けられた後は、金属検出機で検査し、捕獲前に撃ち込まれた鳥撃ち用の弾などがないか、安全確認をします。そして真空パックにした上で、急速冷凍します。
イノシシは地元の猟師が仕留めるため、希望する猟師には、商品としてできあがった肉の最大2割をお礼としてお返ししています。それらを食べた地元の人たちからは「これまでに食べたイノシシ肉と全く違い、おいしい」という感想が聞かれます。鮮度にこだわりつつ、丁寧に処理しているので味には自信があります。取引先は首都圏の飲食店にも広がっており、プロの料理人の間でも好評です。
「イノシシ肉には、食べたことがある人しか手を出さないというイメージがありますが、まだ食べたことのない方々にも、ぜひ試していただきたいと思っています」(加藤さん)
一方、処理されたイノシシの骨や内臓、細かな部分は廃棄物になり、これらは1頭のうち約60%を占めています。このため、のとしし団では、これらを炭素化し、土壌改良剤として地域の農家で使ってもらう取り組みもしています。

革小物の生産も行っている
革は程よい固さで、色のバリエーションが豊富
ふるさと納税で出荷量が増え、冬場の仕事が増加
のとしし団で取り扱うイノシシの量は現在、地域で捕獲されるイノシシの2割程度にとどまっていますが、今後はその量を増やそうとしています。ふるさと納税のお礼品になったことで、出荷量や売上が大きく伸びました。ふるさと納税のお礼品では、年末の出荷が多いことから、特に冬場の仕事が増えたと言います。
のとしし団の事業は、地元の猟師や農家の人たちに支えられ、市とも連携して成り立っています。
「地域の人たちに支えられている事業なので、今後もしっかり維持していかなければいけません」(髙田さん)
現在は当初から人数も増えて5人で活動しており、今後は特に首都圏を中心に販路拡大を目指します。さらにイノシシの皮を活用した革細工などによって、地域の特産品を増やしていこうとしています。
 のとしし団で働く皆さん
のとしし団で働く皆さん