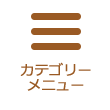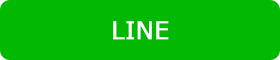信州のりんご 与古美 高級リンゴの栽培

信州のりんご 与古美のシナノスイート
南アルプスと中央アルプスに囲まれた長野県伊那市の「信州のりんご 与古美(よこみ)」は、その技術と経験を活かし、高級リンゴを作り続けています。高効率で収益性の高い農法を採り入れ、農業や地域を盛り上げていこうとしています。
数々のコンクールで受賞
長野県伊那市の「信州のりんご 与古美」は、希少品種「あいかの香り」など数々の高級リンゴを栽培しています。南アルプスと中央アルプスに抱かれた、自然豊かな地域にあります。
屋号の「与古美(よこみ)」は「古き美しい物を与える」という意味で、13代の歴史があります。リンゴ栽培は戦後まもなく11代目が始め、その後は規模を拡大してきました。現在、与古美の代表を務める13代目の伊藤剛史さんは、以前は税理士事務所に勤めていましたが、5年前から与古美を継いでいます。
「高齢化で長野県のりんご農家が減少する中、祖父が始め、父が受け継いできたリンゴ農家がなくなるのは悲しいと思い、後を継ぐことに決めました。」

信州のりんご 与古美 伊藤剛史さん
家業を継いだ伊藤さんは今、リンゴ栽培の奥深さを実感しています。おいしいリンゴを作るにはコツがあり、最も重視しているのは木の樹勢(じゅせい)だと言います。樹勢は「木の勢い」で、これをいくらか弱めて「適樹勢」を保つことで、おいしいリンゴができます。
確実な技術と豊富な経験に基づいて栽培される与古美のリンゴは、「長野県うまいくだものコンクール」で5年連続入賞しているほか、長野県知事賞など数々の賞を受賞し、高く評価されています。
減農薬栽培にも取り組み、農薬は通常の農家が使用する量の3分の1以下に抑えています。栽培品種には「サンふじ」や「シナノスイート」、「シナノゴールド」などのほか、あいかの香りのような希少品種もあります。
あいかの香りは、長野市のリンゴ農家で偶然、生まれた品種で、約15年前に種苗登録されました。大玉で糖度が高く、甘みが強いのが特長ですが、着色しにくいため、あまり栽培されていませんでした。そこで、与古美では研究を重ねて鮮やかな赤色の着色を実現し、霜降り状の蜜ができる新品種として生産を始めました。今では、あいかの香りは非常に人気が高い品種になっています。

100%のりんごジュースもお礼品として提供している
主婦も働きやすい職場に
3年前からは、おいしいリンゴを効率的に栽培するため、「高密植栽培」にも取り組んでいます。この栽培方法では、従来のものより狭い80㎝の間隔でリンゴの木を植え、枝を人工的に真下へ下げて樹勢を弱めます。
リンゴ栽培の面積は、伊藤さんが代表に就任した5年前の倍以上に増え、現在は約5ヘクタールになっています。リンゴの木は苗を合わせると、この5年間で約1万本を育てました。
 写真左側に連なる木々が高密植栽培のもの
写真左側に連なる木々が高密植栽培のもの
「ここまで規模を拡大できたのは、ふるさと納税のおかげです」と伊藤さんは言います。3年前ふるさと納税のお礼品に採用されたことで、受注が大きく増えました。また、規模を拡大する中で大きな力になっているのが、パートの主婦の方々です。
「私がリンゴ栽培を始めた際、主婦の友人に『好きな時に来て、好きなだけ仕事をしてくれれば良いので手伝ってほしい』と頼んだところ、友人がSNSに投稿し、やりたいという方々が集まりました。今では、約40人が登録してくださっています」
パートの方々と話をする中で、多くの主婦が「働きたい」と思っていても働けない状況にあるとわかりました。小さい子どもがいると、仕事を探してもなかなか採用されません。そして、主婦の多くが「子どもが熱を出した時に仕事を休めば、周りに迷惑をかけてしまう」と感じていることがわかりました。しかし、与古美のパート勤務は時間がある時に来て、手伝ってくれれば良いという自由さが特長です。
「農業はある程度、長い期間のどこかで作業すれば良いことが多く、時間の融通が利きます。働きたい時に自分の都合に合わせて働けるという条件が、多くの人に受け入れられ、口コミでパートの方々が増えていきました」
パートの方々に依頼する作業の中には、やや高度な技術を要するものもありますが、皆、一生懸命、習得してくれます。パートを含む従業員には、父子家庭の男性や、子どもが大きな病気を抱え、その手術代を払うために頑張っている方もいます。
伊藤さんはこれらの方々と共に働く中で、仕事を絶やすことなく、良い職場環境を作りたいと考えるようになりました。ふるさと納税による受注の増加で、頑張る従業員に、より多くの手当てを還元できるようにもなっています。
「パートの方からは、『ここに来ると癒される』という声もいただいています。仕事は人生の多くの時間を占めるものなので、良い職場環境を作って『仕事が楽しい』と感じていただければ、人生も楽しくなるはずです」

信州のりんご 与古美の皆さま
モデルを立ち上げ、技術を発信
ふるさと納税サイトには寄付者のレビューが掲載されることから、好評なリンゴの品種を把握したり、必要な部分は改善したりしていくこともできます。例えば、お礼品の配送時にリンゴがぶつかって「痛んでいた」というレビューに対応し、包装資材を改善しました。また、ふるさと納税による売上増加で実現した栽培面積の拡大は、周辺の荒廃した農地を借りて行っています。
「従来の農家は小規模で儲からず、その多くが農業をやめていきました。しかし、1件の農家が数ヘクタールの農地を持ち、大規模に経営するスタイルになれば、状況は変化するはずです。リンゴの高密植栽培なら、それが可能です」
少ない労力や費用で多くの収穫があり、「農業は儲かる」というイメージを抱けるようになれば、若い世代にも就農希望者が増えるはずです。伊藤さんはそのために必要となるビジネスモデルを立ち上げ、技術を発信し、農業や地域を盛り上げていこうとしています。