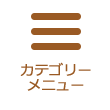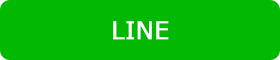ファームランド牧 "ふるさと納税限定"の食べごろがわかるメロン
鹿児島県東部、志布志湾の湾奥ほぼ中央に位置する鹿児島県志布志市。平均気温は16.8℃と暖かく、霧島山系由来の地下水がシラス台地を通して豊富に湧き出ており、鰻の養殖を代表に、南九州随一の農畜産物の生産にとって最高の生育環境が整っています。この志布志市有明町で30年以上、メロン栽培に携わっている株式会社ファームランド牧 代表取締役 牧信一郎さんにお話を聞きました。

さとふるで提供しているお礼品
【わずか5%】鹿児島県志布志産の高級メロン『秘蔵っ娘』(紅白玉各1個・各1.4kg以上)
志布志市お礼品として選りすぐったメロン
1972年から牧さんの父親がメロン農家を始め、親子二代にわたりメロン一筋で続けてきました。牧さんは父親が営んでいたメロン農家を継ぐために1989年に鹿児島に戻りメロン栽培を始め、2009年に「株式会社ファームランド牧」を設立しました。
ファームランド牧のメロンは志布志市有明町の恵まれた自然と大地の中で育まれます。1本のメロンの木に、果実を1個だけ残し、養分をその1個にすべて集めることで、甘く品質の良いメロンに仕上げています。ここで収穫されるメロンの中でも外観・食味・糖度など、独自の厳しい選果基準をクリアした特別なメロンのみに称されるのが「秘蔵っ娘」です。我が娘のように大切に育てられることからこの名がつきました。「秘蔵っ娘」の中でもランクが分かれており、志布志市のお礼品はAランクに該当するメロンで、収穫されるうちのわずか5%ほどしか収穫できない貴重な代物となっています。
 ハウス内の様子 1本のメロンの木に果実を1個だけ残して育てられる
ハウス内の様子 1本のメロンの木に果実を1個だけ残して育てられる
「志布志市のふるさと納税お礼品に相応しくあるためAランクを提供することに決めました。ふるさと納税もギフトと同様に、贈り主と受け取る人がいて、贈り主は受け取る人のことを想い、選ばれたギフトは贈り主の気持ちがこもっています。また、もし贈られてきたギフトがよくない品だった場合、受け取る人の贈り主への心象も悪くなってしまいます。私は贈り主の立場になって、受け取る人が喜ぶもの・美味しいといっていただけるものをつくることに努めています。思いを込めてつくることで、寄付者からの志布志市の心象が良くなり、地域貢献につながればうれしいです」
お礼品には赤玉と白玉のメロンを組み合わせた紅白詰め合わせがあり、赤玉は芳醇で濃厚な甘さ、白玉はすっきりとした甘さが特徴です。
 株式会社ファームランド牧 代表取締役 牧信一郎さん
株式会社ファームランド牧 代表取締役 牧信一郎さん
土壌づくりが生み出したプラスの連鎖
美味しいメロンづくりの秘訣は「土づくりが肝」と牧さんは語ります。
「弊社では定期的に土壌分析し、ミネラル分が豊富な堆肥や有機質肥料をふんだんに使用することで良質な土を保っています。長い年月をかけて有機質を入れることにより、ふわふわの土ができ上ります。一方で、同じ作物を同じ土地で作り続けると、連作障害が発生しやすくなります。これまでは連作障害や病気にかからないように薬剤を使用してきましたが、抵抗性がついてきて薬剤が利かなくなり、次から次へと薬剤を変え続けなくてはならないスパイラルに陥ってしまいます。
そのため、2000年からは減農薬栽培を始めました。当時は微生物による減農薬栽培でしたが、蒸気消毒なども試した結果、現在は『熱水消毒』という方法にたどり着きました。熱水消毒は土壌の深部に約80℃の熱水を注入することで薬剤を使用せずに土壌を消毒する方法です。熱水消毒では、菌の死滅温度が病原菌では45~55℃、有効菌では70~80℃と温度差があることを利用し完全滅菌ではなく病原菌のみ消毒することができます。有効菌を残すことにより有効菌が繁殖し働いてくれることで、病原菌に汚染されにくいよい土地がつくられます。熱水消毒により、土地への負荷が軽減されたことでメロンの出荷率が上がりました」
高い出荷率を保つことで、商談を半年前に済ませておくことができ、安定した雇用にもつながったそう。また、薬剤を使用しないため消費者はもちろん、メロンをつくる生産者の健康への安全・安心も考えられており、さらには環境保全にもつながっています。
 メロン栽培にかかせない土づくり 同社で使用している土はふわふわとしている
メロン栽培にかかせない土づくり 同社で使用している土はふわふわとしている
「熱水消毒はどの農家でもできる方法ではない」と牧さんはいいます。まず大量の水を撒いても流れてしまわない良質な土であることが求められます。同社では以前から土づくりに取り組んでおり、よく吸収・浸透する土であったことから条件をクリアすることができました。次に大量の水を使用することや、設備面において多額の費用が掛かるため資金面をクリアする必要があります。薬剤の費用が7~8万円とすると、熱水消毒では15~16万円と、2倍の費用が掛かります。しかしながら、出荷率は薬剤を使用していたときが70%程度だったのに対し、熱水消毒を使用するようになり90%台まで上がりました。同社は栽培面積が140aと広く、熱水消毒を取り入れ出荷率が30%以上上がることにより熱水消毒で掛かる費用を償却できることが見込めました。これらの条件を満たす農家は限られているため、全国でも熱水消毒を取り入れている農家は数少ないそうです。

熱水消毒に使用する散水機と湯漏れ防止のシート
ほかにも同社には珍しい取り組みがあります。
「従業員の中で最も若い社員は21歳ですが、その社員も含め全社員に年1回人間ドックを受けてもらっています。MRIやCT検査も対象です。年齢に応じた検査項目にすることも考えましたが、若いからといって健康に問題がないとは限りません。農業は体が資本と考えていることから従業員の健康管理も怠らないようにしています」
熱水消毒を採用していることだけでなく、定期的な健康診断受診の取り組みにもメロンづくりに携わる従業員の体への配慮がうかがえました。

株式会社ファームランド牧で働く皆さん
コロナ禍の今だからこそ取り組んだASIAGAP/JGAP※1取得
熱水消毒など同社ならではの付加価値を磨いてきたことにより、2009年の会社設立以降、売上は右肩上がりでしたが、新型コロナウイルスが猛威を振るった2020年は初めて前年よりも売上が下がってしまいました。またふるさと納税においても、在宅で需要が上がったお米などの日常的に食卓に上る食料品の方が選ばれたためか、寄付が減ったそうです。
「一般流通においては特にホテル需要が増える4月に緊急事態宣言が重なってホテルからの受注がほぼ0になり、今まで見たことがないほど経営において大きなダメージを受けました。このことから5月頃には従業員の解雇も検討するほどでした。そこで、今だからこそ取り組もうと思ったのがASIAGAPやJGAPの取得です。農家ごとにそれぞれ拘りはありますが、ASIAGAPやJGAPを取得することで消費者にとってより安心・信頼して選ぶ基準を示せると思ったからです。ASIAGAP・JGAPを取得することにより、商談会での信頼度が向上したことを実感しています。また、従業員においても、明確な基準があること、また基準を守る理由を示すことでモチベーションアップにつながると考えています」
同社はK-GAP※2(かごしまの農林水産物認証制度)をメロン農家の中で最初に取得しました。このこともASIAGAPへの挑戦のきっかけになったようです。
※1 日本およびアジアの農場における、安全な農産物の生産、環境に配慮した農業、農業生産者の安全と人権の尊重、適切な販売管理を実現するため、農業生産者が主体的に活用する農業生産工程管理手法。正しく実施されているかを第三者機関が審査し、認証される。
※2 安心・安全を考えて鹿児島県が定めた基準に沿って、生産者自らが作業を行い、記録し、点検・評価をして、改善していく農業生産工程管理(GAP)の取組を外部機関が審査・認証する制度。

取得したASIAGAPやJGAP、K-GAPの証書
美味しいを追求するために注目した"食べごろ"
ASIAGAP・JGAPの取得以外にも同社で取り組んでいることがあります。
「『美味しいといっていただけるもの』を提供するうえで、人によって硬さの好みが異なることが課題と感じていました。そこで出会ったのが各人の好みに合わせた食べごろを知らせてくれるサービスの導入です。メロンの硬度を元に、硬さの経過(「かため」「食べごろ」「やわらかめ」)をグラフで表示してくれるため、一目で食べごろがわかります。またグラフ上で好みの硬さを設定することで、設定した食べごろの日をお知らせしてくれます。非常に手が掛かるサービスのため限られた数量しか対応することができないのですが、ふるさと納税のお礼品は一般流通と差別化したもの・こだわったものを提供していきたいという想いから現在はふるさと納税のお礼品限定で、このサービスを導入しています」
 QRコードがお礼品に同梱されている
QRコードがお礼品に同梱されている親子二代で続けてきたメロン農家を守っていくために
日本国内の果物の需要は年々減少傾向にあります。同社ではすでにアジア圏をはじめとした海外への輸出を始めており、国内での需要減少も見据えて取り組んでいます。そんな取り組みの裏にはこれまで親子二代で続けてきたメロン農家を守りたいという想いがあります。現在は牧さんの弟や甥がメロン栽培の仕事を手伝っており、牧さんはメロン栽培を「家族が『継ぎたい』と思えるような仕事にすること」を日々課題にしているそうです。農業従事者は年々減少傾向にありますが、牧さん親子が築き上げた土壌や画期的な取り組みをご家族が引き継ぐことで、今後も志布志市の地で美味しいメロンを作り続けてほしいと感じました。