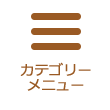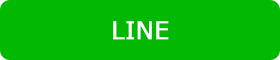村井青果 ふるさと納税をきっかけに、商品への自信を深め、新商品を生みだす

ふるさと納税をきっかけに新しく作成した贈答用のパッケージ
りんご生産量日本一の青森県の南東に位置する南部町。山と川を有する肥沃な土地では果物の栽培が盛んで、県内有数の農作物の産地だ。南部町で親子三代70年に渡って青果卸売業を営む村井さんに、ふるさと納税への参加によって起きた変化や新商品開発について伺いました。
寒暖差は県内一!「南部りんご」の美味しさ再発見
青森県南部町は昼夜の温度差が20度近くなる県内で最も一日の寒暖の差が大きく、りんご栽培に適した地域です。青森のりんごというと津軽のりんごが本場ですが、南部地域もりんごの産地の一つ。青果卸業者として長く南部地域の農産物を扱ってきた村井さんですが、ふるさと納税への参加をきっかけに、自身の扱う商品に対する"意識の変化"があったそうです。
 「うちは卸売りとして、りんごを毎年トラックや貨車で市場へ納入出荷していました。南部地域では、りんごはしっかり実に味が乗ってから収穫するので、お尻の方まで真っ赤でツヤツヤで、『南部のりんごは味がいい』と言われるようなりんごが取れます。うちでは昔から『りんごは量販用』と考えていて、贈答用は販売する発想がなかったのですが、ふるさと納税のお礼の品としてりんごを出してみたところ、寄付者の方からとても良い評価をいただいたんです。ビックリしましたが、このことで『やっぱり美味しいんだ!』と商品への自信が強くなりました。」(村井さん)
「うちは卸売りとして、りんごを毎年トラックや貨車で市場へ納入出荷していました。南部地域では、りんごはしっかり実に味が乗ってから収穫するので、お尻の方まで真っ赤でツヤツヤで、『南部のりんごは味がいい』と言われるようなりんごが取れます。うちでは昔から『りんごは量販用』と考えていて、贈答用は販売する発想がなかったのですが、ふるさと納税のお礼の品としてりんごを出してみたところ、寄付者の方からとても良い評価をいただいたんです。ビックリしましたが、このことで『やっぱり美味しいんだ!』と商品への自信が強くなりました。」(村井さん)
 有限会社村井青果 専務取締役 村井ユリさん
有限会社村井青果 専務取締役 村井ユリさん
ふるさと納税をきっかけに、南部のりんごの美味しさを再認識し、南部町の農産物や自社の扱う商品への自信を得たという村井さん。「青森はりんごを販売している所がたくさんあるし、今更うちが個人向けを販売しても......」と考えていたところから一転、自社のホームページ内にりんごのページを立ち上げ、贈答用りんごの販売を始めます。すると、サイトでの売り上げも上々。今も、「ふるさと納税で村井青果のりんごをもらってよかったから」と2度目の注文を直接してくれるお客様が多くなったそうです。
「うちは卸業者なのでお客様の声を直接聞くことがあまりないため、『美味しかったのでまた買いたい』という言葉をいただくのは嬉しいです。お礼品提供も3年目になって、寄付者の要望やレビューを参考に、毎年少しずつ改良をしています。例えば、以前レビューで、『到着したらお礼品が偏っていた』『梱包がちょっと良くないんじゃないか』という声があったので、りんごの下に敷くダンボールと箱の間に、新たに1枚滑り止めのネットを入れることにしました。これでズレも防げますし、クッション性が高くなったので衝撃にも強くなったと思います。あと、今までは出荷用の一般的な段ボール箱でしたが、お客様にもっとよろこんでほしくて新しい贈答用パッケージも作ってみました。」(村井さん)

干し菊の 「幻の食材」で新商品を開発
既存商品の改良だけでなく、新商品の開発にも意欲的な村井さん。県南地方に根付く食用菊の食文化を広めるため、菊の王様と呼ばれる「阿房宮」という品種の菊を使った商品開発も進めています。これまでも県のサポートを受けながら、2015年には「菊じゃむ」「ほぐし干菊」、16年には「菊サイダー」、17年には「菊粥(がゆ)」と次々と新しい商品を生み出してきました。そして18年、村井さんが新しく開発したのが、「うてな」と呼ばれる菊のガクの部分の佃煮「UTENA(うてな)」です。「うてな」とは「台」と書き、花の萼 (がく)の意味や、仏像などが置かれている台の意味があります。菊の萼をうてなと見立て菊花の蕚の部分を丁寧に炊き上げた佃煮です。
「色々と次の新商品をどうしようかと考える中で、目を向けてこられなかった部分の利用ができたらいいなと思い付きました。うてなは干し菊(食用菊を蒸して乾燥させたもの)を作る時には必要ない部分なのですが、このうてな自体が菊の花の2割程しか取れないので、ある意味、貴重な部分ではあるんです。それで、以前ある料亭さんから『ガクだけを売ってほしい』という注文が入ったことがあって、『何になさるんですか?』と聞いたら、佃煮を作るとおっしゃっていたのを思い出して。あの当時、料亭さんが分けてくださった佃煮の味をイメージしながら、記憶を頼りに作りました。
南部地域では菊の花の天ぷらを食べるので、ガクも食べられることは生産者の方も理解されているのですが、『これだけでも食べられるのはびっくりだ』と驚いていらっしゃいましたね(笑)。視点を変え目を向けられなかった部分を商品化することで、生産者の方の利益にもなればと思っています。」(村井さん)
 「菊粥」と「UTENA」のセット
「菊粥」と「UTENA」のセット
地元の伝統食材「干し菊」を守りたい
近年、干し菊は生産農家が減りつつあります。その現状を見て、村井さんはついに自社で菊を植えることを決めました。2018年春、会社の近くに畑を借りて、菊の栽培を開始しました。初めての菊栽培は全てが手探りで、分からないことばかりだったので、先輩生産者に一つ一つ教えてもらいながら育てたそうです。苦労の甲斐があって、早生種は9月、晩生種の「阿房宮」は11月に収穫。初めての収穫でしたが、「なかなか良い出来の菊」ができたとのことでした。
村井青果の歴史は、昭和20年代初頭、村井さんのおばあさんが行商で関東や関西地方に南部地域の果物や干し菊を売りに歩いたところから始まりました。
「うちの祖母は文字が書けないけど商才がある、この辺りの名物おばあさんでした。祖母の後を父が継いで安定させてくれたので、自分は何か形を変えていけたらなと思っています。」(村井さん)
最後に、卸業で培った目利き力と、おばあさん譲りの発想力と行動力、そしてふるさと南部町を愛する心で商品開発に取り組む村井さんに、今後の展開について伺いました。
「この仕事を始めて20年ですが、作物は毎年同じではないので、勉強はずっと続けていくものだなと思っています。りんごはこれから量産用と共に贈答用も流通に乗せるような展開を考えています。また、菊には抗酸化作用つまりアンチエイジングに役立つだけでなく、頭痛、不眠、ストレスなど、いろいろな効用があるそうで、菊の可能性は無限大だと感じているので、これからも付加価値のある商品を続けて開発していきたいです。」(村井さん)

村井青果の皆さま
写真撮影をしたいとお願いすると、女性陣が笑顔で集まってくれた